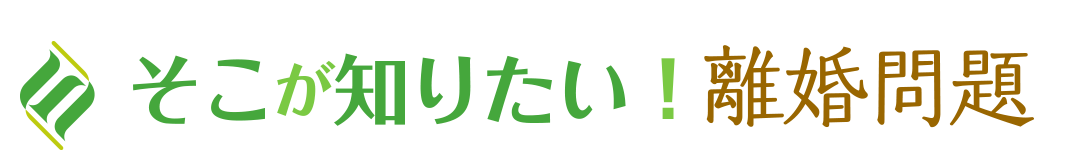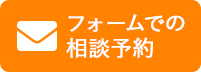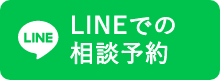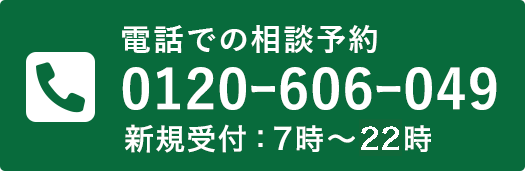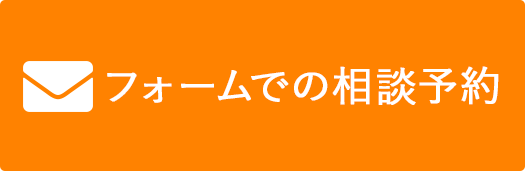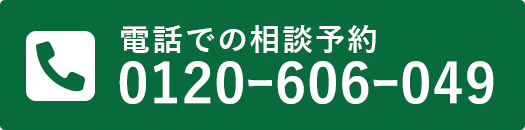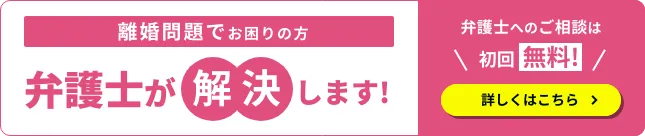

- 養子縁組と養育費の関係について
- 実母の再婚相手が未成熟子と養子縁組をした場合、実父の養育義務が減免される可能性がある
- 養子縁組に伴い養育費を減額・免除する方法とは?
【Cross Talk 】養子縁組があると子どもに対する養育費支払義務はなくなりますか?
養子縁組をすると養育費の支払義務はなくなりますか。
養子縁組によって養育費の負担が軽減される可能性があります。
養子縁組と養育費の関係について、詳しく教えてください。
離婚後に、再婚相手の子どもと養子縁組を行った場合、養育費の支払義務はどうなるのでしょうか。
養子縁組と養育費の関係については、監護親側の養子縁組と非監護親側の養子縁組とにわけて考える必要があります。養子縁組があった場合には、養育費の支払義務が軽減される可能性があるため、この記事で詳しく解説していきます。
養子縁組と養育費の関係とは?

- 養子縁組と養育費の関係について
- 養子縁組によって養育費の負担が軽減される可能性がある
再婚で養子縁組をすると、養育費は誰が払うことになりますか?
ここでは、養子縁組と養育費の関係について解説していきます。
権利者の再婚相手が子を養子にした場合
まず、養育費を請求する権利者の方の親が再婚し、その再婚相手が子どもを養子にした場合について考えていきましょう。このような場合には、養育費を支払ってきた義務者の方の親は、養子縁組によってその義務を免除されることになるのでしょうか。
そもそも、養子縁組とは、養親と養子との間に法律上の親子関係を作り出す民法上の制度です。法律上の親子関係が発生することで、
- 養親と養子は相互に扶養義務を負うことになる
- 養子は養親の親権に服することになる
- 養子は養親の推定相続人になる
という法律上の地位が生じることになります。
養子縁組を行うことで、養親は実親と同様に子どもを扶養する義務が負うことになります。実親と養親の扶養義務の優先順位については、養親が優先すると考えられています。
そのため、基本的には養親だけで子どもを扶養すべきということになるため、養育費の支払いは免除または減額される可能性があります。
義務者が他人の子を養子にした場合
次に、養育費を支払っていた義務者の方の親が再婚し、再婚相手の連れ後と養子縁組をした場合はどうでしょうか。この場合、収入の状況によっては養育費の減額が認められる可能性があります。
養子縁組によって、養親として再婚相手の子どもの扶養義務を負うことになります。そのため、実子と養子の両方に対して扶養義務を果たさなければならなくなり、これまでどおり養育費を負担していたのでは、養子に十分な費用をかけられない可能性が発生してしまいます。
そのため、養育費を支払う義務者の側が再婚し、再婚相手の連れ後を養子にした場合には、養育費の支払いが減額される可能性があります。ただし、収入の状況や家庭の事情によって養育費が減額されるか否かは変わってくるため、必ず専門家である弁護士に相談して確認してください。
実親の扶養義務がなくなるわけではない
養子縁組によって実親の養育費が減額されるとしても、実親の実子に対する扶養義務がなくなるわけではありません。例えば、実母の再婚相手が子どもと養子縁組をした場合には、実母と養父が第一次的に、子どもに対して扶養義務を負うことになります。
そのため、実父の未成熟の子に対する養育費の支払いはいったん消失すると考えられていますが、実子と養父との養子縁組が解消されたり、養父が死亡したりするなど養父が客観的に扶養能力を失った場合などには、未成熟子を扶養するための養育費を負担する義務が復活すると考えられています。
したがって、養子縁組によって実親の扶養義務が完全に消滅するわけではないため、注意が必要です。
養子縁組に伴い養育費を減額・免除する方法とは?

- 養子縁組に伴い養育費を減額・免除する方法とは?
- 養育費減額調停を利用することができる
養子縁組があったため、養育費の金額を見直したい場合にはどうすればいいのでしょうか。
ここでは、養育費の減額・免除の方法について解説していきます。
父母間で話し合いを行う
養育費の支払義務を負っている側が免除や減額を求める場合には、まずは父母間で話し合いを行う必要があります。経済的に支払いが厳しい場合であっても、無断で支払いをストップすることは、トラブルに発展するリスクが高いため控えてください。
養育費の免除や減額を求める場合には、免除・減額が必要な理由や、どの程度の減額を求めるのかを明確にして相手に伝えることが重要です。そして、父母間で養育費の免除・減額について合意できた場合には、その内容を明確にして事後的に紛争が蒸し返されないようにするために、合意書面を作成することが重要です。
養育費減額調停を申し立てる
相手方が話し合いに応じてくれなかったり、養育費の免除・減額を拒絶したりする場合には、調停を申し立てることができます。家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てることで、調停委員会(家庭裁判所の裁判官と一般市民から選任された調停委員2名)が父母の間に入って事情を聴取し、話し合いで解決できる道を探ることになります。
父母間で調停が成立した場合には、合意した内容が記載された調停調書が作成されることになります。
弁護士に相談する
養育費の免除・減額を希望する場合には、弁護士に相談するようにしてください。
なぜ養育費の免除や減額を求めているのか、そのような主張に正当性があるのか、については法律の専門家である弁護士に依頼しておけば、適切に相手を説得してもらえる可能性が高まります。
また、弁護士に依頼することで、相手方との交渉や調停手続についても対応を依頼することができます。相手方との直接のやり取りや面倒な調停手続の準備についても、全て弁護士に一任しておけるため、手続的な負担を軽減することができます。
まとめ
以上、この記事では、養子縁組と養育費の関係について解説しました。離婚した父母が養子縁組を行った場合には、養育費の支払義務が免除または減額される可能性があります。離婚した相手が再婚したことで養育費の支払義務を免れたいという場合には、権利者である相手方に減免を請求していく必要があります。養育費の減免や、相手方との交渉に不安があるという場合には、離婚トラブルに詳しい弁護士に一度相談されることをおすすめします。
当事務所には、養育費に関するトラブルの解決実績のある弁護士が在籍しておりますので、お気軽にご相談ください。