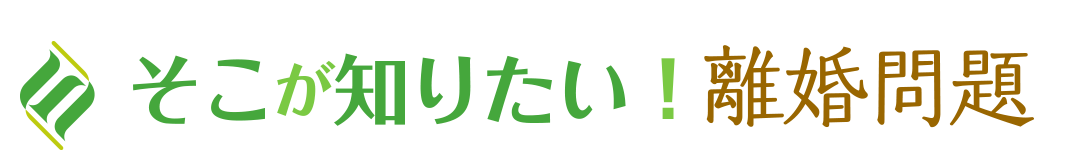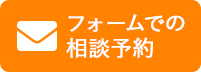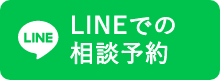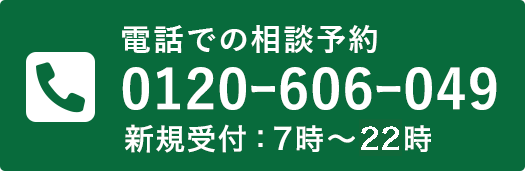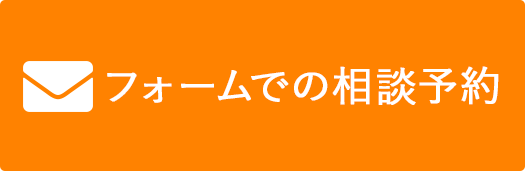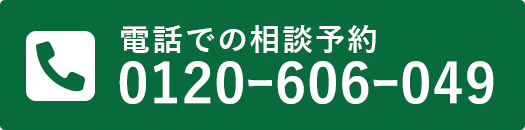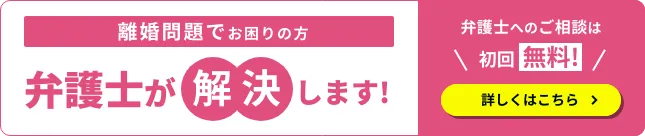

- 離婚は「父母にも自分にも良かった」と答えた子どもが 28.3%、一方で生活水準が(若干)苦しくなった世帯が4割超
- 父母の別居や離婚、お金の問題で悩み周囲に相談できない子どもが多い傾向がある
- 離婚前に親権・養育費・面会交流の取り決めを行い、内容は公正証書に強制執行認諾文言入りで残しておく
【Cross Talk 】離婚や別居が子どもに与える影響は?
夫と離婚協議中です。15歳の子どもがおり私が引き取る予定ですが、離婚が子どもに悪い影響を与えないか不安です。
もしまだお子さんに離婚を伝えていないのであれば、今後について伝え親子でよく話し合ってみてはいかがでしょうか。もう15歳ですので、お子さんの意思もできる限り尊重してあげましょう。
詳しく教えてください!
法務局が公益社団法人商事法務研究会に委託した「未成年期に父母の離婚を経験した子の養育に関する実態についての調査・分析業務報告書」によると、両親の離婚・別居を振り返ると「父母にも自分にもよかった」と回答した人が28.3%という結果でした。一方で、別居により、生活水準・経済状況は苦しくなった・若干苦しくなったという回答は4割超に上ります。
今回は、離婚が子どもに与える影響と子どもに悪影響を及ぼさないために、離婚前・離婚時・離婚後にやっておくべきことを解説していきます。
離婚が子どもに与える影響、調査結果では「父母にも自分にも良かった」が 28.3%

- 離婚・別居が子どもに与える影響、振り返ってみると「特になし」が44.7%、次いで「父母にも自分にも良かった」が 28.3%という調査結果に
- しかし、生活水準・経済状況は「苦しくなった」「若干苦しくなった」が合計 40.5%に。養育費の滞納はおよそ4割に上る
養育費の滞納が多いと聞きましたが、本当ですか?
残念ながら少なくない状況です。「未成年期に父母の離婚を経験した子の養育に関する実態についての調査・分析業務報告書」によると、およそ4割は養育費の滞納があったと見られます。
離婚は「父母にも自分にも良かった」と答えた子どもが 28.3%
法務局が公益社団法人商事法務研究会に委託した事業「未成年期に父母の離婚を経験した子の養育に関する実態についての調査・分析業務報告書※1」を参考に、離婚が子どもに与える影響の調査結果を見ていきましょう。
同調査は未成年時に離婚した子どもが対象で、調査時の平均年齢は29.9歳です。父母が別居を始めた年齢で最も多いのは3歳から6歳(就学前)が19.9%、次いで10歳から12歳(16.7%)、7歳から9歳が15.7%となっています。
「父母の離婚・別居について、今振り返ってみると、どのように思いますか」との問いに、最も多い回答は「特になし(44.7%)」次いで「父母にも自分にもよかった」が28.3%です。
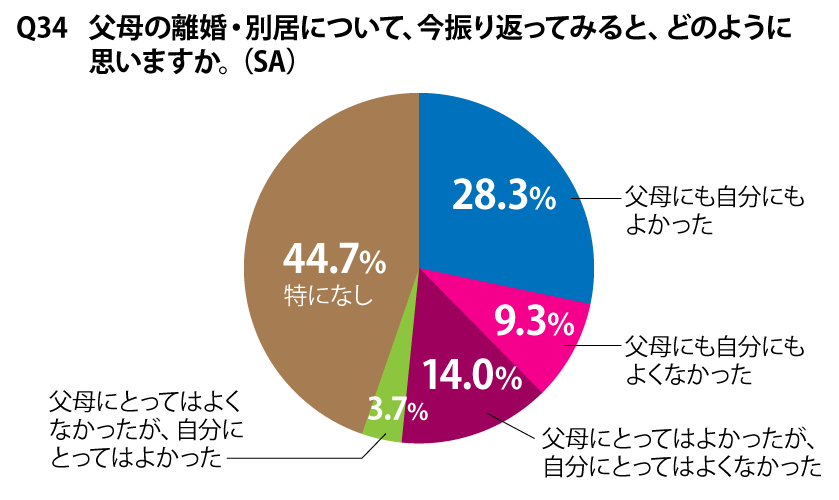
※2
子ども(自分)にとって良くなかったという割合は合計23.3%で、良い影響もしくは特に何も思わないという子どもが7割を超える結果となっています。
父母の離婚・別居が自身の恋愛、婚姻、婚姻生活に対してどのような影響があったかとの問いは「どちらともいえない」「分からない」が合計54.8%、自身の子どもとの親子関係への影響も「どちらともいえない」「分からない」が合計57.1%でした。
生活水準は「苦しくなった」が 40.5%!養育費の滞納はおよそ4割に上る
父母の別居について金銭面の影響を聞くと「別居により、生活水準・経済状況は苦しくなった」が20.4%、「別居により、生活水準・経済状況は若干苦しくなった」が20.1%で4割超という結果です。
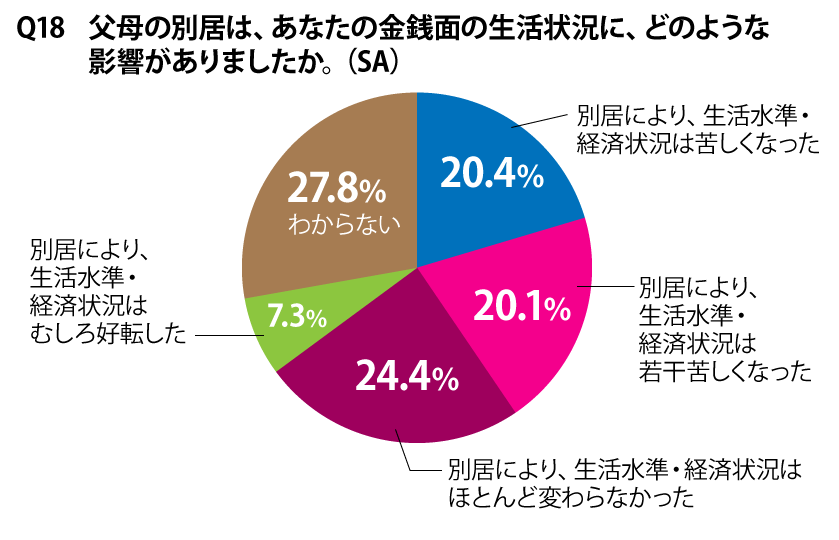
※3
最も多い回答は「分からない(27.8%)」ですが、金銭面では「(若干)苦しくなった」と感じた子どもが比較的多かったことが分かります。
別居した親が同居する親に「きちんと生活費を支払っていた」と回答した子どもは16.8%で、4割は支払いが滞っていた(当初は支払われていたが、その後に支払われなくなった、時々は支払われていた、全く支払われていなかった)ことになります。※4
悩み事があっても相談できない子どもが多い
同調査では、父母が離婚・別居をするときに子どもが誰かに相談したと回答した割合は9.4%でした。
「相談したかったが、適切な人がいなかった(18.6%)」「相談できる人はいたが、自分で抱え込んだ(9.7%)」「人に言いたくなかった(18.6%)」が合計46.9%、で悩みを言えずに抱え込む子どもが多い傾向にあったことが分かります。
父母の離婚・別居後、未成年の間に金銭面で困ったことがあったときにも、「相談したかったが、適切な人がいなかった(12.7%)」「相談できる人はいたが、自分で抱え込んだ(5.9%)「人に言いたくなかった(14.1%)」で合計32.7%と、相談できなかった子どもがいたことが把握できます。
ただし「相談したいことはなかった」という回答が59.6%ですので、金銭面の悩みを感じなかった子どもの方が多かったという結果となります。
子どもに悪影響を及ぼさないためにやっておくべきこととは

- 離婚や別居の理由を丁寧に説明し、変わらず愛情をもって育てていくことを伝える
- 親権・養育費・面会交流を取り決めた後は、強制執行認諾文言を入れ公正証書に内容を残しておく
子どもに悪影響を与えないためにはどうすれば良いのでしょうか?
離婚前には子どもに離婚・別居の理由をきちんと説明し、子どもが不安にならないように変わらず愛情をもっていることを伝えておきましょう。親権・養育費・面会交流の取り決めも重要です。
離婚前にやっておくべきこと
離婚・別居する前には、子どもに父母が離婚・別居する理由を丁寧に説明することをおすすめします。
上記の調査では、両親の別居時に周りに相談できない子どもが多く悩みを抱え込んでしまう傾向があります。子どもに悪影響を与えないために、別居・離婚の理由や今後について説明し変わらず愛情を注いで育てていくことを伝えましょう。
また、離婚前には配偶者との財産分与、子どもの親権・養育費・面会交流について話し合い、取り決めます。相手と何らかの理由で話し合いができないときには、調停で調停委員を通じて話し合うという方法もあります。
離婚するとき、離婚後にやっておくべきこと
離婚時には夫婦の共有財産を分与します。
共有財産とは、結婚中に夫婦が協力して築いた財産です。相続・贈与で得た財産や結婚前の預貯金、ギャンブルで作った借金などは共有財産に含まれません。
結婚中にマイホームを購入した場合は、(1)どちらかが家に住み続けるか売却するか、(2)どちらかが住み続ける場合住宅ローンの返済はどうするのか、(3)家に住み続ける人が名義人になっているかを話し合い決定しましょう。(3)については、例えば夫名義の家を妻に譲り、夫が住宅ローンの返済を約束した場合でも、夫の返済が滞った場合には、銀行が家につけている抵当権を実行することで妻が家から出て行かざるを得なくなってしまうケースもあります。
家の固定資産税も名義人あてに届きますので、名義人と住み続ける人が異なる場合は名義変更を行った方が良いでしょう。住宅ローンが残っている際にはローンの契約を変更しなければいけません。
住宅ローンの残債が家の売却価格を上回るオーバーローンの場合は、売却代金をローン返済に充ててもなお借金が残ってしまいますので注意が必要です。
自身が子どもを引き取る場合、離婚後の子どもの姓・戸籍についても考えておく必要があります。ある程度子どもが大きくなっている場合には子どもの意見を聞きできる限り尊重してあげましょう。
▼関連記事▼
共有財産とは?対象なるもの判断の仕方まとめ
親権・養育費・面会交流の取り決めは公正証書で
相手と親権・養育費・面会交流について取り決め、お互い合意した際には内容を公証役場にて公正証書で残しておき、「強制執行認諾文言」を入れることをおすすめします。
強制執行認諾文言とは、養育費の支払い義務を負う人の支払いが滞ったときに強制執行を受けることを認諾する旨の文です。
この文言を入れることで、調停や審判などをしなくても強制執行の手続きが可能となります。
上で述べた通り、調査結果では金銭面で苦しくなった家庭が多いことから子どものためにも養育費を取り決めいざというときに備え公正証書を作成し強制執行認諾文言を入れましょう。
まとめ
離婚が子どもに与える影響は、世帯によって異なりますが金銭的には苦しくなった家庭が多い傾向にあります。
離婚時の取り決めでは、離婚後のことを考え財産分与や養育費の交渉を進めていきましょう。
「相手に言いくるめられてしまう」「法律面のアドバイスが欲しい」という方は、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。離婚問題に強い弁護士に交渉を依頼することで、有利な条件で離婚できる可能性があります。