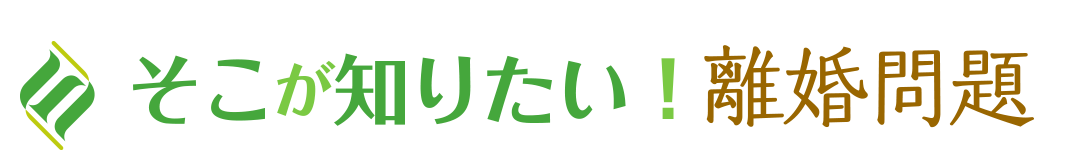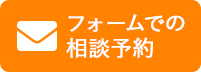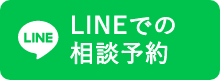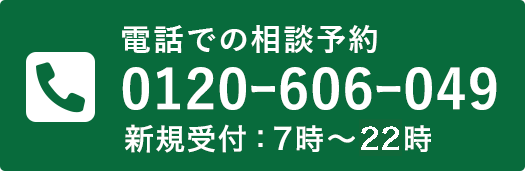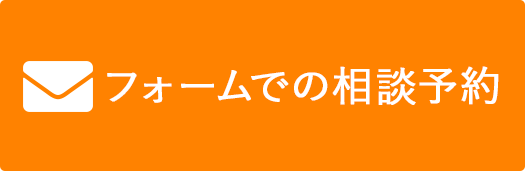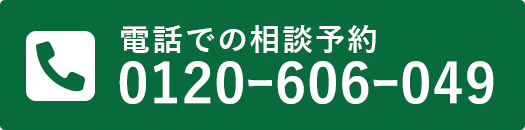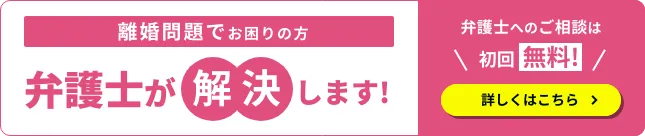

- 婚姻費用と養育費の違いとは?
- 婚姻費用や養育費を請求できる期間は?
- 婚姻費用や養育費を決定する方法とは?
【Cross Talk 】婚姻費用と養育費の違いは何でしょうか?
婚姻費用と養育費は何が違うのでしょうか?
婚姻費用は夫婦生活に必要となる費用で、養育費は子どもの養育にかかる費用です。
婚姻費用と養育費の違いについて、詳しく教えてください。
別居した場合には、夫婦の一方は他方に対して、婚姻費用を請求することができます。また、夫婦が離婚をした場合には、一方は他方に対して養育費を請求することができます。それでは、婚姻費用と養育費の違いはどこにあるのでしょうか。この記事では、婚姻費用と養育費の違いや、婚姻費用や養育費の請求期間や決定方法などについて、弁護士が解説していきます。
婚姻費用と養育費の違いとは?

- 婚姻費用と養育費の内訳とは?
- 婚姻費用と養育費の違いとは?
婚姻費用と養育費の違いはなんでしょうか?
いいい
両者の違いを理解するために、婚姻費用と養育費の概要や内訳について解説していきます。
婚姻費用の概要とその内訳
婚姻費用とは、夫婦が日常生活を送るうえで必要となる経済的な支出を指します。
法律上、夫婦はそれぞれの収入や資産に応じて婚姻費用を負担する義務を負っており、たとえ別居中であっても、戸籍上夫婦である限りこの義務は免れません。
そのため、夫婦のうち収入が低い側は、収入の高い側に対して婚姻費用の支払いを求める権利があります。
夫婦には、同居しているか別居しているかにかかわらず、相手および未成熟子(経済的に独立していない子ども)に対して、自分と同じ生活水準を維持させる義務があります。この義務は「生活保持義務」と呼ばれ、婚姻費用の分担もその一環とされています。
たとえ借金を抱えている場合でも、生活保持義務に基づき、被扶養者が同等の生活を送れるよう経済的支援を行う必要があります。そのため、収入が多い側にとってもこの義務は大きな負担となることがあります。
具体的な婚姻費用の内訳には、以下のような費用が含まれます。
このように、婚姻費用は夫婦や家族の生活を支える上で欠かせないものであり、夫婦間の収入差や状況に応じた適切な分担が求められます。
▼関連記事
婚姻費用?その内容と支払ってもらう方法について解説
養育費の概要とその内訳
養育費とは、子どもの生活を支え、教育を受けさせるために必要な費用のことを指します。
法律上、親には子どもを監護し、教育を行う義務があると同時に、直系血族として扶養義務を負うことが定められています(民法第820条および第877条)。夫婦が離婚した場合、親権を持たない親は監護・教育義務を負わなくなりますが、直系血族としての扶養義務は引き続き存続します。
このため、親権者でない親は、日々の生活費を直接負担する代わりに、養育費を支払う形で扶養義務を果たします。
具体的な養育費の内訳には、以下のような項目が含まれます:
これらの費用は、子どもが経済的に自立するまで支払う必要があります。一般的に、養育費の支払い期間は子どもが就職して収入を得られるようになるまでとされています。
▼関連記事
養育費とは?手続き方法など弁護士が詳しく解説
婚姻費用と養育費の違い
婚姻費用は、法律上婚姻関係にある夫婦が分担すべき生活に必要となる経費のことです。
これに対して、養育費は、離婚後に父母の間で分担すべき未成熟の子どもに必要となる経費のことです。
そのため、婚姻費用は、「夫婦の一方の生活費+子どもを養育するための費用」であるのに対して、養育費は「子どもを養育するための費用」だけです。
したがって、一般的に婚姻費用の方が養育費よりも相手方から受け取る金額は大きくなる傾向があります。
婚姻費用・養育費の請求について

- 婚姻費用や養育費を請求できる期間とは?
- 婚姻費用や養育費の決定方法とは?
婚姻費用や養育費はどのように決められ、どれくらいの期間受け取れるのでしょうか?
ここでは、婚姻費用や養育費の請求期間と決定方法について解説していきます。
婚姻費用を請求できる期間
婚姻費用は、夫婦が法律上の婚姻関係を維持している間、収入や資産に応じて分担する義務が生じます。その支払い期間は、以下のいずれかに該当するまでとされています。
まず、婚姻費用は、別居から離婚が成立するまで請求することができます。
たとえ夫婦関係が破綻していたとしても、法律上の婚姻関係が続く限り支払いが求められます。離婚届を提出し、正式に婚姻関係を解消することで、この義務は終了します。
また、別居中の夫婦が再び同居し、家計を一緒にする状態に戻った場合も、婚姻費用の支払い義務はなくなります。そのため、別居した夫婦が再び同居するまでの婚姻費用を請求することができます。
また、婚姻費用の支払い義務は、「請求された時点」から発生するのが一般的です。
そのため、別居開始から時間が経過している場合には、過去の期間にさかのぼって未払い分を請求することは難しいとされています。ただし、離婚の条件や財産分与の話し合いの中で未払い分が考慮されるという場合はあります。
婚姻費用は、法律上の婚姻関係が継続する限り支払い義務が発生する重要な制度です。そのため、夫婦が別居を開始した場合には、速やかに支払義務者に請求することが重要となります。
養育費の請求できる期間
養育費は、子どもが経済的・社会的に自立するまでの期間、請求することが可能です。
離婚前の養育費は婚姻費用に含まれるため、離婚するまでの分を負担しなくて良いというわけではありません。
養育費の終期は、子どもが経済的・社会的に自立すると見込まれる時期が基準となります。
20歳を終期とするのが一般的でしたが、これは20歳が従来の成年年齢であり、また20歳までは親が子どもを支えるべきだとする社会的な背景があったためです。
令和4年4月1日施行の「民法の一部を改正する法律」によって成年年齢が18歳に引き下げられましたが、社会的慣習や経済的自立の観点から、引き続き20歳を終期とする場合が多いとされています。
なお、令和4年3月31日以前に「子が成年に達するまで」として養育費の支払いを合意していた場合、当時の成年年齢が20歳だったことから、成年年齢の引き下げ後も20歳まで支払う義務があると考えられます。
また、養育費の制度の趣旨に照らすと、子どもが未成熟で経済的に自立していない場合には、たとえ成年に達しても支払い義務が続くことがあります。
例えば、大学進学により自立が遅れる場合には、大学卒業まで支払う取り決めがなされることが一般的です。解釈の違いによる混乱を避けるため、養育費の合意をする際には終期を具体的に定めることが推奨されます。
例えば、「子どもが22歳に達した後の3月まで」と明記することで、進学や就職状況を考慮した柔軟な対応が可能になります。
婚姻費用・養育費の決定方法
婚姻費用や養育費の金額は、まず夫婦間の話し合いによって決められます。話し合いで双方が合意すれば、具体的な金額に制限はなく、自由に取り決めることができます。
金額について意見が分かれ、話し合いがまとまらない場合には、裁判所が公開している 「養育費・婚姻費用算定表」 を活用する方法があります。この算定表は、夫婦の収入や生活状況に基づいて、適正な金額の目安を示したものです。算定表は、調停や審判の場でも参考にされるため、相場として信頼性が高いものです。
夫婦間での話し合いがどうしてもまとまらない場合は、調停や審判といった法的手続きに進むことを検討します。その際、算定表は金額を決定する重要な資料となり、公平性を確保するために用いられます。
このように、婚姻費用や養育費の金額は夫婦間の合意が最優先ですが、算定表を利用することで、適正な基準をもとに話し合いを進めることが可能です。特に金額でもめる場合には、算定表を活用することで合理的な解決が期待できます。
まとめ
婚姻費用とは、夫婦が日常生活を送るうえで必要となる経済的な支出を指します。
これに対して、養育費とは、子どもの生活を支え、教育を受けさせるために必要な費用のことを指します。
婚姻費用には、子どもの養育に必要となる費用のほかに、夫婦の一方の生活費も含まれているため、養育費よりも高額になる傾向があります。
そして、婚姻費用や養育費については、夫婦の話し合いで取り決めることができますが、話し合いがまとまらない場合には、調停や訴訟などの裁判手続きを利用する必要があります。
婚姻費用や養育費についてお悩みの場合には、夫婦トラブルや離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。当事務所には、離婚問題の解決実績の豊富な弁護士が在籍しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。