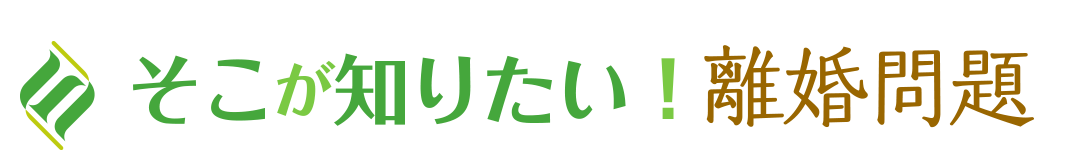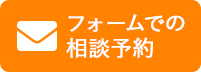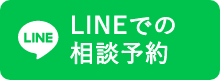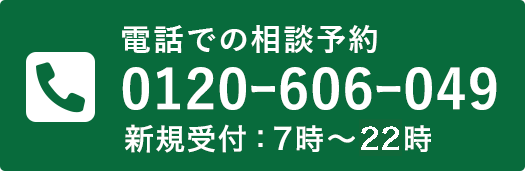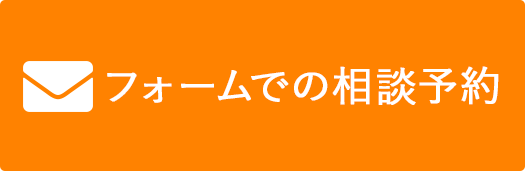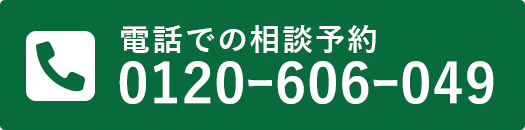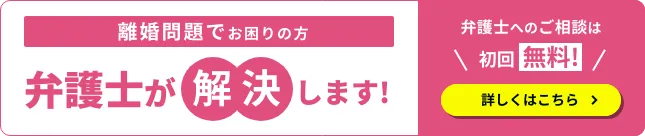

- 共有財産は財産分与の対象となる
- 共有財産となる具体的な財産とは?
- 共有財産とならない財産とは?
【Cross Talk 】共有財産とはどのような財産ですか?
離婚をする場合、財産はどうやって分ければいいのでしょうか。
共有財産については、財産分与によって公平に分け合うことになります。
共有財産について詳しく教えてください。
夫婦が離婚する場合、財産はどうなるのでしょうか。
夫婦の共有財産は、財産分与によって離婚時に公平に分け合う必要があります。
それでは、どのような財産が共有財産になるのでしょうか。共有財産とならない財産はどのような財産なのでしょうか。この記事では、共有財産の意義やその具体例、特有財産について解説していきます。
共有財産とは

- 共有財産の定義とは?
- 共有財産は財産分与の対象となる
共有財産とはどのようなものなのでしょうか。
共有財産と財産分与についてお伝えします。
夫婦が結婚期間中に協力して形成・維持した財産のことを「共有財産」といいます。
形式的には夫婦の一方の名義になっている財産であっても、夫婦の協力によって得られたものと評価される場合には、夫婦の共有財産となります。
例えば、夫婦の一方が専業主婦(主夫)であり、もう一方の収入によって購入された資産であったとしても、夫婦両方が権利を有しています。専業主婦の方は会社に勤めて給料を稼いでいませんが、家事労働に貢献したことによって、他方の配偶者が会社勤めに集中して給料を稼ぐことができた、と考えられます。そのため、夫婦の一方の給料で購入されたものであっても、夫婦の共有財産と言えるのです。
そして、共有財産については、夫婦が離婚する際に公平に分け合うように請求することができます(民法第768条1項)。これを財産分与請求権といいます。
離婚の際の財産分与の分与割合は、原則として2分の1ずつです。夫婦の一方が専業主婦の場合であっても、半分ずつ分けるというのが原則です。
共有財産の対象

- 共有財産の対象となる具体的な財産とは?
共有財産となるのはどのような財産なのでしょうか。
ここでは、共有財産になるものを具体的にお伝えしましょう。
預貯金・現金
預貯金や現金は財産分与の対象となります。
夫婦が婚姻期間中に協力して貯えた預貯金や現金については、共有財産となるため、財産分与の対象となります。
夫が会社で働いて稼いだお金や、夫の名義の通帳で預金していた預貯金についても、基本的には夫婦で公平に分け合うことになります。
預貯金・現金が財産分与の対象となる基準時は原則として夫婦の別居時点です。別居後に夫が散財して預貯金の金額が無くなったとしても、基本的には別居時に存在していた金額を基準に財産分与を判断することになります。
不動産
婚姻期間中に購入したマンションや一戸建てなどの不動産についても、夫婦の共有財産です。
不動産の名義が夫婦のどちらであっても、婚姻期間中に購入されたものについては財産分与の対象となります。
不動産を離婚時に分け合う方法としては、不動産を売却したうえで現金化したものを公平に分け合うという方法や、夫婦の一方がマンションや戸建てに住み続けるという方法が考えられます。
ただし、住宅ローンの返済が残っている場合には、複雑な問題が生じるおそれもあります。不動産の評価額よりも住宅ローン残債務が低い場合(アンダーローンの場合)には、不動産を売却したお金によって住宅ローンを完済し、売却にかかった経費を差し引いたうえで、残った利益を夫婦で公平に分けることになります。
これに対して、不動産の評価額よりも住宅ローンの残債務が大きい場合(オーバーローンの場合)には、不動産の売却によって得られたお金をすべて住宅ローンの返済に回しても完済することができません。残った住宅ローンについては、夫婦の資産から支払う必要が出てきます。オーバーローンの場合には、住宅ローンを完済できるほどの資金的な余裕が必要となります。
生命保険の解約返戻金
結婚期間中に夫婦や子どもの将来に備えて加入していた生命保険や学資保険については、解約時に解約返戻金が発生する場合があります。加入していた保険の解約返戻金については、共有財産として財産分与の対象となります。学資保険や生命保険について婚姻期間中に支払ってきた保険料は夫婦の共有財産であると考えられているからです。
年金
年金についても年金分割という制度によって分けることができます。
厚生年金・共済年金については、婚姻期間中の年金保険料の納付実績を分割することで、他方配偶者が年金を受け取れるようにすることができます。ただし、婚姻期間中に配偶者が国民年金に加入していた場合には、年金分割の制度で受け取ることはできません。
退職金
夫婦の一方が会社から支給される退職金についても夫婦の共有財産として、財産分与の対象となり得ます。
退職金は、賃金の後払い的な性質のある金銭であることから、夫婦が協力して得た財産であると考えられています。共有財産となる退職金は、婚姻期間中に形成された部分のみです。
ただし、退職までに時間がある場合には、退職金が確実に支払われるとは限りません。そのため、退職金が財産分与の対象となるのは、退職金の支給がほぼ確実であるという場合に限られます。
自動車
婚姻期間中に購入した自動車についても夫婦の共有財産として、財産分与の対象となります。
自動車の分け方については、売却益を分割するほかに、引き続き自動車を使用する方が金銭を支払って調整するという方法もあります。
共有財産の対象とならない財産

- 共有財産の対象とならない財産とは?
- 特有財産は財産分与の対象とはならない
共有財産の対象とならない財産はどのようなものでしょうか。
ここでは特有財産について解説していきます。
前述の通り、財産分与の対象となるのは夫婦の共有財産です。夫婦の共有財産ではない場合には、財産分与の対象とはなりません。
特有財産については、財産分与の対象とはなりません。
特有財産とは、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名義で得た財産」のことをいいます(民法第762条1項)。
したがって、特有財産とは以下のいずれかの財産です。
したがって、結婚する前に取得した、現金・預貯金や不動産、自動車などは特有財産となります。また、自分が相続人として承継した相続財産や、自分が受遺者として譲り受けた贈与財産、別居後に形成された財産も、特有財産となります。
判別が難しい場合には共有財産とされる

- 共有財産には推定規定がある
夫婦の共有財産かどうかわかりにくいものはどうなりますか?
夫婦の共有財産には推定規定があります。
民法は、「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する」と規定しています(民法第762条1項)。よって、共有財産であるか否かの判別が難しい場合には、共有財産であると推定され、財産分与の対象となります。
なお、推定であるため、推定を破る事情を主張・立証できる場合には特有財産として財産分与の対象から外すことも可能です。
まとめ
以上この記事は、共有財産の種類や、共有財産とはならないものなどについて解説してきました。
離婚する場合、夫婦の共有財産は財産分与の対象となりますので、公平に分け合う必要があります。財産分与や離婚についてお悩みの場合には、離婚事件に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。