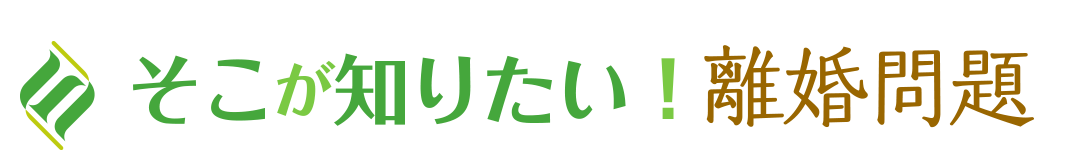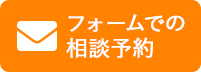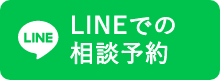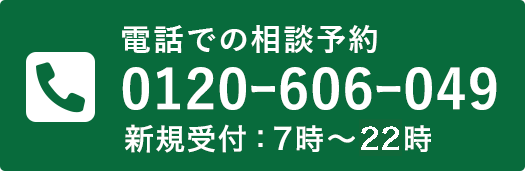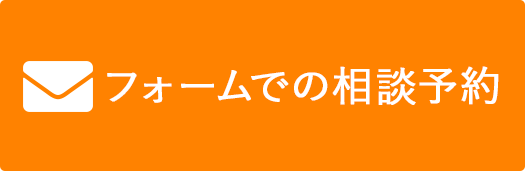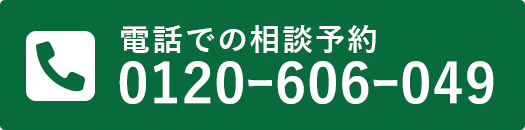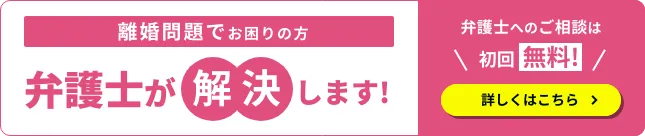

- 面会交流の決め方とは?
- 面会交流の頻度はどのくらい?
- 面会交流の頻度が多い場合の対処法とは?
【Cross Talk 】面会交流の頻度が多い場合には減らすことができるか?
離婚した相手が望む面会交流の頻度が多すぎて困っています。
面会交流の頻度が多い場合には減らせる場合があります。
面会交流の頻度を減らすための方法について教えてください。
面会交流とは、離婚した親のみならず、その親と離れて暮らす子どもの権利でもあります。しかし、離婚後の面会交流の頻度が多すぎる場合には、監護親の負担が大きくなってしますおそれもあります。
そこで、面会交流の頻度が多すぎる場合には、事後的に面会交流の実施回数を変更する必要があります。
このコラムでは、面会交流の取り決め方法や頻度が多い場合の対処法などについて解説していきます。
面会交流とは?

- 面会交流とは?
- 面会交流の意味は?
面会交流とはどのようなものなのでしょうか。
ここでは、面会交流の定義や意義について解説していきます。
「面会交流」とは、子どもと別居して暮らしている父または母が子どもと定期的・継続的に会って話をしたり遊んだり電話や手紙・メールなどで交流することを指します。
民法には、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める」と規定されています(民法第766条1項)。そのため、面会交流に関する取り決めは、親権者の指定や養育費などと同じように父母が離婚する場合に話し合って合意しておく必要があります。
夫婦が離れて暮らすことになっても、子どもがどちらの親からも愛されていることを実感し、それぞれと温かく、信頼できる親子関係を築いていくことは子どもの成長にとってとても重要なことです。
面会交流が円滑に行われることによって、子どもはどちらの親からも愛され、大切にされていることを実感し、安心感や自信を得ることができると考えられています。
▼関連記事
面会交流調停の流れとは?有利に進めるための方法も
面会交流の頻度

- 面会交流の決定方法は?
- 面会交流の実施の頻度とは?
面会交流はどのように決められ、どれくらいの頻度で実施されているのでしょうか。
ここでは、面会交流の決定方法や実施頻度について統計資料を交えてご紹介します。
面会交流の頻度等の取り決め方法
面会交流の具体的な実施方法などについては、父母が自由に話し合いによって決定することができます。
面会交流を実施するのか否か、行う場合その実施方法はどのように行うのか(実際に面会するのか、テレビ電話やLINE通話、電子メールなどで行うのか)、実施の回数はどの程度か、実施日時や場所はどうするのかなどの詳細なルールについては、父母が協議によって決定する必要があります。
もし、父母の協議で面会交流について決定することができない場合には、裁判所に決めてもらうことができます。父母は面会交流調停を申立てることができます。
面会交流調停では、子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるため、子どもの年齢・性別・性格・就学の有無・生活のリズム・生活環境などを考慮し、子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して話合いが進められます。また、面会交流の取決めに際しては、面会等を行う際に父母が注意する必要のある事項について裁判所側から助言します。なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、一切の事情を考慮して審判をすることになります。
なお、裁判所が公表する「令和4年司法統計年報・3家事編・第24表」によると、調停や審判で決定した面会交流の回数は以下の通りです。
| 総数 | 9895件 |
| 週1回以上 | 217件 |
| 月2回以上 | 767件 |
| 月1回以上 | 4090件 |
| 2~3カ月に1回以上 | 514件 |
| 4~6カ月に1回以上 | 177件 |
| 長期休暇中 | 27件 |
| 別途協議 | 2926件 |
| その他 | 1177件 |
以上の通り、面会交流の実施頻度については、「月1回以上」が4割以上を占めており最も多くなっています。
面会交流の頻度が多い場合の対処法

- 面会交流の頻度が多い場合の対処法とは?
- ADRや調停・審判手続きを利用する
面会交流の回数が多すぎる場合に頻度を減らすにはどうすればいいのでしょうか。
ここでは、面会交流の変更をする場合の対処法について解説していきます。
元配偶者と話し合いを行う
既に取り決められている面会交流の内容について、一方的にルール変更をすることはできません。
そのため、面会交流の回数が多すぎる場合には、頻度を減らすために元配偶者と話し合う必要があります。
面会交流の頻度が多すぎるからといって、親権者だけの判断で面会交流を取りやめたり回数を減らしたりすると、非監護親との間でトラブルに発展するリスクがあります。
父母のみでは冷静な話し合いを行うことが難しいという場合には、弁護士に依頼して間に入ってもらうようにしてください。弁護士に相談することで面会交流の条件について適切に見直し、法的に有効な書面を取り交わしておくことで、今後もスムーズに面会交流を実施できるようになります。
ADR手続きを利用する
当事者同士の話し合いでは決められないという場合には、ADR(裁判外紛争処理手続き)を活用することができます。
ADR手続きは、NPO法人などが行っており、弁護士や親子交流の支援者が父母の間に入って、面会交流の条件について合意することを支援しています。
ADR手続きの場合には、オンラインで話し合いを行うことができたり、土曜祝日・夜間であっても対応してもらえたりする場合があります。
ADR手続きのように、第三者が関与して話し合いを行うことで、当事者双方が冷静に対応できる可能性が高まります。
面会交流調停・審判を申立てる
当事者同士の話し合いやADR手続きを利用できない場合には、家庭裁判所に面会交流調停・審判を申立てる必要があります。
調停手続は裁判官・調停委員を介して父母の協議で紛争の解決を目指すことになる手続きですので話し合いがまとまらなければ調停は「不調」です。その場合には裁判官によって審判が下されます。
面会交流について調査官は必要な調査ができます。
相手が要求している面会交流が多すぎる場合は調査官調査を要請することが効果的なこともあります。調査を依頼したとしても必ず調査が行われるとは限りませんが、調査官がおこなった調査の結果相手方を説得できる場合や、審判手続きに移行した場合にも重要な判断要素として考慮される可能性があります。
▼関連記事
面会交流は何歳まで?子どもや元配偶者が拒否する場合の対処法も
まとめ
以上この記事では、面会交流の意義や、その頻度が多い場合の対処法などについて解説してきました。
面会交流の回数を事後的に変更したいという場合には、弁護士に相談するようにしてください。
当事務所には、親子の法律トラブルの解決実績が豊富な弁護士が在籍しておりますので、お気軽にご相談ください。