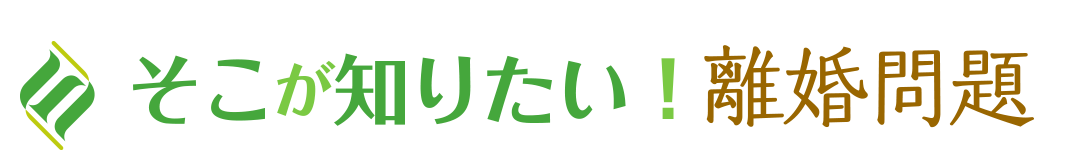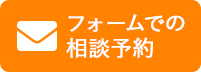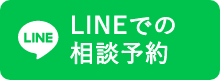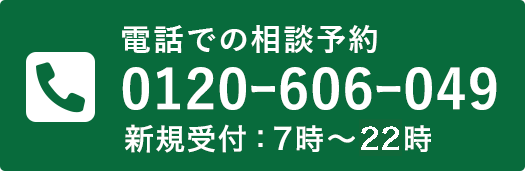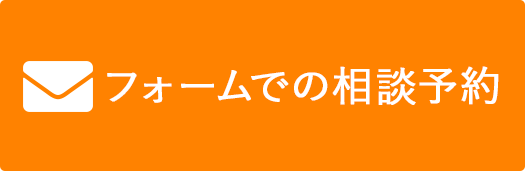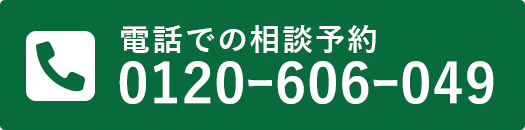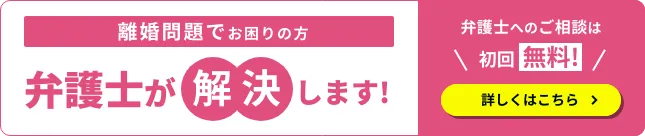

- 配偶者が意思疎通できる状態で、双方が離婚に合意していれば協議離婚ができる
- 配偶者が意思疎通できない状態であれば、成年後見人をつける
- 離婚後の配偶者の療養・生活について具体的方策を講じることが必要に
【Cross Talk 】妻がうつ病になりました。看病が辛く、離婚したいです。
妻がうつ病になってしまいました。私も2年間できる限りのことはしてきましたが、昼間は仕事もあるので心身ともにしんどくなってしまい、離婚を検討しています。病気を原因とする離婚は可能ですか?
双方が合意していれば、協議離婚はできます。奥さまが身内と同居できるもしくは1人でも生活できる状態であれば、まず別居をするという方法もあります。
詳しく教えてください!
夫または妻が病気になり、それが理由で離婚することは可能なのでしょうか?
今回は、夫・妻の病気が原因で離婚できる場合とできない場合、難病や精神疾患などの状況別の対処法を解説していきます。
夫・妻の「病気」が原因の離婚、できる場合とできない場合

- 双方が合意できれば協議離婚は可能、意思疎通が取れるかどうかがポイント
- 長期間の別居、配偶者がDV・モラハラをする場合などは離婚が認められること
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないときには離婚できると聞いたのですが・・・。
確かに、民法第770条には離婚訴訟を提起できる事由として定められていますが、精神疾患を法定離婚原因とする民法770条1項4号は削除されました。また、過去の判例では病気になった配偶者が離婚後に生活できるような目途がたたなければ離婚は不相当とされています。
協議離婚はできる
配偶者が病気になり、離婚が原因で「離婚したい」という場合は合意ができれば協議離婚は可能です。
ただし協議離婚は、夫婦が合意のうえで離婚届を出すものですので配偶者が意思疎通できている状態でなければいけません。
まずは「配偶者と意思疎通がとれるか」がポイントになります。
協議離婚が不可能でも、民法では離婚訴訟を提起できる5つの「法定離婚事由」があります。ただし、上記のとおり、4号の法定離婚原因は早ければ2025年には削除されることになります。
法定離婚事由について
民法※1第770条では、以下5つの「法定離婚事由」を定めています。
- 第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 1 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- 5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2の「悪意で遺棄された」とは、配偶者が困ることを分かっていながら家にお金を入れない、正当な理由がなく家を追い出すなど夫婦の「同居・協力・扶助」の義務を怠ることです。
4の「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」について、過去の最高裁判所判例 では「民法770条の規定は、夫婦の一方が不治の精神病にかかった事実が肯認される場合においても、離婚請求の許否を決するに当たっては、なお諸般の事情を考慮し、各関係者間において病者の離婚後における療養、生活などについてできるかぎりの具体的方策が講ぜられ、ある程度において、前途に、その方途の見込がついたうえでなければ、婚姻関係を解消させることは不相当と認め、離婚の請求は許さない趣旨のものであると解すべき」とされています。
たとえ配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがなくても、配偶者が離婚後に療養や生活に困らないような策を講じ(具体的方途)、ある程度生活の目処がつく(ある程度において、前途に、その方途の見込がついたうえでなければ)ことが求められます。
5の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、長期間の別居、暴力や虐待・モラハラ、過度な宗教活動などが該当します。
配偶者がDV・モラハラをする、長期間の別居などは離婚が認められることも
上で述べた通り、「配偶者が病気になった」というだけでは離婚訴訟を提起しても認められる可能性は低いでしょう。
しかし、以下のような行為があれば「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚できる可能性があります。
- 長期間に渡り別居している
- 配偶者がDV・モラハラをする
- 過度な宗教活動にのめり込む
- 犯罪行為に伴う服役
- アルコール依存・薬物依存
- 借金・ギャンブル・浪費など
例えば病気をきっかけに、過度な宗教活動にのめり込み夫婦生活が破綻した場合などが想定されます。
過去の判例 では、「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」としては認められなかったものの、離婚訴訟を起こした夫が出生時から子どもを養育している、病気の妻の治療費などを捻出した、妻は自営業の夫が営む店の仕事に無関心で協力しなかったといった理由から「婚姻の継続を相当と認める場合にはあたらないものというべき」という判決が出たことがあります。
精神4疾患、難病・・・状況別の対処法と離婚について

- 配偶者が精神疾患にかかった場合、「意思疎通ができるか」という点がポイントに
- 病気になった配偶者と意思疎通ができない場合は、成年後見人を選任する
配偶者が重度の認知症で、離婚の話ができません。
自身で判断ができない状態なのですね。成年後見人をつけ、離婚するという方法があります。
配偶者が精神疾患にかかった
配偶者が精神疾患にかかった場合、まず「意思疎通ができるか」という点がポイントです。
意思疎通が可能で双方が合意している際には協議離婚が可能です。
財産分与、子どもがいるときには親権・養育費・面会交流などについて話し合います。
配偶者が精神疾患になった原因が自身にある場合、慰謝料を請求される可能性があります。
例えば自身の不貞行為やDVなどが原因で配偶者が精神疾患にかかった事例などが該当します。
一方で、配偶者が意思疎通できない場合には成年後見人をつけることになります。
配偶者が難病になった
配偶者が難病であっても、上記の判例のように「病気になった」というだけで離婚を認められる可能性は低いでしょう。
離婚案件では、様々な事情を考慮して婚姻生活を継続できるか否かを判断します。
病気になった配偶者が自分の意思を表示できない
病気になった配偶者と意思疎通ができない場合は、成年後見人の選任の申立てをします。
協議離婚は両性の合意の下で成立しますので、協議離婚は不可能となり成年後見人を選出し訴訟により離婚を請求することになるでしょう。
成年後見人とは、精神障害・認知症などにより一人で意思決定をすることが難しい方の契約や手続きなどを行う方を指します。※2
後見人を選任するためには、管轄の家庭裁判所に申し立てる必要があります。
病気になった配偶者に離婚したいと言われた
病気になった配偶者に「離婚したい」と言われたときには、双方が合意すれば離婚は可能です。
ただし、配偶者が意思疎通、判断ができない状態であれば成年後見人をつけて離婚を求めることになります。
まとめ
病気が原因での離婚は、協議離婚が可能であればスムーズに離婚できる可能性があります。
しかし配偶者が離婚を拒否している、意思疎通や判断ができない状態であれば離婚まで長期化する可能性が高いでしょう。
お困りの方は離婚問題に詳しい弁護士に相談してみましょう。今後の対処法や法律的な観点からのアドバイスを聞くことができるでしょう。