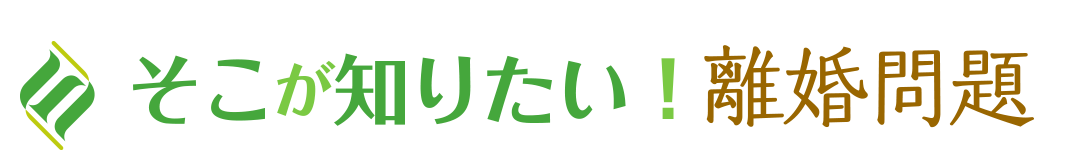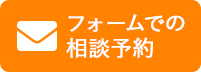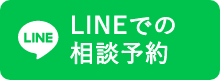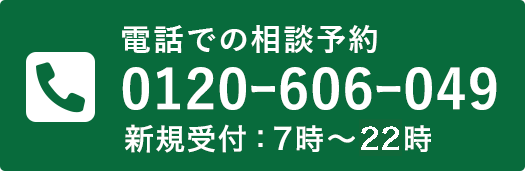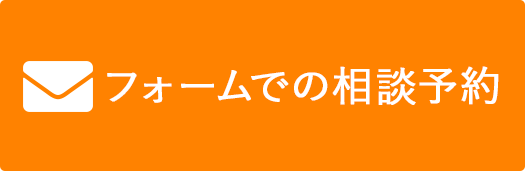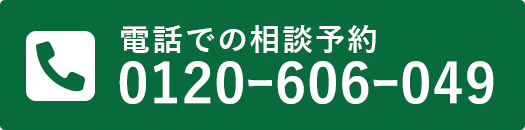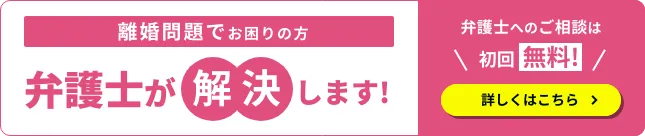

- 医者の離婚が多いと言われる理由
- 医者の離婚で注意すべき点
- 医者の離婚トラブルを弁護士に相談すべき場合
【Cross Talk 】医者の離婚トラブルは弁護士に相談する必要がある
医者が離婚する場合には、弁護士に相談した方が良いのでしょうか。
医者の方が離婚する場合には、特有の問題が発生する可能性があります。
医者の離婚トラブルについて詳しく教えてください。
医者については、いくつかの仕事の特徴から離婚することが多いと言われることがあります。
医者の方が離婚する場合には、特に紛争に発展しやすい問題があるため、注意しておく必要があります。
医者の方が通常業務をこなしながら、離婚の問題に対応するためには、弁護士に相談することも検討されてください。
医者は離婚が多いと言われる理由

- 医者の離婚が多いと言われている理由とは?
なぜ、医者は離婚が多いと言われているのでしょうか。
医師の離婚が多いと言われている理由について解説します。
仕事の拘束時間が長い
医師の仕事は、一般的に仕事の拘束時間が長いため、家庭に割くための時間が相対的に短くなってしまう傾向があります。医者は、人の生命・身体の安全に関わる仕事をしており、特に勤務医の場合には、組織の中で重要な役割分担を担うことになります。運び込まれた急患への対応や、不規則なシフト勤務に加え、長時間労働が当たり前という風土もあります。
そのため、家庭に戻った際には、精神的にも肉体的にも消耗し、自身の家庭に目を向ける余裕がなくなっている方も少なくないでしょう。
このように医者の仕事は、拘束される時間が長く、激務によるストレスも大きいため、離婚の原因になる場合があると言われています。
職場での不貞トラブル
医師は、看護師などの同僚の病院スタッフや、患者、その他医師仲間からの紹介で出会う方など様々な方に接触する機会が多い職業です。特に、病院は夜間の勤務シフトや宿直、また学会への参加のため遠方へ宿泊を伴う出張をする機会があります。
自宅以外に寝泊まりする機会が増えると、家族に知られることがなく、不倫をすることが容易になるため、離婚に繋がるリスクが高くなると言えるでしょう。
また、医師は、社会的地位や経済的地位が高いと広く認知されているため、魅力的に見えるということも理由のひとつであると言えます。さらに、仕事と関係なく不倫を続けていても、「この日は夜勤・出張だから」と簡単にごまかすことができることも、不倫を助長する一因になっていると考えらえます。
年収が高い
医師という仕事は激務である一方で、一般的に、年収が高い職業であるとわれています。
そのため、同年代の方と比べて収入が高いため、医師であれば離婚してもすぐに再婚できる可能性が高いのです。
また、年収が相対的に高いことは女性医師であっても同様です。一般的に世の中の女性が「離婚したいけどできない」と考えている理由に、経済的な事情が挙げられます。夫の収入があるおかげでなんとか生活できているという女性も少なくありません。
しかし、女性医師の場合にはご自身の収入も高いため、離婚へのハードルが非常に低くなります。
このように、医師の収入が高いということも、医師の離婚が多い理由のひとつであると考えられています。
医者が離婚する際に注意すべきこと

- 医者が離婚する場合の注意すべきこととは?
- 財産分与や養育費について紛争になるおそれがある。
医者が離婚する際に気を付けるポイントはありますか。
ここでは、医者が離婚する際に注意すべきことを解説します。
財産分与の問題
医者が離婚する際には、財産分与が問題となる可能性があります。
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成・維持した共有財産を、離婚する際に公平に分け合おうという制度です。このような制度の目的から、財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦が協力して形成・維持した共有財産です。
医者は一般的に収入が高いため、同世代の離婚事件と比べて、財産分与の対象となる共有財産が多くなる傾向があります。有価証券や高級車、不動産などが財産分与の対象となっていると、その分与方法や評価方法を巡って夫婦間で意見が対立してしまう可能性があります。
また、開業医の場合には、個人事業主となるため、病院・診療所に関する資産についても、夫婦の共有財産とみなされる可能性があります。離婚によって身ぐるみをはがされ、今後の病院経営が難しくなってしまうという結果だけは避けなければなりません。
財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産(共有財産)のみです。婚姻前から保有している財産や第三者から無償で取得した財産など、夫婦が協力して形成したものでない財産(特有財産)については、対象外となるため、その違いは正確に把握しておく必要があります。そして、原則として財産分与の割合は、「2分の1」となります。
なお、医療法人の名義となっている動産・不動産については、財産分与の対象とはなりませんが、配偶者が医療法人の出資者となっている場合など例外的な場合には、財産分与の対象となる可能性があるため、不安な方は弁護士に相談するようにしましょう。
関連記事
財産分与の「2分の1」原則の例外が認められる場合とは?
親権・養育費の問題
医者が離婚する場合には、親権者の指定や養育費の算定についてももめる可能性があります。特に収入の高い医者の場合には、一般的な養育費の相場よりも高額になるおそれがあります。
養育費は、離婚して子どもと離れて暮らす方の親が、子どもを監護する親(親権者)に対して月々支払うことになる、子どもの生活費・教育費・医療費などの費用のことを指します。一般的な養育費の算定方法は、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」をベースに子どもの年齢・数、夫婦の年収などを参考に決定されることになります。そのため、高収入の医者の方の場合には、養育費算定表の年収額の範囲を超えてしまうことがあるのです。
養育費の金額については、夫婦が話し合いによって合意することができます。親権者の決定や養育費の金額で紛争になった場合には、弁護士に相談するようにしましょう。
医者の離婚トラブルを弁護士に相談すべき場合

- 医者の離婚で弁護士に相談すべき場合とは?
医者の離婚トラブルを弁護士に相談すべきなのはどのような場合なのでしょうか。
ここでは、離婚トラブルを弁護士に相談した方が良い場合について解説してきます。
激務で時間がない場合
一般的に医師に仕事は激務で時間的な余裕が全然とれないという方も少なくありません。
そのような時間のない中で適切に離婚の話し合いを進めていくことは非常に難しいでしょう。
そこで、医師として通常業務を行いながら、離婚条件も適切に取り決めていくためには、弁護士に対応を依頼することがおすすめです。弁護士が財産の算定から相手との交渉、調停・訴訟についても対応してくれるため、スムーズに手続きを進められる可能性が高まります。
資産・収入が高額の場合
資産や収入が高額な場合には、財産分与・養育費・婚姻費用分担などでトラブルに発展するおそれがあります。また、夫婦双方が医者の場合には、お互いに高額の資産や収入を保有していることが多く、どのように夫婦共有財産を分けるべきか、どのように財産を算定すべきかなども問題となります。
早い段階で弁護士を入れて資産の洗い出しや分与方法についてアドバイス・サポートを受けることで、双方の意向を踏まえた適切な内容で合意できる可能性が高まります。
有責配偶者の場合
専ら婚姻関係を破綻させた原因を作出した当事者のことを、有責配偶者といいます。例えば、不貞行為やDV・モラハラなど婚姻関係を継続できない原因を作った相手に対して、他方の配偶者は裁判上の離婚を請求することができます。他方で、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。
有責配偶者に対しては、婚姻を破綻させたとして不法行為に基づく慰謝料請求をすることもできます。
もし、離婚の原因について有責性がある場合には、一般的に不利な状況に置かれるリスクが大きいため、弁護士に相談して適切な解決を目指すことが重要です。
親権を争う場合
医者の離婚の場合、熾烈な親権トラブルに発展する可能性もあります。
例えば、代々医者の家系で、子どもも医者として病院の跡取りとしたいと考えていた場合には、親権を巡って紛争となるおそれがあります。
親権者の指定では、子の福祉にかなうのはどちらかという観点から、様々な考慮要素を基に裁判所が父母のいずれかが親権者にふさわしいのか判断します。親権獲得のためにどのような主張をすべきかの判断は非常に専門的知見が必要であるため、親権を獲得したいという場合には、必ず弁護士に相談するようにしましょう。
関連記事
離婚の親権争い、母親と父親どっちが有利?親権を取るためには
まとめ
以上この記事では、医者の離婚が多いと言われている理由や、注意すべきポイント、医者の離婚を弁護士に任せるべき理由などについて解説してきました。
医者の離婚については、資産が多いことから、お金に関する問題を大きな争点となるおそれがあります。医者として通常業務を行いながら、不利な条件で離婚しないようにするためには、離婚問題に詳しい弁護士に相談することが大切です。