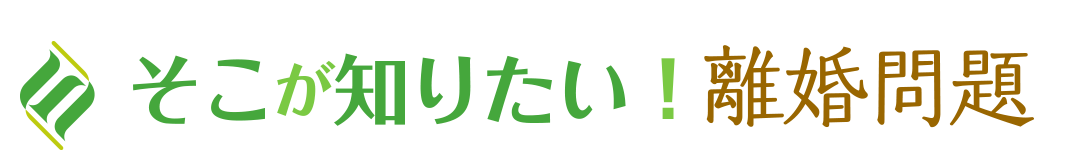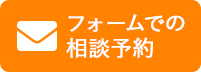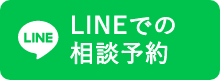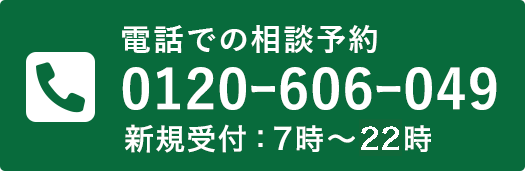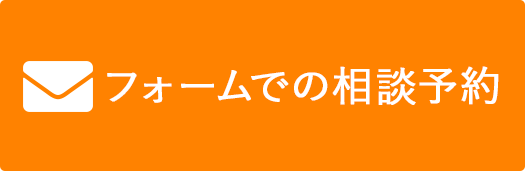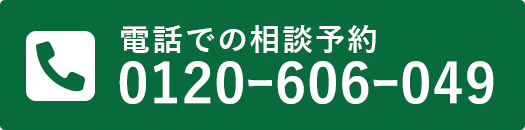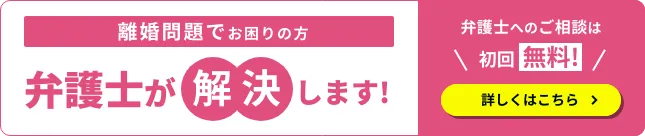

- 2人で話し合い、相手が親権を持つことを承諾すると親権を手放すことができる
- 父母どちらも親権取得を希望しない場合は「子の監護者の指定調停」を申立てる
- 親権を譲ることでデメリットも生じるため、慎重に検討を
【Cross Talk 】離婚で親権を譲りたい場合に手放すことはできる?
離婚をする予定ですが、親権は譲りたいと考えています。可能でしょうか?
配偶者が承諾しているときには可能です。ただし、配偶者も親権の取得を希望しない場合には子の監護者の指定調停を申立てることになります。
詳しく教えてください。
離婚時に親権を譲りたい場合、配偶者が親権を持つ意思があれば手放すことが可能
です。
ただし、2人とも親権の取得を希望しないときには、子の監護者の指定調停を申立てることになります。
重病などやむを得ない事情がある場合は、親権の辞任もできます。
しかし一度親権を手放すと、気持ちが変わり子どもと一緒に暮らしたいと希望しても親権を変更することが難しくなってしまう事例があります。
本記事では、親権を手放す方法や手放す前に知っておきたい3つのことを解説していきます。
「親権を持ちたくないから離婚したい」は可能なのか

- 配偶者が親権を持つ意思がある場合には親権を手放せる
- 2人とも親権の取得を希望しない場合は「子の監護者の指定調停」へ
そもそも親権とはどのような権利なのでしょうか?
親権は子どもの利益や福祉のための権利であり、親の義務でもあります。
どちらかが親権を持つことになる
「親権を持ちたくないから離婚したい」は可能なのでしょうか?
親権は子どもの利益・福祉のために行使することとされています。子どものための権利であり、親の義務ともいわれています。※1
子どもの世話や教育をする「身上監護権」(監護権)と子どもの財産を管理する「財産管理権」(親権)という2つの権利があります。監護権と親権を父母のどちらかが担当することもできますが、トラブル回避の観点からは避けた方が良いでしょう。
未成年者の子どもがいる場合にはどちらが親権を持つか、親同士で決める必要があります。
養育費や面会交流についても取り決めておきましょう。
「子どもの親権を譲りたい」という方は、まずは配偶者と話し合うことが重要です。
一般的に、離婚後の親権は母親が持つ事例が多いです。2021年の司法統計年報家事編※2によると、子どもの親権者を定めた婚姻関係事件の総数は19,915件で、そのうち18,678件(約93.8%)は母親が親権を持つ結果となっています。特に乳幼児は母親が親権を獲得する確率が高いといわれています。
お互い親権の取得を希望しない場合は「子の監護者の指定調停」へ
夫婦で話し合い、お互い親権の取得を希望しない結論になった場合はどうすれば良いのでしょうか?
家事事件(離婚・相続など家庭内のトラブル)については、基本的に訴訟の前に調停で話し合う「調停前置主義」となっています。
家庭裁判所に「子の監護者の指定調停」を申立て、調停委員・調査官に話をする、資料を提出するなどの方法で解決に向けて話し合います。
なお親権の他に離婚についても意見が合わない場合には、親権を含めた離婚調停を申立てることが可能です。
調停では、父母のどちらが子どもの監護者に適しているか調査が行われることがあります。
調査では両親のこれまでの養育状況や経済力・家庭環境、子どもの性格・通っている保育園・学校などの様子・生活環境などを聴かれることが多いです。
調査官が裁判官に調査報告書を提出し、裁判官が様々な事情を考慮して親権者を審判で指定します。
審判に不服の申立てをせずに2週間が過ぎた場合、高等裁判所で不服申立てが認められなかった場合に審判が確定します。※3
審判に対して不服の申立てがあった際には、高等裁判所で審理を行います。
やむを得ない事情がある場合は親権の辞任ができる
民法837条※4では「やむを得ない事由」がある場合に親権の辞任が認められています。
2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
やむを得ない事由とは重病で入院をしている、犯罪行為により服役しているなど親としての役割が果たせない状況にある事柄が該当します。
2項に記載されているように、親権を辞任した後に回復することが可能です。
また親権を譲った後に元配偶者が虐待など親権者にふさわしくない行為をした場合には、親権の停止や喪失の審判を申立てることができます。
第834条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。
第834条の2 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。
子ども自身が親権の停止・喪失を申立てることもできます。
親権を手放す前に知っておきたい3つのこと

- 親権を手放すと、変更が難しくなってしまう可能性があるので慎重に検討する
- 子どもが15歳以上の場合には、子どもの意思が尊重される
親権は後で変更できますよね?
親権の変更は可能ですが、元配偶者や子どもが拒否するかもしれません。また、一度親権を手放すと、取り戻すことが難しくなってしまう可能性がありますので慎重に検討しましょう。
親権を譲ると養育費を支払う必要がある
離婚後に親権を手放した後でも、子どもの親であることに変わりはありません。
子どもの生活や教育に必要な費用は両親が負担する義務があります。一般的に離婚後に子どもと離れて暮らす親が養育費を支払う事例が多いです。
ただし、厚生労働省の「2021年度全国ひとり親世帯等調査結果報告※5」によると、父親は養育費をもらっていない世帯が多いことが分かります。
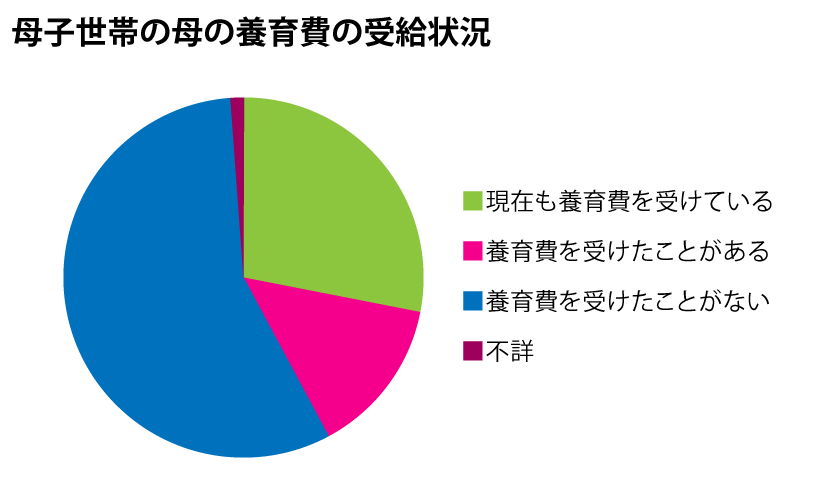
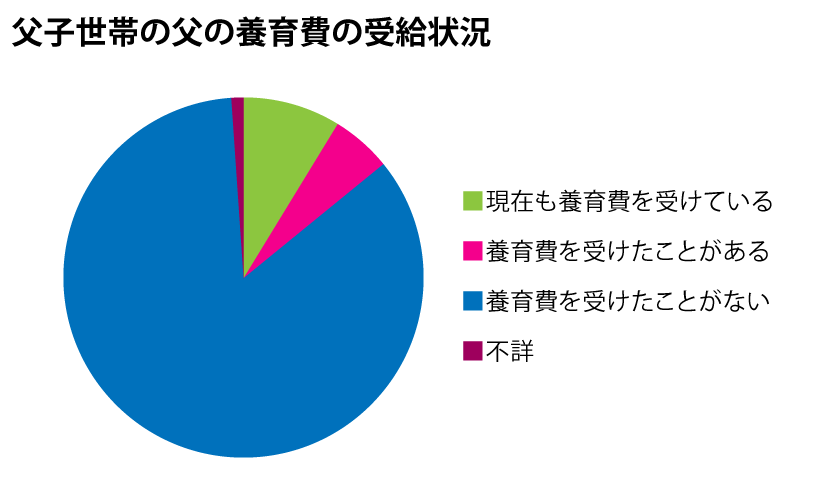
支払い義務はありますが、お互いの収入や環境によっては支払わないこともあります。
▼関連記事▼
離婚をする際の親権・養育費の決め方について解説
親権者変更の手続きで取り戻すことができるが・・・
親権を手放した後に「やはり親権が欲しい」と考えが変わった場合は、子どもや元配偶者に親権者の変更を提案します。
話し合いでまとまらないときには「親権者変更調停」を申立てることが可能
です。
ただし親権は今までの養育実績も判断材料になります。
一度親権を手放し、再び親権を獲得することが難しいという事例もありますので慎重な判断をする必要があります。
親の事情による環境の変化が、子どもにとって負担になってしまう可能性もあります。
子どもが15歳以上の場合には、子どもの意思が尊重される
子どもが15歳以上になると、親権について子どもの意思がより尊重される傾向にあります。
よって子どもが15歳以上で自分と一緒に住みたいと思っている場合では、親権を手放すことが難しいかもしれません。親権を手放した後に、回復したいと希望しても子どもが15歳以上で自分と暮らすことを望んでいない場合は難しくなるでしょう。
まとめ
配偶者が同意している場合には、親権を譲ることが可能です。
しかし、一度親権を手放すと気持ちが変わっても今までの養育状況や子どもの環境が重視され取り戻すことが困難となるおそれがあります。
養育費を請求されることもありますので、慎重に判断しましょう。