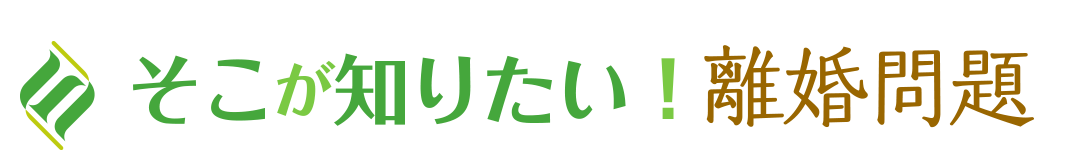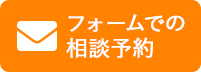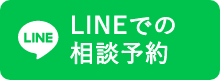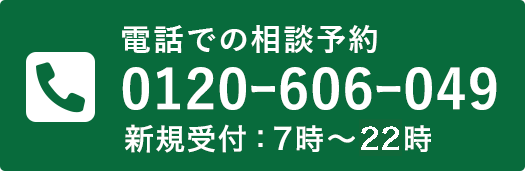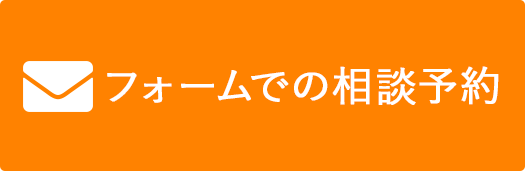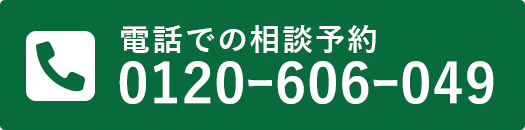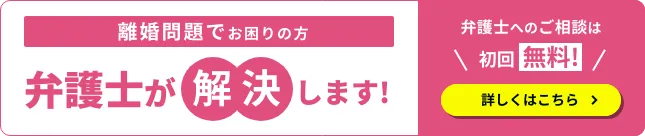

- 養育費の支払い義務者が自己破産をするとどうなる?
- 自己破産をした場合、養育費債権はどのように取り扱われる?
- 養育費の減額が認められる場合とは?
【Cross Talk 】自己破産をすると養育費を支払う必要はなくなるのでしょうか?
離婚した元妻に対して養育費を支払っていますが、自己破産をした場合には、養育費はどうなるのでしょうか。
養育費に関する債権は、自己破産によっても免除されないのが原則です。
自己破産をした場合の養育費の取り扱いについて、詳しく教えてください。
自己破産をすると、借金を帳消しにすることができるということをご存知の方は多いと思います。それでは、離婚をして月々の養育費を支払っている方が、自己破産をした場合、養育費の支払い義務も免除されるのでしょうか。この記事では、自己破産をした場合の養育費の取り扱いや、養育費の減額が認められる場合、養育費の支払いが難しい場合の対処法などについて、弁護士が解説していきます。
養育費の支払義務者が自己破産をするとどうなる?

- 債務者が自己破産をすると、借金の支払いが免除される
- 養育費の支払い債務については自己破産をしても免除されない
養育費を支払っている方が自己破産をするとどうなるのでしょうか?
ここでは、自己破産の概要やその効果について詳しくお伝えします。
自己破産をするとどうなる?
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、最終的に借金の返済義務を免除してもらう手続きのことです。
破産手続きは、借金の返済ができない状態に陥った債務者が裁判所に申立てを行い、裁判所が破産手続きの開始を決定することから始まります。その後、免責手続きを経て負債の返済義務を免除される仕組みです。
債務者(お金を支払う義務を負っている方)が、自分の財産を換価・処分して、債権者(お金を請求する権利を持っている方)に対して公平に分配する手続きを行います。その後、裁判所から「免責」決定を得ることによって、残った債務について支払義務が免除されることになります。
財産を持たない方や、浪費などの免責が認められない理由がない場合は、破産手続きの開始と同時に手続きが終了し、免責手続きに進みます。このような手続きを「同時廃止」と呼びます。
一方で、一定以上の財産を所有している場合(基準として生活費を除いた後の資産が20万円以上)や、免責に問題がある場合には「少額管財手続き」が適用されます。この場合、破産管財人が選任され、債権者集会を経て免責手続に移行します。
実際は免責手続に進んだほとんどの方が免責を受けており、最終的に借金の返済義務を免れる結果となっています。
非免責債権とは?
破産申立てを行い、裁判所によって免責の決定が出されると、債務の支払いが免除されるため、債務者は支払う必要がなくなります。しかし、自己破産をしたからといって、全ての債務・借金が免除されるとは限りません。破産法には、免責許可決定が出された場合であっても、支払いが免除されないものが存在しています。このような債権(債務者側から見ると債務)を、「非免責債権」といいます。
そして、非免責債権にあたるものとして、以下のような種類の債権があります(破産法第253条1項各号)。
したがって、離婚後に子どもに対して支払っている養育費の支払義務については、非免責債権であるため、自己破産をしても免除されないことになっています。
自己破産した場合の養育費債権の取り扱い

- 自己破産をした場合、過去の養育費の未払い分の取り扱いはどうなる?
- 自己破産をした場合、将来発生する養育費の取り扱いはどうなる?
養育費を支払っている親が自己破産をすると、過去や将来の養育費はどのように取り扱われるのでしょうか?
ここでは、自己破産をした場合の養育費債権の取り扱いについて、過去の未払分と将来発生分に分けて解説していきます。
過去の未払い分がある場合
養育費は非免責権なので、未払いのものであっても支払い義務がなくなることはありません。
しかし、破産手続き中、債権者は平等原則なので、支払いを受けることはできません。なお、破産手続き終了後は請求可能です。
自己破産しても将来の債権には影響なし
破産開始決定時に存在する債権だけが破産手続での公平な取り扱いの対象となります。そのため、未払い分がない場合や破産手続中以降に新たに発生する養育費については、引き続き支払請求を受けることになります。
破産手続が開始されたとしても、養育費の取り決めが自動的に無効になったり、変更されたりすることはありません。
しかし、後述のように、破産によって相手が失業したり収入が大幅に減少したりした場合には、養育費の減額を求める調停や請求が行われる可能性があります。大幅な収入減少が認められれば、養育費の取り決め自体が変更される可能性があるのです。
養育費の減額が認められる場合

- 養育費の減額が認められる義務者側の事情とは?
- 養育費の減額が認められる権利者側の事情とは?
それでは、どのような事情があれば、養育費の減額が認められるのでしょうか?
ここでは、養育費の減額が認められる事情について解説していきます。
養育費の減額が認められる条件については、養育費の「義務者側の事情」と「権利者側の事情」に分けて整理することができます。
まず、養育費を減額できる義務者側の事情として、以下のようなものが挙げられます。
ただし、単に再婚しただけでは養育費減額の理由にはなりません。扶養家族が増えた結果、経済的負担が増加する場合に限り、減額が認められる可能性があります。また、リストラや病気、ケガなど不可抗力による収入減少の場合は、養育費の減額が認められやすいでしょう。
上記に対して、権利者側の事情として、以下のような状況が挙げられます:
再婚相手が子どもと養子縁組を行った場合、再婚相手が法律上の扶養義務者となるため、子どもの扶養義務が一次的に再婚相手へ移ります。この場合、実親の扶養義務は二次的なものとなり、養育費が減額または免除されることがあります。ただし、再婚相手に収入がなく扶養が困難な場合は、実親が引き続き養育費を負担しなければならない場合もあります。
▼関連記事
養育費を減額できる場合・できない場合とは?減額請求の方法も解説
養育費の支払いが難しい場合の対処法

- 養育費の支払いが難しい場合の対処法とは?
- 話し合いがまとまらない場合には、養育費減額調停を利用する
養育費の支払いが経済的に難しい場合には、どうすればいいのでしょうか?
養育費の支払いが難しい場合の対処法について解説していきます。
減額交渉を行う
養育費を減額したい場合、まずは義務者側と権利者側が直接話し合いを行い、養育費の減額について合意を目指すという方法があります。父母双方の合意により減額することになるため、一番簡単な対処法であり、合意書を取り交わしておくことで事後的なトラブルも回避することができます。
家庭裁判所に養育費減額調停の申立てを行う
話し合いが不成立に終わった場合、または話し合いに応じてもらえない場合は、家庭裁判所に「養育費減額請求調停」を申立てます。
調停手続きでは、家庭裁判所の調停委員会が間に入り、公平な立場から話し合いを進めることになりますが、双方の合意が成立しない限り、調停は成立しません。
そして、調停での合意に至らない場合、「養育費減額審判」に進みます。この審判では、裁判官が双方の主張や提出された資料をもとに、養育費の金額変更が妥当かどうかを判断します。義務者側または権利者側が提出した証拠や資料を基に、裁判官が事情の変更を検討したうえで、養育費の金額変更が必要とされる場合、審判に基づいて決定が下されることになります。
▼関連記事
養育費請求調停とは?流れや有利に進めるコツについて弁護士が解説
まとめ
養育費の支払い義務者である側の親が自己破産をした場合であっても、養育費を請求する権利は、非免責債権とされているため、免除されることはありません。しかし、自己破産などによって、養育費の支払いが経済的に難しい場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。
養育費の減額を求める場合には、権利者側と直接交渉したり、養育費減額調停を申立てたりする必要があります。したがって、法律の専門家である弁護士に相談したうえで、対応を検討するようにしてください。当事務所には、養育費トラブルに詳しい弁護士が在籍しておりますので、お困りの場合にはすぐにお問い合わせください。