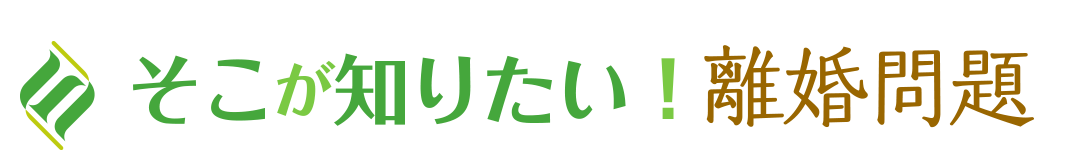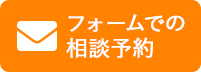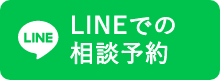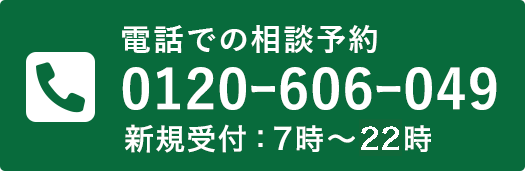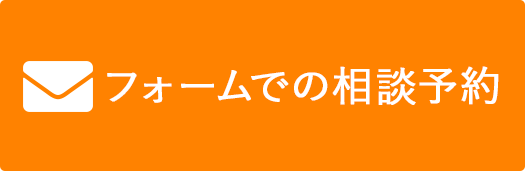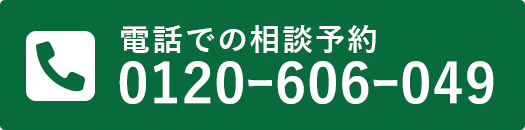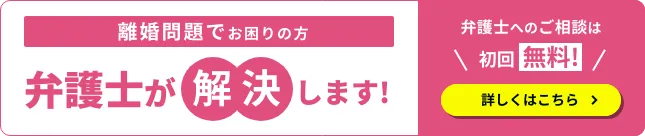

- 離婚後でも養育費の請求は可能
- 離婚後に養育費を請求する方法
- 離婚後に養育費を請求する場合の注意点
【Cross Talk 】離婚後も養育費を請求することはできる
離婚してから時間が経ちましたが、離婚した相手に養育費を支払ってもらうことはできますか?
離婚後であっても養育費の請求は可能です。
離婚後の養育費請求について詳しく教えてください。
離婚する際、子どもの親権者は定めたものの、養育費などの取り決めを一切せずに離婚してしまう方も少なくありません。養育費は子どもが成人するまで受け取ることができるお金であるため、離婚してから受け取りたいと思うようになる親権者の方もいます。離婚後であっても養育費を受け取れるのでしょうか。
このコラムでは、離婚後の養育費の請求の可否や、その方法、注意点などについて解説していきます。
離婚後でも養育費の請求は可能

- 養育費とは?
- 養育費の相場とは?
養育費は離婚後であっても受け取ることができますか?
養育費は離婚後であっても請求できます。
養育費とは
「養育費」とは、離婚後に子どもを監護する親(監護親)から子どもを監護しない親(非監護親)に対して請求する、子どもの養育に必要な費用のことです。
養育費は、子どもが経済的に自立するまで受け取ることができるため、子どもが20歳になるまでを目安に(両親とも大卒程度である場合には、大学を卒業するまで)受け取ることができます。
配偶者と一刻も早く離婚したいがために、養育費や財産分与、慰謝料などを請求せずに離婚してしまう方も一定程度いらっしゃいます。離婚時に養育費の取り決めをしていないという世帯は、母子世帯では50%以上、父子世帯では約70%と非常に多くなっています。
そもそも、「子の監護に関する費用の分担」については、離婚する際に父母の協議で決定することが基本です(民法第766条1項)。しかし、親が負っている未成熟の子に対する扶養義務(民法第877条1項)は、離婚後であっても消滅するものではありません。
そのため、養育費は、離婚後であっても離婚した相手に請求することができます。
養育費の相場
養育費の金額については、両親が話し合って決定することができます。
ただし、話し合いでは具体的な金額が決まらないという場合には、裁判所が公表している「養育費算定表」を参考にして、月々の養育費の金額を算出することが一般的です。
この養育費算定表は、子どもの人数や年齢、父母の年収をもとに標準的な養育費の月額の目安が定められています。
なお、厚生労働省が公表しているデータによると、令和3年度の子どもの数別の養育費の平均月額は以下の通りです。これは、養育費を現在も受けている・受けたことがある世帯で、養育費の金額が決まっている世帯に関する統計です。
| 子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 | 子ども4人 | 総数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 母子世帯の養育費の平均月額 | 40,468円 | 57,954円 | 87,300円 | 70,503円 | 50,485円 |
| 父子世帯の養育費の平均月額 | 22,857円 | 28,777円 | 37,161円 | – | 26,992円 |
(厚生労働省「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」より)
離婚後に養育費を請求する方法・流れ

- 離婚後に養育費を請求する方法は?
離婚後に養育費を請求するにはどうすれば良いのでしょうか?
離婚後の養育費の請求方法・流れについて解説します。
当事者間で話し合う
離婚後に元配偶者に養育費を請求する場合には、まずは相手に連絡をとったうえで話し合いを行う必要があります。ただし、離婚の理由や経緯によっては、養育費は請求したいけれど、相手と直接連絡を取り合うのは避けたいという方も少なくありません。
そのような場合には、直接会わない方法(電話やLINE)を利用するか、弁護士に依頼して代理で話し合いを行ってもらうという方法をとることもできます。
話し合いでは、養育費の金額、支払方法、支払期限などを決める必要があります。
父母間の話し合いがまとまれば、取り決めた項目を書面に落とし込む必要があります。また、合意書を公正証書の形で残しておけば、相手が支払いに遅れた場合であっても、強制的に回収できる可能性もあります。公正証書に「強制執行認諾文言」を付けておくことで、裁判等を経ることなく強制執行の申立てを行うことができます。
養育費請求調停・審判
父母間の話し合いでは決まらない場合や、相手が養育費の支払いを拒否した場合には、家庭裁判所に養育費請求調停を申立てることができます。
調停手続きとは、当事者の間に調停委員会(裁判官1名・調停委員2名)が入り、双方から意向や事情を聴き取ったうえで、話し合いによって解決を目指す手続きです。
調停委員を介することで客観的・合理的なアドバイスや解決策を受けることが期待できるため、当事者だけで話し合うよりもスムーズな話し合いが期待できます。
調停が成立しなかった場合には、調停の経緯を踏まえて、裁判官が審判を行います。審判では、裁判官が養育費の金額や期間などを決定します。
離婚後に養育費を請求する際の注意点

- 養育費には時効がある
- 過去の養育費分の請求は難しい
離婚後に養育費を請求したい場合、気を付けなければならないことはありますか?
離婚後の養育費請求の注意点を解説します。
養育費請求権には時効がある
まず、養育費請求権には消滅時効があります。
親権者が養育費を請求できることを知ったときから5年が経過すると時効が完成します。また、請求できることを知らなかったとしても権利を行使することができるときから10年経過すると、養育費を請求することはできなくなります。
過去の養育費の請求は難しい
原則として、養育費は請求した時点以降の分について支払いが認められます。
そのため、過去に遡って受け取っていなかった部分を請求することは難しくなります。
しかし、養育費請求調停の申立てよりも前の時点で養育費を請求していることが明らかであれば、過去の養育費についても、請求できる可能性があります。ただし、過去に請求したことが証拠によって証明できる必要があるため、注意が必要です。
まとめ
以上、養育費は離婚後であっても離婚相手に請求することができますが、相手が任意の支払いに応じない場合には、養育費請求調停を申立てる必要があります。
離婚後の養育費についてお困りの方は、家事事件に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、相手方との交渉や裁判手続きについてもすべて任せておくことができます。