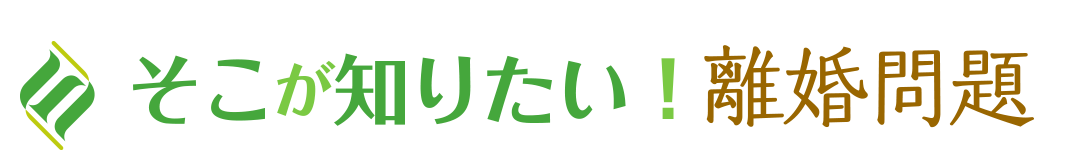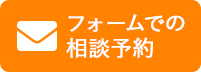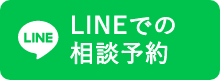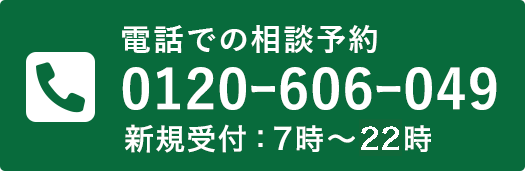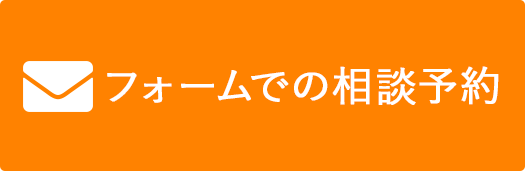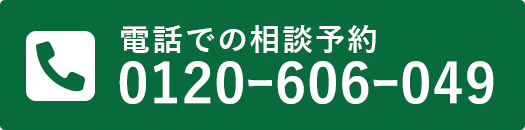- 離婚する際、不動産は財産分与の対象となるか?
- 不動産を財産分与する方法とは?
- 不動産の財産分与の注意点とは?
【Cross Talk 】不動産の財産分与はどうすればいいですか?
夫と離婚する予定なのですが、自宅は財産分与の対象となりますか?
結婚後の共有財産については、2分の1ずつ財産分与することになります。
不動産の財産分与について、詳しく教えてください。
夫婦は離婚する際に、共有財産について財産分与をすることになります。建物や土地などの不動産についても財産分与の対象となる可能性があります。それでは、どのような不動産が財産分与の対象となるのでしょうか。不動産の財産分与の方法や注意点はどのようなものなのでしょうか。このコラムでは、これらの疑問点について、弁護士が解説していきます。
不動産は財産分与の対象となる?

- 不動産が共有財産の場合には、財産分与の対象となる
- 不動産が特有財産の場合には、財産分与の対象とならない
夫の名義で登録している自宅は、財産分与の対象となるのでしょうか?
不動産が共有財産である場合には、財産分与の対象となります。詳しく紹介していきます。
共有財産は財産分与の対象
夫婦が離婚する際には、相手方に対して財産分与を請求することができます。財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を離婚のときに分け合うことで、財産に対する実質的な持分を清算することになります。
このような財産分与の制度趣旨から、財産分与の対象となる財産は、「夫婦が婚姻期間中に協力して取得した共有財産」です。
そのため、結婚後に夫婦が共同で生活するための自宅として購入した不動産については、財産分与の対象となる共有財産になります。
また、夫婦の共同生活から生じた通常の債務については、夫婦が連帯して負担している債務であり、財産分与の対象財産です。さらに、住宅ローンなど、夫婦の共有財産を形成するために負担したローンや借金などの債務についても、財産分与の対象となります。
特有財産は財産分与の対象にはならない
特有財産は、財産分与の対象とはなりません。
特有財産とは、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産」や、「婚姻とは無関係に得た財産」のことを指します。具体的に以下のような不動産については、特有財産となるため、財産分与する必要はありません。
- 独身時代に購入した土地や建物などの不動産
- 独身時代・結婚後に親族からの相続により承継した不動産
- 独身時代・結婚後に遺贈された不動産
- 結婚後、別居後に購入した土地や建物などの不動産
財産分与の割合は原則として2分の1
財産分与の分与割合は、原則として2分の1ずつとなります。
財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して取得した共有財産を離婚する際に公平に分担することにあります。そして、婚姻期間中に共有財産を取得するための夫婦の貢献度は等しいものと考えられています。
夫婦の一方が専業主婦・主夫であったとしても、2分の1の財産分与請求権があります。
専業主婦・主夫のように会社に勤務して給与収入を得ていない場合であっても、家庭で家事労働に貢献したことによって、他方が給与収入を得ることに集中できたと評価されます。
そのため夫の単独名義の不動産であっても、夫婦が婚姻期間中に取得したものである場合には、2分の1の財産分与を請求できます。形式的に単独名義で登記されていたとしても、夫婦の共有財産と評価される限り、自宅は夫婦それぞれに等しい持分が認められます。
不動産を財産分与の方法とは?

- 不動産の財産分与の方法とは?
- 不動産の財産分与には、引き継ぐ・売却するという方法がある
不動産の財産分与はどのようにすればいいのでしょうか。
持ち家の財産分与の方法として、引き継ぐか売却するという方法があります。
売却して現金化する
不動産の財産分与の方法として、不動産を売却してその代金を分割するという方法があります。
この場合、不動産仲介会社に依頼して、買い主を見つけてもらうという方法と、不動産会社に直接買い取ってもらうという方法があります。
不動産の売却代金から諸経費を除いた金額を夫婦で分け合うため、わかりやすく夫婦間でトラブルになることも少ないでしょう。
ただし、不動産が売れない場合には、この方法はとれないため注意が必要です。特に後述のように、不動産に住宅ローンが残っている場合には売却代金とローン残高と多寡が問題となります。
夫婦の一方が住み、他方が現金を受け取る
不動産を夫婦のどちらか一方が取得する代わりに、不動産を取得しなかった側に評価額の半分相当の現金を支払うという分け方もあります。
夫婦のうち一方が購入した自宅不動産に住み続けたい場合には、この方法が選択される場合があります。現金を受け取る場合も、まとまった資金を得ることができます。現金については、不動産の査定をもとに評価額を確定させて、その半分が支払われます。また、住み続ける側の単独名義で登記しておく必要があります。
この分与方法の場合には、実際に不動産は売却されないため、夫婦で何かしらの基準をもとに話し合いで価格を決める必要があります。
一般的には不動産の固定資産評価額や、実勢価格をもとに決めることが通常ですが、どうしても話し合いで決まらない場合には、不動産鑑定士などの専門家に査定を依頼して価格を決めることもあります。
不動産の財産分与の注意点

- 不動産の財産分与の注意点
- 住宅ローンが残っている不動産の財産分与は注意が必要
不動産の財産分与で注意しておくことはなんでしょうか?
住宅ローンが残っている不動産を分与する場合には、注意が必要となります。
住宅ローンが残っている不動産を財産分与する場合には、注意が必要です。
住宅ローンがある場合、不動産の価値が住宅ローンの残高を上回っている状態(オーバーローン)と、不動産の価値が住宅ローンを下回っている状態(アンダーローン)によって、取り扱いが異なってきます。
まず、アンダーローンであれば、不動産の売却代金で住宅ローンを全額返済できます。
不動産を売却して財産分与する場合には、残った現金を夫婦で分け合うことができます。また、一方が不動産に住み続ける場合には、不動産の価格から住宅ローンを除いた金額を分けつつ、残った住宅ローンについては住み続ける側が返済し続ければ良いでしょう。
これに対して、オーバーローンの場合には、不動産を売却したとしても住宅ローンを完済することができません。そのため、残りのローンの支払いについては、夫婦の現預金など共有財産から捻出する必要があります。
したがって、オーバーローンの不動産を売却するためには、住宅ローンを完済できる余剰資金がなければならず、そうでなければ不動産を売却するという選択肢はとれなくなります。
まとめ
以上、婚姻期間中に夫婦が協力して取得した不動産については、財産分与の対象となります。財産分与の割合については、基本的に夫婦が等しく分け合うことになります。不動産の財産分与の方法については、不動産を売却して代金を分け合う方法と、一方が住み続け他方が現金を受け取る方法があります。
離婚する際、財産分与についてお悩みの方は、弁護士に相談するようにしてください。離婚問題に詳しい弁護士に相談することで、不動産の財産分与を含めた離婚問題について、適切なアドバイスやサポートを受けることができます。