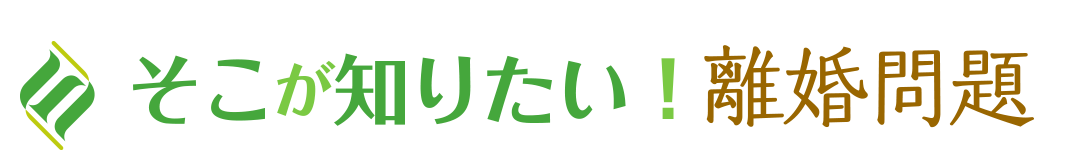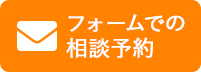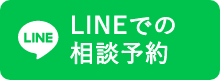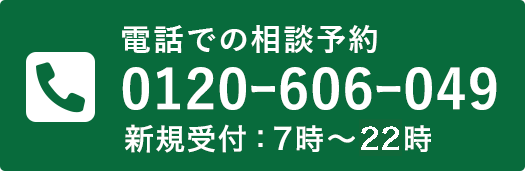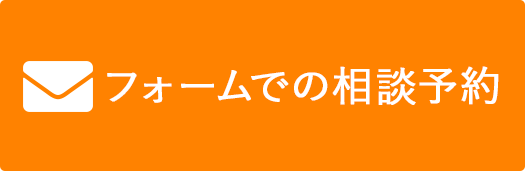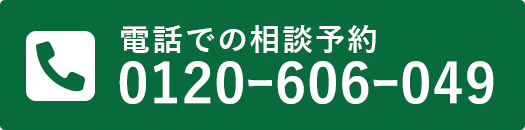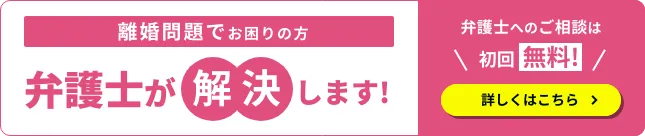

- 財産分与とは?
- 財産分与の割合は原則として「2分の1」
- 財産分与の「2分の1原則」の例外となる場合は?
【Cross Talk 】財産分与の2分の1原則はどのような場合に変更されるのでしょうか?
財産分与の割合は必ず2分の1なのでしょうか?
財産分与の割合は原則として2分の1ですが、例外的にこの割合を変更できることもあります。
財産分与の割合について、詳しく教えてください。
夫婦が離婚する際には、婚姻中に取得された共有財産について財産分与を請求することができます。財産分与の割合は、夫婦が公平になるように、原則として「2分の1」とされていますが、例外的な事情がある場合には、この原則の例外が認められる場合があります。この記事では、財産分与の割合や、財産分与の割合の例外が認められる場合について、弁護士が解説していきます。
財産分与の割合とは?

- 財産分与とは?
- 財産分与の割合は原則として2分の1
財産分与の割合は、どれくらいなのでしょうか?
財産分与の割合は、原則として2分の1です。
財産分与の割合は原則「2分の1」
夫婦が離婚する際には、相手方に対して財産の分与を請求することができます。これを離婚における財産分与といいます。離婚に際して、夫婦にこのような財産分与の権利が認められている理由は、結婚期間中に夫婦が協力して取得した財産を、離婚する際に公平に分け合うためです。
財産分与の対象となる財産は、夫婦が結婚してから協力して取得した共有財産です。そして、財産分与の割合は、原則として「2分の1」とされています。仮に、形式的に夫の名義になっている不動産や預貯金であっても、その半分については妻にも分与を受ける権利があると考えられています。
さらに、夫婦の一方が専業主婦(主夫)であったとしても、2分の1の割合で財産分与を請求できます。専業主婦(主夫)は会社に勤務して給与を得ているわけではありませんが、他方が家庭で家事労働に貢献してくれているおかげで、もう一方が会社勤めに集中できると評価されています。
このように、夫婦の婚姻生活の貢献度は等しいと考えられており、夫婦が共働きの場合も、他方が専業主婦(主夫)であってもこの考え方は変わりません。
夫婦の合意により分与割合を変更できる
夫婦の婚姻期間中の財産形成への貢献度は等しいと考えられているため、財産分与の割合は、原則として「2分の1」とされています。
しかし、財産分与の割合や分与の方法については、法律で基準が定められているわけではありません。
そのため、夫婦がお互いに2分の1とは異なる割合で財産分与を行う合意ができる場合には、分与割合を変更することができます。
例えば、早期に離婚を成立させたいという方は、財産分与の分与割合を交渉の材料として早期に離婚を成立させるということも可能です。
さらに、財産分与をしないという選択も可能です。財産分与請求権はあくまで権利であるため、放棄することができます。夫婦が話し合いで「財産分与をしない」と合意できれば、財産分与をせずに離婚をすることも可能です。
例外的に財産分与の割合が変更される場合とは?

- 財産分与の2分の1原則が変更される場合とは?
財産分与の2分の1原則が変更されることはありますか?
ここでは、財産分与の2分の1原則の例外が認められる場合を解説します。
一方の特殊な才能・能力によって財産を形成した場合
財産分与の「2分の1原則」の例外が認められる場合として、夫婦の一方が特殊な才能や能力によって財産を得られた場合があります。このような場合には、財産分与の割合が変更され、才能・能力を有する方に傾斜がかけられるケースがあります。2分の1原則が特殊な才能・能力によって変更される場合、その割合は個別的な事情によって判断されますが、例えば、「6:4」といった割合に変更される可能性があります。
会社経営など本人の経営能力や人脈によって、多くの財産を形成したような場合には、特殊な才能・能力が評価され、財産の分与割合が変更されます。例えば、医療法人を経営している医師である夫に、妻が、共有財産(約3億円)の財産分与を請求して事案においては、夫の個人的な努力や資格を考慮して、妻の割合を40%と判断したケースもあります。
一方の浪費が著しかった場合
財産分与の「2分の1原則」は、夫婦の財産形成や維持に対する貢献度は、基本的には等しいと考えられていることに由来します。そのため、夫婦の一方が財産形成や維持に対して全く貢献していないという場合には、財産分与の割合が修正される可能性があります。
例えば、夫婦の一方がギャンブルやブランド品の購入などによって高額な浪費をして、夫婦の共有財産を減少させたという事情がある場合には、その方の財産分与割合は、2分の1を下回る可能性があります。
特有財産を元手に財産を形成した場合
特有財産とは、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産」と「婚姻中自己の名義で得た財産」のことを指します。例えば、結婚するよりも前に取得した不動産や預貯金などは、一方の特有財産となります。
特有財産は財産分与の対象とはなりません。
そして、特有財産を元手にして財産を形成したという場合でも、その特有財産が財産形成に貢献した割合が大きいため、財産分与割合が変更される可能性があります。
例えば、親族が亡くなり不動産を相続した場合、その不動産の賃貸収入を婚姻期間中に得ていた場合には、特有財産を元手に形成された財産であると評価できます。また、結婚するよりも前に購入していた株式や投資信託が高騰した場合や、そこから得られる配当金などについても、特有財産から派生した財産であると考えられます。
まとめ
夫婦が離婚する場合には、財産分与を請求することができ、その割合は原則として「2分の1」とされています。しかし、共有財産の形成に、夫婦の一方の貢献度が著しく高い場合、または著しく低い場合には、この2分の1原則が変更される可能性があります。
どのような事情で、どの程度財産分与の割合が変更されるのかは、過去の裁判例や具体的な事情によってケースバイケースで判断されることになります。
離婚に際して財産分与についてお悩みの場合には、お早めに弁護士に相談するようにしてください。離婚問題に詳しい弁護士に相談することで、適切なアドバイスや法的なサポートを受けることができます。