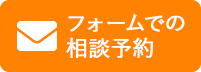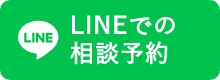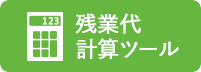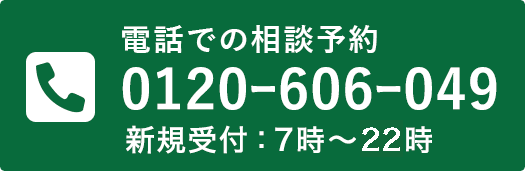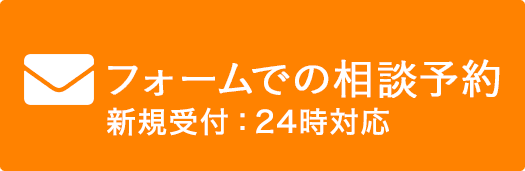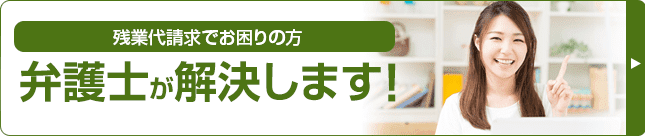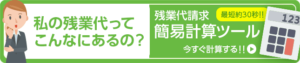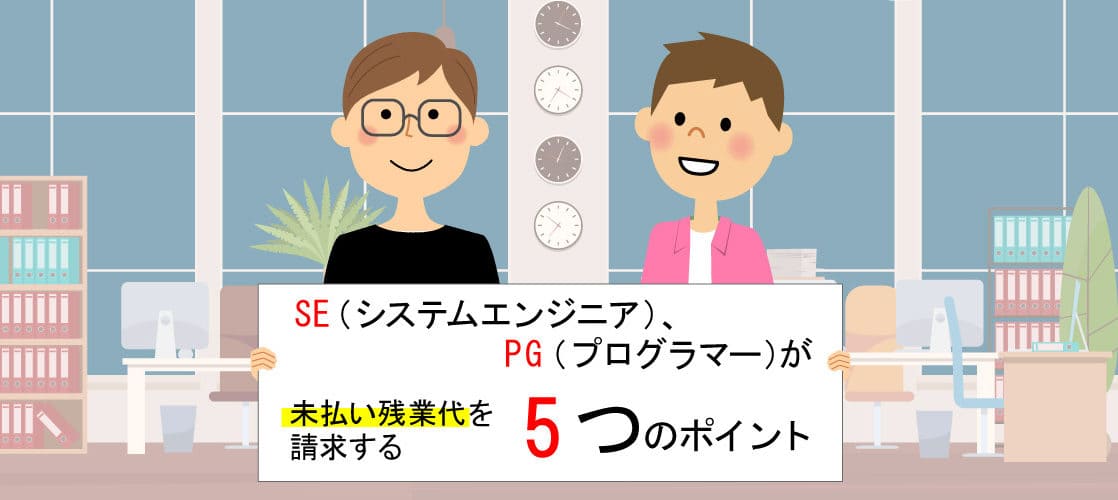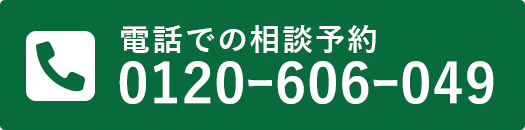- IT業界では長時間のサービス残業が珍しくない
- 証拠収集は残業代請求の要!IT業界特有の証拠も
- 業務委託でも実質的な雇用関係にあるならば残業代請求できる
- 裁量労働制、みなし残業、年俸制でも残業代請求できる場合がある
【Cross Talk】SEには残業代を支払わなくてもいいの?
SEとして働いているのですが、毎日深夜まで残業をしているのに残業代を支払ってもらえません。
同業者から同じような話を聞くこともあるのですが、SEは残業代を請求できないのですか?
そんなことはありません。契約形態や労働条件によって要件は異なりますが、SEやPGも残業代を請求することができます。
残業代を請求できることがあるんですね。詳しく教えてください!
SE(システムエンジニア)やPG(プログラマー)のようにIT業界で働く職種は、一般的に激務というイメージを持たれており、実際に長時間の残業をしている方は大勢いらっしゃいます。
法律で認められた範囲で残業をし、それに対してきちんと残業代が支払われているのなら問題ありませんが、長時間の残業をさせているにも関わらず残業代を支払っていないブラック企業もあり、未払い残業代についてお悩みのSEやPGは少なくありません。
そこで今回は、SEやPGのようにIT業界で働く方が未払い残業代請求をするポイントを解説します。
IT業界特有の労働環境

- 厳格な納期や人手不足から長時間労働が当たり前になっている
- 下請けや孫請けを中心に体力のない企業ではサービス残業が横行している
どうしてIT業界では残業代が出ないことが多いのですか?
IT業界では、納期が厳しいことや人手不足などが原因で長時間の残業をせざるを得ないことが少なくありません。また、IT業界にも下請け、孫請けがあるので、孫請けに支払われる単価自体が低くなってしまうことがあります。このような理由から、SEは長時間の労働を強いられるのに、会社には残業代を支払うだけの体力がなく、結果として残業代が支払われなくなってしまうのです。
労働基準法は、法定労働時間を厳格に定め、法定労働時間を超える労働について割増賃金の支払いを義務付けるなど、基本的に労働時間の長さに応じた賃金を支払うことを想定しています。
しかし、業務の内容によっては、労働時間を労働者の裁量にゆだね、かつ労働の長さではなく労働の成果によって賃金を支払うのがふさわしいものもあります。
SEやPGのようなIT業界の労働環境には、
・クライアントの希望による仕様変更が頻繁に行われることがある
・慢性的に人材不足であり、今後ますます深刻化すると予想される
などの理由から、長時間の残業をせざるを得ない職場が多いという特徴があります。
また、IT業界にも、建設業界と同じように、下請け、孫請けがあります。クライアント(発注者)から支払われる報酬から元請け、下請けの取り分が差し引かれるので、孫請けに残る金額はどうしても少なくなってしまいます。
そうなると、従業員には長時間の残業をさせないと納期に間に合わない、しかし従業員に残業代を支払う余裕がないということになりかねません。そのため、以下で解説するような理由を付けて、残業代を払わない会社が少なくないのです。
IT業界で未払い残業代請求する5つのポイント

- 証拠の収集が重要!
- 業務委託契約と題されていても残業代を請求できるケースがある
- 裁量労働制、みなし残業、年俸制でも残業代を請求できる
SEが残業代の請求をする場合、具体的にどんなことに気をつければいいのですか?
まず、証拠を集めることが重要です。一般的なタイムカードのほか、パソコンのログ記録などIT業界特有の証拠もあります。また、会社は、労働契約ではなく請負契約である、裁量労働制だから残業代は支払わないなど、残業代の未払いを正当化するさまざまな主張をすることが予想されるので、これらの会社の主張に対し、適切に反論していく必要があります。
IT業界特有の証拠
どれだけ残業をしても、証拠がなければ会社は残業代の支払いには応じないでしょうし、裁判をしても裁判所は残業代の支払いを認めてくれません。
ですから、証拠収集は残業代請求の要といえます。
残業した時間(実労働時間)についての証拠としては、一般的にタイムカード、業務日誌、シフト表、従業員が個人的に作成した日記・メモなどがあります。
それに加えて、IT業界の場合、パソコンを使用した業務が中心となることから、パソコンのログ記録、クライアントとの電子メールの送受信記録なども残業時間に関する証拠になります。
また、IT業界の場合、機密情報の保護が重要になりますから、セキュリティのしっかりしたビルにオフィスを構えたり、独自に警備会社と契約したりしていることが多いので、ビルや事務所の入退館記録が残っていることがあり、これも残業時間に関する証拠になります。
契約形態を確認する
残業代を含む労働条件を規制する労働基準法は、労働契約について適用されるものです。
労働契約とは、労働者が使用者の指揮命令下において労務を提供し、使用者がその対価としての賃金を支払うことを内容とする契約です(労働契約法6条)。
ところで、人に何らかの仕事をさせ、その対価を支払うことを内容とする契約は、労働契約だけではありません。たとえば、「業務委託契約」と呼ばれる契約があります。
業務委託契約は、民法上、①仕事の完成を目的とし、その対価として報酬を支払うことを内容とする請負契約と、②一定の事務を処理することを目的とし、その対価として報酬を支払うことを内容とする準委任契約とに区別することができます。
いずれも労働契約と異なり、時間的・場所的な拘束を受けず、注文者・委任者から仕事の具体的なやり方について指揮命令を受けず、自身の裁量でで仕事を進める権利があることに特徴があります。
SEやPGと会社との間の契約が労働契約ではなく業務委託契約であった場合、労働基準法は適用されず、残業代は請求できません。そのため、残業代を請求する前に会社との契約形態をきちんと確認する必要があるのです。
なお、このことを悪用して、実際には労働者を使用者の指揮命令下に置いて労務提供させているにもかかわらず、契約の名称を業務委託契約と題する等して、労働基準法の適用を免れようとする会社もあります。
契約が、労働契約にあたるのか業務委託契約にあたるかは、その形式ではなく、その実態に基づいて判断されます。そのため、業務委託契約という名目であっても、実質的に労働契約と同視できるような実態がある場合には場合には、労働基準法が適用され、残業代を請求することができます。
裁量労働制でも残業代請求ができる
会社から、「裁量労働制だから残業代は出ない」と言われることがあります。しかし、裁量労働制であれば一切残業代を請求できないというわけではありません。
裁量労働制とは、一定の専門的・裁量的な業務に従事する労働者について、実際に働いた時間にかかわらず、事前に決めた時間(みなし時間)だけ働いたものとみなす制度をいいます。
裁量労働制には、専門業務型裁量労働制(労基法38条の3)、企画業務型裁量労働制(労基法38条の4)の2種類があり、どちらも対象となる業務や導入するための手続等について、厳格な要件が定められています。
SEやPGに関しては、専門業務型裁量労働制が採用されている場合があります。
専門業務型裁量労働制が認められるのは、厚生労働省令で定める業務に限られますが、その業務の一つとして、「情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務」(労働基準法施行規則24条の2の2第2項2号)が挙げられているからです。
しかしながら、ここでいう「情報処理システムの分析又は設計の業務」とは、
・入出力設計、処理手順の設計等アプリケーション・システムの設計、機械構成の細部の決定、ソフトウェアの決定等、
・システム稼働後のシステムの評価、問題点の発見、その解決のための改善等の業務
をいうとされており、プログラムの設計又は作成を行うプログラマーは含まれないとされています
参考:厚生労働省「専門業務型裁量労働制」(参照 2019/03/19)
したがって、PGはもちろん、肩書はSEであっても情報処理システムの分析・設計に従事していないSEについては、専門業務型裁量労働制の対象業務の要件を満たさないことになります。
また、情報処理システムの分析・設計に従事しているSEであっても(いいかえれば対象業務の要件を満たしていても)、導入するための手続の要件を満たさない場合があります。
したがって、会社が専門業務型裁量労働制を導入したと主張しても、実際には要件を満たしていないことも少なくありません。専門業務型裁量労働制の要件を満たしていない場合、実際の労働時間に関係なく、みなし時間働いたとみなすことはできません。
みなし時間が8時間であった場合、実際には8時間を超えて働いたとしても8時間働いたものとみなされるので、残業代を請求することはできません。
ただし、みなし時間が8時間を超える場合、8時間を超えた部分については残業代を請求することができます(たとえば、みなし時間が10時間であった場合、2時間分の残業代を請求することができます)。
このように、専門業務型裁量労働制の要件を満たしたSEであっても、残業代を請求できる場合があるのです。
裁量労働制について詳しく知りたい方は「裁量労働制(みなし労働制)の場合の残業代請求」をご参照ください。
「みなし残業(固定残業制)だから残業代は出ない」は誤解
会社から、「みなし残業(固定残業制)だから残業代は出ない」と主張されることがあります。しかし、みなし残業だから固定残業代以外は支払う必要がないというのは間違いです。
みなし残業(固定残業制)とは、あらかじめ一定の残業を想定し、それに対する時間外手当を取り決め、実際の残業時間にかかわらず支給する制度をいいます。
みなし残業の合意が有効と認められるためには、
・当該定額(固定額)が労基法所定の額を下回るときは、その差額を当該賃金の支払時期に精算するという合意が存在するか、あるいは少なくとも、そうした取扱いが確立していること
など厳しい要件を満たさなければならないとされています(イーライフ事件・東京地判平25・2・28労判1074・47)。
したがって、会社がみなし残業を主張しても、これらの要件を満たしていない場合には、みなし残業の合意は無効であり、残業代を請求することができます。
また、みなし残業の合意は有効であっても、合意で想定された残業時間よりも長く残業した場合、実際の残業時間をもとに計算した残業代の額と既に支払われた固定残業代との差額を請求することができます。
詳細は別コラムをご参照ください。
年俸制でも残業代請求はできる
会社から、「年俸制だから残業代は出ない」と主張されることがあります。しかし、年俸制だけを理由に残業代を支払わなくてもいいということにはなりません。
年俸制は給与を1年単位で決定する(1年間に支払われる給与の額があらかじめ決まっている)というものにすぎず、年俸制を採用したからと言って労働時間や残業代(割増賃金)についての労働基準法の規定が適用されなくなるわけではないからです。
したがって、年俸制であっても残業代を請求できる場合があります。詳細は別コラムをご参照ください。
まとめ
SE、PGの未払い残業代請求について解説しました。IT業界は長時間労働が当たり前といった風潮があり、サービス残業を強いるブラック企業もいまだに少なくないのが現状です。
しかし、残業代の請求は、あなたが使用者に対して労務を提供した対価として法律上認められた当然の権利です。使用者はあなたの労務提供によって利益を受けているのですから、その対価については泣き寝入りなどせず、毅然とした態度で回収するべきといえます。ご自身で請求することに不安があるという方は、労働問題に詳しい弁護士に相談するといいでしょう(弁護士の探し方については、「未払い残業代請求について弁護士の探し方や相談の仕方とは?」をご参照ください。)。