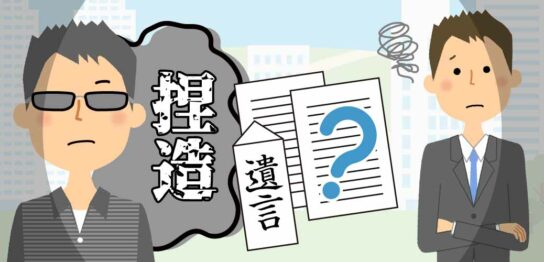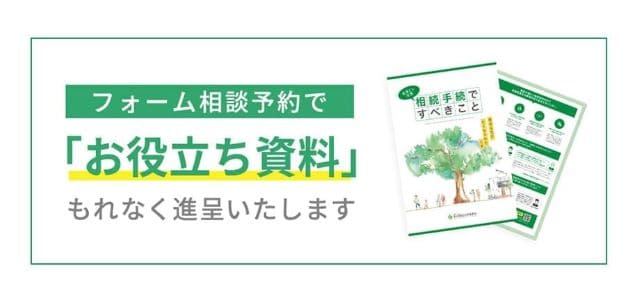- 非嫡出子は法律婚でない男女の間に生まれた子どもである
- 非嫡出子抜きで遺産分割協議をしても無効になってしまう
- 遺言書を作成しておくと非嫡出子と相続人の相続トラブルを防止しやすくなる
【Cross Talk 】非嫡出子の法定相続分は嫡出子と同じ?
私は非嫡出子ですが、法定相続分は嫡出子よりも少なくなってしまうのでしょうか?
民法の改正によって、非嫡出子の法定相続分は嫡出子と同じになりました。とはいえ、非嫡出子がいる相続では注意点もあります。
非嫡出子の法定相続分は嫡出子と同じになったんですね。非嫡出子の相続における注意点についても詳しく教えてください!
法律婚でない男女の間に生まれた子どもを非嫡出子といいます。 民法の改正によって、非嫡出子の法定相続分は嫡出子と同じになりましたが、非嫡出子がいる相続には注意すべき点もあるのです。 そこで今回は、非嫡出子の法定相続分や相続の注意点などを解説いたします。
非嫡出子とは?相続分はどうなる?

- 非嫡出子は法律婚でない男女の間に生まれた子どもである
- 非嫡出子と嫡出子の法定相続分は同じである
私は非嫡出子なのですが、相続人になった場合、認知をされていても相続分は嫡出子よりも少なくなってしまうのでしょうか?
民法の改正によって、非嫡出子と嫡出子の間の法定相続分の差異はなくなりましたので、安心してください。
非嫡出子とは
非嫡出子とは、法律婚をしていない男女の間に生まれた子どものことです。 法律婚とは法律によって婚姻関係が認められることであり、婚姻届を提出することで成立します。 いわゆる事実婚や内縁関係など、婚姻届を提出していない男女の間に子どもが生まれた場合は、非嫡出子にあたります。非嫡出子の場合、母親との親子関係は出生によって当然に認められますが、父親との親子関係が認められるには認知の手続きが必要です。 そのため、非嫡出子の方が父親の相続の際に相続人となるためには、認知をされているか、父の死後3年以内の死後認知請求訴訟により親子関係が成立している必要があります。
また、法律婚の夫婦の間に生まれた子どもを「嫡出子」といいます。嫡出子の場合は、認知によらずに父親との親子関係も認められます。非嫡出子の相続分は現在では嫡出子と同じ
非嫡出子の法定相続分(民法が規定する相続の割合)は、以前は嫡出子よりも低く設定されていましたが、民法の改正によって嫡出子と同じになっています。民法の改正前は、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の法定相続分の1/2でした。
しかし、非嫡出子であることを理由に法定相続分を半分とすることは、憲法が定める法の平等に反する規定であるとの批判が古くからあり、ついに最高裁も違憲の決定を下しました。最高裁の決定を受けて民法が改正された結果、非嫡出子の法定相続分は嫡出子と同じ割合になったのです。
非嫡出子でも遺留分侵害額請求は可能
非嫡出子が相続人の場合も、遺留分侵害額請求が可能です。被相続人の配偶者や子どもなど、一定の法定相続人には遺産の最低限の取り分が法律で認められており、遺留分といいます。 遺言書などによって遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害した者に対して、遺留分に相当する金銭を請求することができ、遺留分侵害額請求といいます。
非嫡出子が相続人であっても、遺留分を侵害された場合は遺留分侵害額請求が可能です。 例えば、遺産の総額が1,000万円であり、相続人として嫡出子と非嫡出子の2人がいる場合に、「嫡出子に全ての遺産を相続させる」という遺言書があったとしましょう。上記においては、非嫡出子には遺留分として250万円(遺産の総額の1/4)が認められます。 嫡出子が1,000万円全てを相続した場合、非嫡出子は250万円の遺留分を侵害されているので、遺留分侵害額請求として、長男に250万円の金銭の支払いを請求できます。
非嫡出子を参加させずに遺産分割協議をするとどうなる?

- 遺産分割協議を成立させるには相続人全員の同意が必要
- 認知のされている非嫡出子抜きで遺産分割協議をしても無効になってしまう
仲の悪い非嫡出子が相続人にいるのですが、遺産分割で揉めたくありません。非嫡出子なしで遺産分割協議をしても大丈夫ですか?
遺産分割協議を成立させるには相続人全員の同意が必要であり、非嫡出子の場合も同様です。一人でも欠けると協議が無効になるので注意してください。
非嫡出子を除いてした遺産分割協議は無効
非嫡出子であっても認知により親子関係がある場合には相続人となり、その人を除外して遺産分割協議をすると、協議は無効 になってしまいます。 遺産分割協議とは、相続人が話し合いをして、遺産をどのように分割するかを決める手続きのことです。 被相続人が遺言書によって遺産の分割方法を指定していない場合は、遺産分割協議によって遺産をどのように分割するかを決める必要があります。非嫡出子と日頃から疎遠であったり、仲が悪かったりした場合は、非嫡出子を交えずに遺産分割協議を成立させたくなるかもしれません。 しかし、遺産分割協議を成立させるには、相続人全員が遺産分割協議の内容に同意する必要があります。
相続人のうち一人でも同意が欠けている場合は、遺産分割協議をしても無効になってしまいます。 これは非嫡出子の場合も同様なので、もし非嫡出子の同意なしで遺産分割協議をした場合、協議は無効になるので注意しましょう。非嫡出子がいる場合の相続における注意点

- 遺言書を作成しておくと相続人と非嫡出子の相続トラブルを防ぎやすくなる
- 当事者同士での交渉でトラブルになりそうな場合は弁護士に依頼すべき
非嫡出子がいる相続について、どのような注意点があるかを教えてください。
非嫡出子がいる場合、遺言書を作成しておくと相続争いを防止しやすくなります。当事者同士で交渉をしてトラブルになりそうな場合は、早めに弁護士に依頼しましょう。
相続人の中に非嫡出子がいる場合、大きなトラブルになる可能性も
相続人の中に非嫡出子がいる場合、大きなトラブルになる可能性も考えられます。 嫡出子と非嫡出子の関係はそれぞれですが、仲が悪かったり疎遠だったりした場合は、相続をきっかけに顔を合わせることで、遺産をめぐってのトラブルになることがあるからです。遺言書を作成しておき遺産分割協議を不要とするのが良い
非嫡出子がいる相続においては、遺産分割協議を回避するために遺言書を作成しておくのがおすすめです。遺言書によって遺産分割の方法を指定しておかないと、相続人が遺産分割協議をして、自分たちで遺産分割の方法を決めなければなりません。
非嫡出子との仲が悪い場合は、遺産分割協議をしても同意が得られずに、遺産をめぐって争いになってしまう可能性があります。 被相続人が遺言書によって遺産分割の方法を指定しておけば、遺言書の内容が優先されるので、原則として遺産分割協議をする必要がなくなります。 遺言書によって遺産分割協議を回避すれば、非嫡出子と他の相続人による相続争いを防ぎやすくなるのです。当事者を通して交渉するとトラブルになりそうな場合には弁護士に依頼
当事者同士で交渉をするとトラブルになりそうな場合は、早めに弁護士に依頼することをおすすめします。遺言書がない場合は、相続人が遺産分割協議をして話し合いをし、どのように遺産を分割するかを決めなければなりません。 遺産分割協議は相続人のうち一人でも同意が欠けると成立しないので、感情的なことが原因で争いになってしまうと、解決が難しくなりがちです。
特に、非嫡出子と他の相続人との仲が悪い場合は、そもそもの感情的な対立を発端として、遺産分割をめぐって争いになってしまう可能性があります。 遺産分割をめぐって争いになった場合、当事者同士で交渉をしようとしても、お互いに相手に譲る気が起きないことから、交渉が難航しがちです。
相続問題に詳しい弁護士に交渉を依頼すると、専門的な法的知識をもとに的確な主張ができるので、相手が交渉に応じることが期待できます。 また、当事者にかわって第三者である弁護士が交渉をすることで、相手が感情的にならずに、冷静に交渉に応じる可能性が高くなります。まとめ
法律婚でない男女の間に生まれた子どもを非嫡出子といいます。 かつては、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の1/2でしたが、民法の改正によって、法定相続分は嫡出子と同じになりました。 相続人の中に非嫡出子がいる場合は、相続トラブルが生じやすいので、遺言書を作成して遺産分割協議を回避するなどの工夫が重要です。


- 死亡後の手続きは何から手をつけたらよいのかわからない
- 相続人の範囲や遺産がどのくらいあるのかわからない
- 手続きの時間が取れないため専門家に任せたい
- 喪失感で精神的に手続をする余裕がない
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.02.19相続放棄・限定承認空き家となる不動産を相続放棄する場合の注意点などについて解説
- 2025.02.19相続全般孫が相続人になる場合と注意点について解説
- 2025.01.20相続手続き代行非嫡出子の法定相続分は?相続の注意点を解説
- 2024.12.25相続全般車を相続する場合に必要な手続き・必要書類・税金の知識について解説!