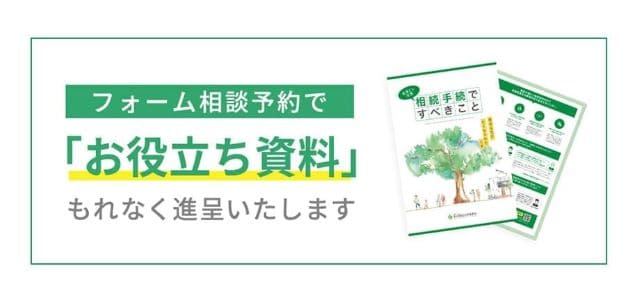目次
- 1.寄与分とは
- 1-1.法定相続分による相続では不公平が生じる
- 2.寄与分が認められるための要件
- 2-1.寄与をおこなったのが共同相続人であること
- 2-2.寄与行為が「特別の寄与」であるといえること
- 2-3.寄与行為と被相続人の財産が増加したことに因果関係があること
- 3.寄与行為の例
- 3-1.家事従事型
- 3-2.金銭等出資型
- 3-3.療養看護型
- 3-4.扶養型
- 4.寄与分の具体的な額の決定方法
- 4-1.寄与分は当事者の協議で決定する
- 4-2.当事者の協議が調わないときは寄与分を定める処分調停を申し立てる
- 5.寄与分の計算方法
- 5-1.相続財産から寄与分を控除
- 5-2.みなし相続財産を法定相続分で配分
- 5-3.控除した寄与分を加算
- 5-4.計算例
- 6.まとめ
1.寄与分とは
寄与分とは、相続財産が増えたことに貢献した相続人を、他の相続人よりも優遇する制度のことをいいます。
1-1.法定相続分による相続では不公平が生じる
被相続人が亡くなって相続が始まると、遺言が無ければ法定相続分にしたがって相続が開始します(民法第900条)。
例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続した場合には、妻が1/2・子がそれぞれ1/4ずつの法定相続分となります。
ただ、具体的な事情を考えれば、この割合で相続させるのはかえって不公平という場合もあるでしょう。
例えば、長男は同居して親の事業を助けて・老後の面倒まで見ていたけども、次男は自宅を購入するために親から多額の資金援助をうけているような場合を考えてみてください。
このような場合、長男と次男の相続分が同一であるのは、かえって不公平といえます。
このような相続の具体的な事情を考慮するための仕組みとして、特別受益という制度とともに民法第904条の2で寄与分が規定されています。
相続財産を増やすような結果があった場合には寄与分、相続財産を減らすような結果があった場合には特別受益という考え方で良いでしょう。
2.寄与分が認められるための要件
それでは、相続において寄与分が認められるためには、どのような要件が必要でしょうか。
2-1.寄与をおこなったのが共同相続人であること
まず、寄与を行ったのが法定相続人であることが必要です(民法第904条の2第1項)。
たとえば、内縁の妻や長男の妻が日常的な介護をしているようなケースがあります。
内縁の妻はそもそも相続人ではないので、寄与分は認められず、特別縁故者と認定された場合に相続財産を譲り受けることができるにとどまります(民法第958条の3)。
長男の妻も同様に相続人ではないので、長男の妻に寄与分が認められるわけではなく、また寄与をしていたわけではない長男の相続分に影響を与えるものではありません。
長男の妻などの親族については、特別寄与料の請求をすることができることになっていますが(民法第1050条)、これは寄与分とは異なる制度です。
2-2.寄与行為が「特別の寄与」であるといえること
次に、寄与分が認められるためには、寄与行為が「特別の寄与」であるといえることが必要です。
上記のように、寄与分は、被相続人の財産が増えることに貢献したことを評価するものです。
家業を手伝っていた・介護をしていたとしても、対価をもらっていたような場合には、被相続人の財産が増えることに貢献したとはいえません。
2-3.寄与行為と被相続人の財産が増加したことに因果関係があること
最後に、寄与行為と被相続人の財産増加に因果関係があることが必要です。
寄与行為があったとしても、それによって被相続人の財産は増えておらず、被相続人の財産が増えた理由は別にある場合には寄与行為を行った相続人に相続において特別な配慮をする必要がないといえるので、寄与分は認められないことになります。
3.寄与行為の例
寄与行為には次のような型があります
3-1.家事従事型
被相続人が事業をしているような場合に、これに一緒に従事をしているような場合です。
被相続人が農業をしていてこれに従事している、被相続人が飲食店をしていてこれに従事している、といった場合があります。
特に業種が限定されるわけではありません。
3-2.金銭等出資型
たとえば、親が住んでいる自宅を、体が不自由になっても利用できるようにリフォームする資金を子が出したような場合です。
3-3.療養看護型
被相続人に看護が必要となったような場合に、付き添い看護をすることで、ヘルパーさんを雇わなくて済んだ、といった場合が挙げられます。
特別な寄与といえるためには、看護に専従していることや、一定期間以上の継続性が必要とされる点に注意が必要です。
3-4.扶養型
被相続人に生活費を与えるなどして、扶養をしていた場合です。
ただし、民法が規定する扶養義務(民法第877条)の範囲で扶養をしている場合には、特別の受益とはいえないことが多いので注意が必要です。
4.寄与分の具体的な額の決定方法
では、具体的な寄与分はどのようにして決定するのでしょうか。
4-1.寄与分は当事者の協議で決定する
民法第904条の2第1項で、寄与分は当事者の協議で決定することが規定されています。
通常は遺産分割協議の中で寄与分がいくらになるのかの協議を行うことがほとんどです。
4-2.当事者の協議が調わないときは寄与分を定める処分調停を申し立てる
寄与分が当事者の協議で定まらない場合には、当事者の申し立てによって、家庭裁判所が寄与分を定める旨が規定されています。
この規定に応じて、寄与分を定める処分調停という手続きが、家庭裁判所で用意されています。
調停とは、裁判官1名と民間の相続問題に詳しい専門家2名からなる調停委員が、当事者の言い分を相互に聞きながら、調停案を提案し、当事者がこれに同意する形で紛争を解決する手続きです。
調停案に同意できない場合には、裁判所が寄与分を定めることになる審判手続きに移行することになっています。
5.寄与分の計算方法
では寄与分がある場合にはどのような計算をするのでしょうか。
5-1.相続財産から寄与分を控除
まず、相続財産の額から寄与分に相当する分を控除します。
この控除された相続財産のことを「みなし相続財産」といいます。
5-2.みなし相続財産を法定相続分で配分
次に、みなし相続財産を法定相続分で配分します。
配分された各人の相続分は「一応の相続分」と呼ばれます。
5-3.控除した寄与分を加算
最後に寄与分が認められる人に、最初に控除された寄与分を加算します。
5-4.計算例
具体的な計算例を以下の事例で確認しましょう。
まず、相続財産から寄与分を控除します。
4,000万円-1,000万円=3,000万円(みなし相続財産)
次に、みなし相続財産を法定相続分で配分します。
3,000万円
妻B(1/2)=1,500万円(一応の相続分)
子C(1/4)=750万円
子D(1/4)=750万円
最後に子Cに控除していた寄与分を加算します。
子C=750万円+1,000万円=1,750円
6.まとめ
このページでは、寄与分についてお伝えしました。
相続について具体的な事情を考慮するためのもので、特別受益と併せて把握をしておきましょう。
無料
遺産分割に関するよくある質問
遺産分割協議に関する当事務所の弁護士監修コラム


遺産分割協議をしたいのに相続人の1人が行方知れず…協議できる?