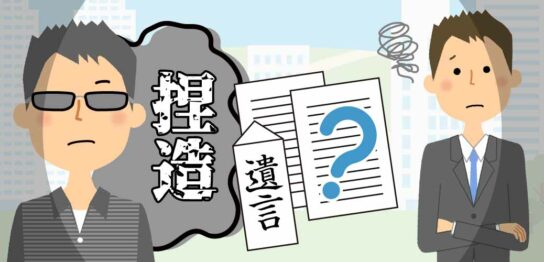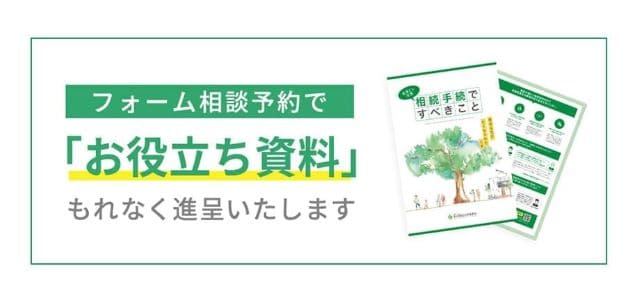- 遺言書の原本を破棄されると、遺言書の内容を確認できなくなる
- 相続人が遺言書を破棄した場合、相続欠格に該当する
- 遺言書のトラブルを防止するには、公正証書遺言を利用する方法がある
【Cross Talk 】遺言書を破る・燃やす・捨てるなどした場合はどうなる?
私が死んだ場合に備えて遺言書を作成しようと思うのですが、素行の悪い長男が遺言書を破棄したりしないか心配です。
相続人がわざと遺言書を破る・燃やす・捨てるなどして、遺言書の原本がなくなってしまうと、遺言書の内容を確認できなくなります。その相続人は相続欠格に該当するので、遺産を相続できなくなります。
遺言書を破ったり捨てたりした場合は、遺言書の効力に影響する場合があるんですね。遺言書のトラブルを防止する対処法についても教えてください!
被相続人が生前に遺言書を作成した場合、遺言書の内容によっては不満を感じる相続人がいる場合があります。 不満を感じた相続人によって、遺言書が棄損された場合、遺言書の内容を確認できず問題になります。 そこで今回は、相続人が遺言書を破る・燃やす・捨てるなどの破損した場合について解説いたします。
遺言書を破る・燃やす・捨てるなどして破棄した場合どうなるか?

- 遺言書の原本を破棄されると、遺言書の内容を確認できなくなる
- 相続人が遺言書を破棄した場合、相続欠格に該当する
内容に不満のある相続人が、私が作成した遺言書を捨ててしまいました。遺言書を破る・燃やす・捨てるなどされた場合、どうなるのでしょうか?
破る・燃やす・捨てるなどの行為によって、遺言書の原本がなくなってしまった場合は、遺言書の内容を確認できなくなってしまい、遺言書通りの相続ができなくなります。そのため、すぐに作成し直して、第三者に保管をゆだねましょう。また、遺言書をわざと破棄した相続人は相続欠格に該当し、遺産を相続できなくなります。
通常の自筆証書遺言書・秘密証書遺言書
破る・燃やす・捨てるなどの行為によって、通常の自筆証書遺言や秘密証書遺言がなくなってしまった場合、遺言書の内容を確認できなくなってしまいます。 自筆証書遺言を作成した場合、被相続人が自分で遺言書を管理することが多いでしょう。 もし破る・燃やす・捨てるなどによって遺言書がなくなってしまった場合は、遺言作成者がまだ生きていれば、作成しなおせば問題ないかもしれません。 しかし、自筆証書遺言書が破棄された後、被相続人が新しい遺言書を作成せずに死亡した場合は、遺言書の内容をだれも確認できない以上、相続人全員で遺産分割協議をして、誰がどの遺産を相続するかを決めなければなりません。秘密証書遺言の場合も同様です。
公正証書遺言書・自筆証書遺言書保管制度を利用している場合
公正証書遺言書は遺言書の原本が公証役場に保管されるので、遺言書を破る・燃やす・捨てるなどの方法で破棄される危険性がありません。また、一部の相続人による破棄を防ぐ制度として、自筆証書遺言書保管制度があります。 自筆証書遺言書保管制度とは、自筆証書遺言書を法務局が保管してくれる制度です。
従来、自筆証書遺言書は自分で保管場所を確保しなければならず、遺言書を相続人に破棄されるなどのリスクがありました。 保管制度を利用すれば、自筆証書遺言書の原本が法務局に保管されるので、公正証書の場合と小名仕様に、遺言書の破棄を防止できます。相続欠格
相続人が遺言書をわざと破る・燃やす・捨てるなどした場合、相続欠格に該当します。 相続欠格とは、相続人が一定の不正行為をした場合に、その相続人の相続権が失われる制度です。 相続欠格によって相続権を失った場合、その相続人は遺産を相続できなくなります。相続権がなくなるので、遺留分(最低限の遺産の取り分)も認められません。 相続欠格に該当する事由は民法に規定されており、その一つとして以下のものがあります(民法第891条5号)。
・相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したもの
被相続人が作成した遺言書について、相続人がわざと破る・燃やす・捨てるなどした場合は、一般に上記のうち破棄にあたるので、相続欠格に該当します。
例えば、被相続人である父親が自筆証書遺言書を作成したところ、自分にとって不利な内容が書いてあると知った長男が遺言書を燃やしてしまった場合、長男は相続欠格に該当します。
遺言書があることでトラブルになりそうな場合の対応方法

- 遺言書のトラブルを防止するには、公正証書遺言を利用する方法がある
- 自宅以外に遺言書を保管したり、遺言執行者に預けるなどの方法もある
私が作成した遺言書をめぐって、相続人の間で争いにならないか心配です。遺言書のトラブルを防止する対処法はありますか?
遺言書のトラブルを防止する対処法としては、公正証書遺言を利用したり、遺言執行者に預けるなどの方法がありますね。
公正証書遺言の利用
遺言書を破る・燃やす・捨てるなどのトラブルを防止する対応方法として、公正証書遺言を利用する方法があります。 公正証書遺言は遺言書が公証役場に保管されるので、相続人が遺言書を破ったり捨てたりすることを防止できます。また、原本が保管されることから、相続人によって遺言書の内容が書き換えられてしまう心配がないのもメリットです。 自筆証書遺言も保管制度はありますが、遺言書の内容が法的に有効かどうかまでは確認されないので、法的に無効な遺言書を保管してしまう可能性があります。 公正証書遺言であれば、遺言書を公正証書にする際に公証人が確認してくれるので、法的に無効な遺言書を作成するリスクが低くなります。
自宅以外で遺言書を保管
遺言書を破る・燃やす・捨てるなどの対策として、自宅以外で遺言書を保管するのも一つの方法です。 自宅で遺言書を保管する場合、配偶者や子どもなどが保管場所を把握しやすいので、破る・燃やす・捨てるなどのトラブルが起こりやすいのがデメリットです。 遺言書を自宅以外に保管すれば、相続人が簡単に遺言書を入手できなくなるので、遺言書をめぐるトラブルを防止しやすくなります。 自宅以外に遺言書を保管する方法として、以下のものがあります。- 銀行の貸金庫に預けておく
- 相続人ではない信頼できる方に預けておく
- 遺言書の作成を依頼した弁護士などの専門家に預けておく
遺言執行者をつけて預けておく
遺言書を破る・燃やす・捨てるなどのトラブルを防止するために、遺言執行者をつけて遺言書を預けておく方法があります。 遺言執行者とは、遺言書の内容をきちんと実現するために選任される方です。 例えば、被相続人が遺言書の内容として「長男に自宅を相続させる」とした場合、遺言執行者は相続登記をして、自宅の登記の名義を被相続人から長男に変更します。遺言執行者には様々な任務がありますが、遺言書をきちんと実現するためには、被相続人が作成した遺言書をきちんと保管することも重要です。 そこで、遺言書を破る・燃やす・捨てるなどのトラブルが生じないように、遺言執行者に遺言書を預けておくことができます。
まとめ
相続人が破る・燃やす・捨てるなどの行為によって遺言書を破棄した場合、遺言書の種類によっては、遺言書の内容を確認できなくなってしまいます。 相続人が遺言書を破棄した場合、相続欠格に該当するので、その相続人は遺産を相続できなくなります。 公正証書遺言は遺言書の原本が公証役場に保管されるので、相続人による破棄の心配がありません。 遺言書を破る・燃やす・捨てるなどのトラブルを防止するには、公正証書遺言を利用するのがおすすめです。


- 遺言書が無効にならないか不安がある
- 遺産相続のトラブルを未然に防ぎたい
- 独身なので、遺言の執行までお願いしたい
- 遺言書を正しく作成できるかに不安がある
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.01.20相続全般遺産分割がなかなかまとまらない場合に一部分割をすることは可能?
- 2025.01.20相続全般兄弟も未成年後見人になれる?弁護士が解説
- 2025.01.20遺言書作成・執行遺言書を破る・燃やす・捨てる!といった場合の遺言書の効力は?
- 2024.11.05遺言書作成・執行遺言書の種類別にどのような費用がかかるかを解説