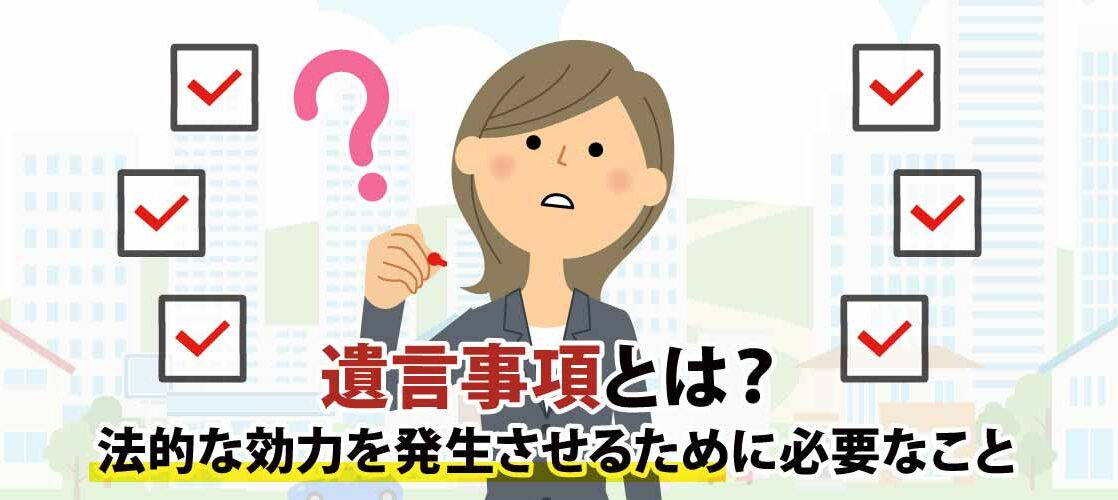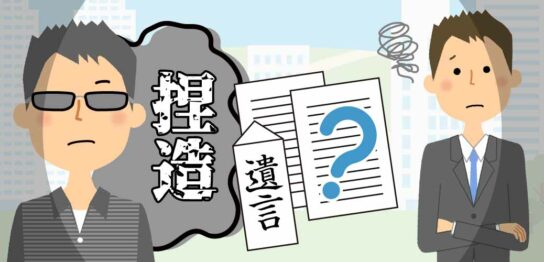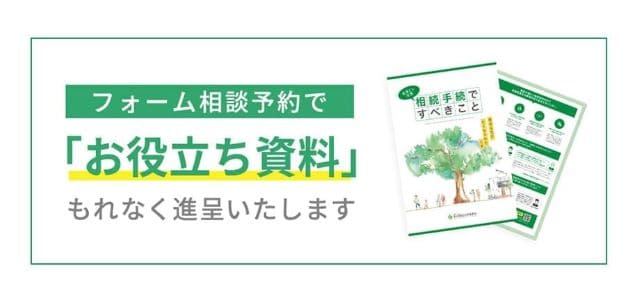- 遺言に記載すると法的な効力が発生するものを遺言事項という
- 遺言事項の種類は相続、遺産の処分、身分上の事柄、遺言の執行などがある
- 法的な効力を発生させるには遺言の方式を守ることが重要
【Cross Talk 】遺言に記載すると法的な効力が発生する事項と、そうでない事項がある
遺言書に記載したことは民法の法定相続よりも優先されると聞いたので、遺言書を作成したいのですが。
遺言書に記載したことの全てについて、法的な効果が発生するわけではありません。遺言書に記載した事項のうち、遺言事項と呼ばれるものが法的な効果を生じさせます。
遺言をする場合は遺言事項が重要になるのですね。遺言事項にはどんな種類があるかも知りたいです!
遺言書を作成した場合、民法が規定する法定相続よりも遺言書の内容が基本的に優先されます。もっとも、遺言書に記載した全ての事柄が法的な効力を有するわけではありません。 遺言書に記載することで法的な効力が発生する事項を、遺言事項といいます。遺言事項は法律に厳密に規定されているので、どんな事柄が遺言事項に該当するかは重要です。 そこで今回は、遺言事項の概要や種類、遺言で法的な効力を発生させるために重要なことなどを解説します。
遺言書に書けばなんでも法的効果が発生するわけではない

- 遺言書に記載したことが全て法的な効果を持つわけではない
- 遺言書に記載することで法的な効力が発生するものを遺言事項という
遺言書を作成するには遺言事項が重要と聞きました。遺言事項とは何ですか?
遺言書に記載することで法的な効力を発生するものを、遺言事項といいます。遺言事項は民法などの法律に規定されています。
遺言事項とは
遺言事項とは、遺言書に記載することで法的な効力が発生する事項のことです。遺言書には様々なことを記載できますが、記載したことがなんでも法的な効力を持ってしまっては、不当な相続や混乱につながります。そこで、あらかじめ法律で規定された事項のみが、遺言書に記載することで法的な効力を発生するように定められています。主な遺言事項の種類は相続、遺産の処分、身分上の事柄、遺言の執行などについてです。
遺言に法的な効力を発生させるために必要なこと
遺言に法的な効力を発生させるためには、法律に定められた遺言の方式を遵守することが重要です。遺言の方式は厳格に規定されており、方式を満たしていない場合は遺言書が無効になるからです。 たとえば、民法が規定する遺言の一種である自筆証書遺言の場合、必ず遺言者本人が全文、日付及び氏名を自書する(遺言者が自分で書く)必要があります。代筆してもらった場合は遺言書としての効力が生じません。遺言事項ではないことを遺言に書く意味はないのか?
遺言事項ではないことを遺言書に記載しても法的な効果はありませんが、全く意味がないというわけではありません。法定遺言事項以外の内容として、遺言書に付言事項(ふげんじこう)を記載することは一般に行われています。付言事項の例としては遺言した経緯や、家族への感謝などがあります。
相続では不平不満が出る場合も少なくありませんが、付言事項として遺言をした経緯を説明したり、家族への感謝の気持ちを述べたりすれば、相続についての家族間の争いを避けることにつながる可能性があります。相続に関する遺言事項

- 相続に関する遺言事項は推定相続人の廃除、相続分の指定、遺産分割方法の指定などがある
- 相続できるか、何をどのくらい相続するかなどに関わってくる
相続に関連する遺言事項はどんなものがありますか?
相続に関する遺言事項には推定相続人の廃除、相続分の指定、遺産分割方法の指定などがあります。相続ができるか、何をどのくらい相続するかなどです。
推定相続人の廃除・その取消し
相続人の廃除とは、被相続人の意思に基づいて、推定相続人(相続人になるであろう者)の相続人としての資格を失わせ、遺産を相続させないようにする制度です。遺言書で推定相続人を廃除する意思表示がされた場合、遺言について事務を行う遺言執行者が家庭裁判所に対して相続人廃除の請求をします。推定相続人の廃除は相当な理由がなければ認められません。遺言者が推定相続人から虐待を受けた、重大な侮辱を受けた、その他の著しい非行があったときに認められます。また、生前に推定相続人の廃除をしていた場合、遺言による廃除の取消しもできます。
相続分の指定・指定の委託
相続分の指定とは、遺言により、民法が定める法定相続分とは異なる割合で相続分を定めることです。たとえば夫が亡くなって相続人が妻と子の計2人の場合、法定相続分は妻と子が1/2ずつですが、相続分の指定によって妻が2/3で子が1/3にすることができます。 また、相続分の指定を第三者に委託することもできます。弁護士に相続分の割合を決めてもらうなどです。遺産分割方法の指定・指定の委託
遺産分割方法の指定とは、遺産をどのように分割するかを指定するものです。どの財産をどの相続人に相続させるかを指定するのが典型例です。 たとえば相続財産が土地と預貯金の場合に、長男に土地を相続させて次男に預貯金を相続させるなどです。また、遺産分割方法を指定することを第三者に委託することもできます。遺産分割の禁止
遺産分割の禁止とは、文字通りに遺産の分割を禁止することです。相続の開始から5年以内の範囲で禁止する期間を定めることができます。 相続人同士が揉めることが予想される場合に遺産分割をひとまず禁止する、土地を分割すると家業の継続が困難になる場合に分割を禁止するなどです。遺贈の減殺方法の指定
一定の法定相続人には相続財産の一定割合を取得できることが法律上保証されており、この保証されている一定割合を遺留分といいます。遺留分を侵害された者は、侵害された額に相当する金銭の支払いを、遺贈を受けた人や遺産を多く取得した相続人に対して請求する(減殺する)ことができます。遺贈が複数ある場合、それぞれの価格の割合に応じて減殺するのが原則ですが、遺言によって減殺方法を指定することができます。たとえば100万円の遺贈と200万円の遺贈がある場合に、まず100万円の遺贈から減殺するなどです。
遺産の処分に関する遺言事項

- 遺産の処分に関する遺言事項は遺贈、財団法人の設立、信託の設定などがある
- 遺産をどう処分するか、どう活用するかなどに関わってくる
遺産の処分に関する遺言事項はどんなものがありますか?
遺産の処分に関する遺言事項としては遺贈、財団法人の設立、信託の設定などがあります。遺産をどう処分するか、どう活用するかなどです。
遺贈
遺贈とは、遺言によって遺言者の財産を他者に無償で譲ることです。入院でお世話になった看護師に自分の財産の一部を譲るなどです。相続は遺言をしなくても発生しますが、遺贈は遺言によらなければ発生しません。財団法人の設立
遺言によって一般財団法人を設立することができます。一般財団法人は財産に法人格を与えている組織のことで、財産の集まりを意味します。 財産の運用が主な業務ですが、公益性の有無や活動目的を問わず、一定の財産があれば基本的に誰でも設立できます。非営利型の一般財団法人の場合は、非営利事業が非課税になります。信託の設定
遺言によって信託の設定ができます。信頼できる個人または法人に対して、指定する財産を指定の目的に従って管理・給付・処分などをするように遺言で依頼します。 たとえば、軽度の認知症の妻の生活を保障するために、長男に対して信託財産の中から相当な生活費を手渡しするように求めるなどです。身分上の遺言事項

- 身分上の遺言事項として認知、未成年後見人や未成年後見監督人の指定がある
- 遺言で指定するだけでなく、認知などは事前に周知することも重要
身分上の遺言事項にはどんなものがありますか?
身分上の遺言事項としては認知、未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定などがあります。認知などは他者への影響も大きいので、必要に応じて事前に周知するなどの工夫も大切です。
認知
認知とは、法律上の婚姻関係によらずに出生した子を自分の子であると認めることです。認知を受けた子は、相続について権利を獲得します。 遺言によって子を認知することは、他の相続人にとっては自分の相続財産が減少することにつながるため、相続争いのトラブルの原因になる可能性があります。トラブルの防止には遺言で認知するだけでなく、事前に相続人に周知しておくなどの工夫も重要です。未成年後見人の指定
未成年後見人とは、未成年の子の親権者がいなくなった場合(または親権者が管理権を有しない場合)にその未成年の法定代理人となる者です。未成年後見人は財産の調査および財産目録の作成や、財産の現状についての家庭裁判所への報告などを行います。 管理権を有しない場合を除いて、未成年後見人は遺言によって指定できます。未成年者、破産者、行方不明者などの欠格事由に該当する場合は未成年後見人になることはできません。未成年後見監督人の指定
未成年後見監督人は未成年後見人の事務を監督する者です。未成年後見人を指定できる者は、遺言で未成年後見監督人を指名することも可能です。未成年後見監督人の主な事務は、未成年後見人の事務を家庭裁判所への報告すること、未成年後見人に対して財産目録の提出を請求すること、独自に事務や財産の状況を調査することなどです。
遺言の執行に関する遺言事項

- 遺言執行者の指定は遺言事項である
- 遺言執行者の指定を第三者に委託することもできる
その他の遺言事項はありますか?
遺言の内容を実現するために様々な手続を行う者を、遺言執行者といいます。遺言執行者を誰にするかは遺言者が指定できますが、これも遺言事項の一種です。
未成年者および破産者以外は誰でも遺言執行者になれますが、相続を問題なく完了させるには信頼のおける人物を遺言執行者に選ぶことが重要です。弁護士などの専門家に依頼する方法もあります。
遺言執行者の指定は遺言事項であり、遺言者は誰を遺言執行者にするかを指定することができます。また、顧問弁護士に遺言執行者を選んでもらうなど、遺言執行者の指定を第三者に委託することも可能です。まとめ
遺言に記載することで法的な効力が発生する事柄を遺言事項といいます。遺言事項は民法などの法律に規定されており、遺言事項の種類として相続、遺産の処分、身分上の事柄、遺言の執行などがあります。 遺言書の方式を満たすこととあわせて、必要な遺言事項を漏れなく記載することも、自身の意思を遺すためにとても重要なことです。方式を満たした遺言書に適切な遺言事項を記載して、相続に備えましょう。「自分の意思をどう遺言書に書けばよいかわからない」「自分の書いた遺言書は本当に適法なのだろうか」等の疑問がある場合や、遺言書についての悩み、不安がある場合には、弁護士に相談するのが良いでしょう。


- 遺言書が無効にならないか不安がある
- 遺産相続のトラブルを未然に防ぎたい
- 独身なので、遺言の執行までお願いしたい
- 遺言書を正しく作成できるかに不安がある
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2024.09.17相続手続き代行相続したときに必要な戸籍謄本の取り方・見方・提出先について解説!
- 2024.08.29遺産分割協議葬儀費用や香典返しはだれが払う?遺産分割の対象にできる?
- 2024.08.28遺産分割協議遺産分割の弁護士費用はどれくらいかかるの?費用を抑える方法は?
- 2024.08.28相続税申告・対策弔慰金は相続税ではどのように評価するか解説