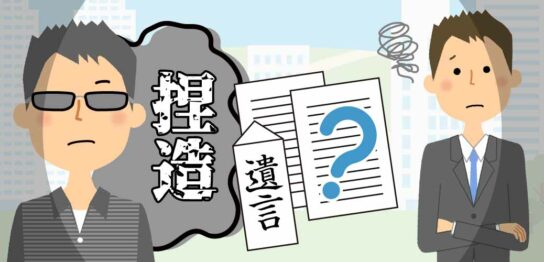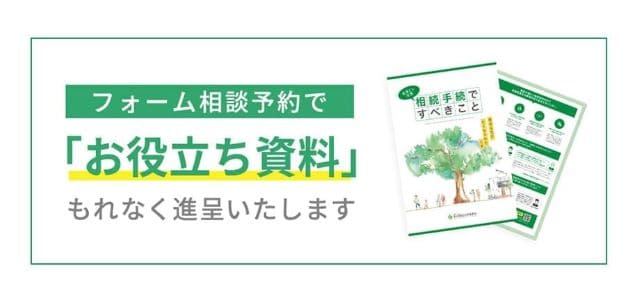- 遺言無効確認とは
- 遺言の内容に反する遺産分割
- 遺留分侵害額請求
【Cross Talk 】遺言の内容に反対したい
先日父が亡くなり、母・長男である兄・長女である私が相続をしました。父は遺言を残しており、結婚をして家を出た私には一切相続させてもらえませんでした。父は晩年は認知症の症状が出ていて、遺言をできる状態じゃなかったはずです。この遺言に反対したいのですが何か方法はありませんか?
遺言無効確認をしたり、相続人全員が遺言の内容に反対である場合には全員で遺産分割をします。遺言は有効であるとして遺留分侵害額請求をすることも検討しましょう。
そんなに方法があるんですね。詳しく相談に乗って下さい。
遺言があった場合に相続人の中には著しく不利な内容になることがあります。このような場合には遺言の内容に反対したいと考えるのは当然なのですが、その場合にはどのような主張の仕方があるのでしょうか。遺言無効確認・遺言の内容とは違う遺産分割をする、という方法がありますが、遺言は有効であっても遺留分侵害額請求をすることも可能です。
遺言無効確認の方法

- 遺言の内容が無効であると主張して反対する
- 遺言無効確認の手続き
そもそも認知症があって本人が遺言ができる状況じゃなかったと思うんです。
そのような場合には遺言無効確認を検討します。最終的には遺言無効確認の訴訟を起こすことになります。
遺言の内容に反対する方法として一つは遺言無効確認をすることが挙げられます。
遺言が無効となる理由
遺言は、民法の形式に従ってなされてなければならず、また遺言をするときに遺言能力がなければすることができません。 たとえば、自筆証書遺言が残されていた場合に、日付が抜けていた、遺産目録以外のところで自署していないところがあるなど、民法が定める様式に従っていない場合には無効になります。遺言能力とは、自分の遺言によってどのような法律関係になるのか判断することができる能力をいい、認知症などが原因で判断能力が衰えると、遺言能力がないと扱われることがあります。 自筆証書遺言を意味も分からず書かされた・偽造されたような場合がよくあるパターンなのですが、公正証書遺言をする場合でも公証人とのやりとりにあたって頷いていただけで遺言能力があると公証人が判断してしまい遺言書が作成された場合でも、後に遺言能力がなく無効であると判断されたケースもあります。
検認があったからといって遺言が有効になるわけではない
自筆証書遺言や秘密証書遺言がされた場合には、家庭裁判所で検認という手続きを経ることになっています。 検認では、遺言書がどのような形状をしているか、どのような内容が記載されているかを、相続人などの関係者全員の立ち会いのもと家庭裁判所において確認をします。 検認は、以後の偽造や変造を防ぐためにおこなわれるものであり、もし記載によって遺言が無効であるような場合にも、そのような記載であったと確定するために行います。 そのため,検認によって、遺言を有効にするものではありません。遺言は無効であると交渉する
遺言無効確認は、他の相続人や受遺者に対して、その遺言は無効であると主張して、法定相続分による相続をするように主張することになります。 遺言は無効であると主張する場合には、遺言で有利な扱いをされている人に遺言の無効を主張しましょう。遺言無効確認の訴えを起こす
遺言の形式が明らかに法律の要件を満たしていない限り、相手に主張をしただけで遺言は無効であると認めることは考えづらいです。 このような場合には遺言無効確認の訴えを起こします。 形式的には相続に関する争いについては、調停を先に行なってから訴訟を行うのですが、遺言が有効か無効かで当事者が対立しているような場合に、妥協策を検討する調停で解決することは望めません。 ですので、実務上調停を経ず遺言無効確認の訴えを行う場合もあります。 訴訟で遺言は無効であるとする旨の判決が出ると、その遺言は存在しないものとして相続の手続きを行うことになります。相続人全員が遺言に反対の場合

- 相続人全員が遺言の内容に反対の場合にはあらためて合意の上遺産分割を行うことができる
- 受遺者がいる場合には受遺者にも合意をとる
実は父はいくつか遺言を遺していたようで、その一つ前の遺言は兄も私も、遺言で遺産をもらう兄の奥さんも反対のものでした。もし最新の遺言が無効になった場合でも、その遺言が有効となって全員が望まない相続になりませんか?
そのような事情があるのですね。もし遺言の内容に全員が反対している場合には、全員の合意であらためて遺産分割をすることができます。
もし遺言があったとして、遺言の内容に全員が反対している場合でも遺言が絶対的に有効となると、相続人に酷な結果を強いることになります。 そのため、遺言の内容に全員が反対している場合には、全員の合意のうえで遺言の内容と異なる遺産分割をすることが可能です。 基本的には相続人全員の合意ですが、遺言で遺贈がされている場合には、受遺者にも合意を得る必要があります。
遺留分侵害額請求

- 遺言が有効な場合でも遺留分侵害額請求をする
- 遺留分侵害額請求は1年で消滅時効にかかるため内容証明だけでも出しておく
いろいろ調べてみたのですが、どうも遺言は有効なようです。この相続では私は何らの主張もできないのでしょうか。
いいえ、遺言は有効でも遺留分を侵害されている場合には、遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺言は有効で他の相続人が遺言のままの相続をする場合でも、その人の遺留分が侵害されている際は、遺留分侵害額請求をすることを検討しましょう。 遺留分侵害額請求とは、遺留分が侵害されている場合に、遺留分に相当する金銭を受け取ることを請求するものです。
民法1042条は、兄弟姉妹以外の相続人に遺留分という相続において最低限主張できる取り分を保障しています。 そして、遺留分の侵害をされた場合に、遺留分に相当する金銭を請求できます(民法1046条)。 遺言に反対できなくても、遺留分の請求をすることは別途可能です。 このときに注意が必要なのは、遺留分侵害額請求に時効があることです。 遺留分侵害額請求は、1年で時効にかかることになっています(民法1048条)。 遺言無効確認の訴えをしていると、解決までに1年以上かかることがあります。 そのため、遺留分が時効にかからないように、1年までの間に内容証明を送っておきます。 内容証明を送っておけば時効にはかかりませんので、遺言無効確認の訴えで負けた後でも請求が可能となります。
まとめ
このページでは、遺言に反対の場合の解決方法についてお伝えしてきました。 遺言が無効であるから反対であるという場合には遺言無効確認を、遺言の内容に全員が反対であるという場合にはあらためて遺産分割を行います。 遺言に反対でも遺言が有効な場合にはそのとおりに遺産が承継されますが、遺留分侵害額請求は別途可能ですので、時効に気をつけつつ請求をしましょう。 詳しく気になる方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。


- 遺言書が無効にならないか不安がある
- 遺産相続のトラブルを未然に防ぎたい
- 独身なので、遺言の執行までお願いしたい
- 遺言書を正しく作成できるかに不安がある
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2024.05.23相続全般相続法が改正された!いつから?今までと何が変わった?
- 2024.05.23相続全般相続人代表者指定届とは?その効力は?書き方も併せて解説
- 2024.03.22相続放棄・限定承認遺留分放棄とは?相続放棄との違いやメリット、撤回の可否を解説!
- 2023.11.06相続全般「死んだら財産をあげる」相続における口約束はトラブルのもと!事例をもとに解決方法を解説