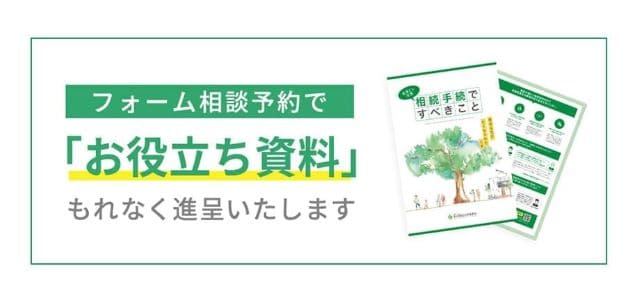はじめに
親の介護や家業を長年支えてきたにもかかわらず、いざ相続の場面で思ったより取り分が少ない…そんな不満や疑問を抱えていませんか?
または、「あなたの取り分は多すぎる」と他の相続人から主張され、どう対応すべきか悩んでいる方もいるかもしれません。
本記事では、相続時によく争点となる「寄与分」と「遺留分」の関係や制度の仕組み、よくあるトラブルとその解決策についてわかりやすく解説します。
寄与分と遺留分の関係
遺留分の金額は法定相続分によって決まります。
そのため、寄与分が認められる場合でも遺留分の金額は変化しません。
ただし、寄与分が認められる場合は、各相続人が相続する金額が変わってきます。
寄与分と遺留分のせいどについて詳しく解説します。
寄与分とは
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に関して特別な貢献をした相続人がいる場合に、貢献の度合いに応じて相続分を増額できる制度です。
例えば、長男が被相続人の介護をしたことで介護士に介護を依頼する費用を節約できた場合には、「財産の維持」が認められる可能性があります。
また、次男が無償で被相続人の家業を手伝ったことで、被相続人の収入が増加した場合は、「財産の増加」と判断される可能性ががあります。
寄与分が認められる場合は、通常の相続分よりも多く遺産を相続させることが可能です。
遺留分とは
遺留分とは、法律によって認められている「遺産の最低限の取り分」のことです。 被相続人に近い血縁関係にある親族(配偶者や子ども)は、被相続人が亡くなった場合に遺産を相続するのが一般的です。 しかし、被相続人が残した遺言書に「愛人にすべての遺産を相続させる」など書かれている場合、親族が十分に遺産を相続できなくなる場合もあります。 そこで、被相続人に近い親族の遺産に対する利益を保護する制度が遺留分です。 遺留分が認められる法定相続人は、被相続人の配偶者・子(代襲相続の場合は孫)・父母(代襲相続の場合は祖父母)です。 被相続人の兄弟姉妹も法定相続人になりますが、遺留分は認められていません。 遺留分を侵害された場合は、遺留分を侵害した相手に対して、遺留分に相当する金銭を支払うように請求することができます。 これを遺留分侵害額請求といいます。
特別寄与料とは
特別寄与料とは、一定の範囲の親族が被相続人に対して特別な寄与をした場合に、寄与の度合いに応じて請求できる金銭のことです。
寄与分は相続人のみに認められる制度なので、相続人以外の方が寄与をしたとしても、寄与分は認められません。
例えば、被相続人の長男の妻が被相続人の介護をしたとしても、長男の妻に対する寄与分は認められないのです。
特別な寄与をしたのに相続人でなければ寄与が認められないとなると、不公平感が生まれてしまいます。
そこで、相続人以外の一定の親族(配偶者・6親等内の血族・3親等内の姻族)が特別な寄与をした場合に、寄与の度合いに応じて金銭を請求できるようにしたのが、特別寄与料です
寄与分・遺留分の争いの解決方法
寄与分について相続人の間でトラブルになることがあります。
注意点と解決方法について解説します。
寄与分を高額に考慮することは許される?
法律上、寄与分の上限金額について規定されていません。
そのため、寄与分が高額に設定されることがあります。
ほかの相続人が認めるのであれば、高額の寄与分を渡すことも法的に可能です。
ただし、調停や訴訟など、裁判所の手続きによって寄与分を算定する場合は、ほかの相続人の遺留分が侵害されないように配慮される場合があります。
高額の寄与分が認められた場合,遺留分侵害額請求はできるのか
ほかの相続人に寄与分が認められたことで、自分の相続分が遺留分を下回ったとしても、寄与分に対して遺留分侵害額請求をすることはできません。
遺留分侵害額請求の対象になるのは、遺留分を侵害するような遺贈や贈与などで、寄与分は含まれていないからです。
寄与分でトラブルになりそうな場合は弁護士に相談
寄与分について相続争いが発生しそうな場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
寄与分が認められると、ほかの相続人にとっては自分の相続分が減ってしまうので、取り分を認めようとしない可能性があります。
寄与分について争いが発生すると、遺産をどのように分割するかを決めることができず、相続手続きがスムーズに進まなくなってしまいます。
争いが激しくなる前に弁護士に相談・依頼すると、弁護士が適切な主張や証拠に基づいてほかの相続人と交渉してくれます。
弁護士に依頼することで、争いになるのを防ぎしつつ適切な金額の寄与分を獲得しやすくなるでしょう。
さいごに
遺留分の金額は法定相続分によって決まるので、ほかの相続人に寄与分が認められる場合でも、相続人の遺留分の金額は変わりません。
しかし、寄与分が認められてしまうと、ほかの相続人が相続できる金額に影響があるので、寄与分をめぐってトラブルになる可能性があります。
寄与分に関してトラブルになりそうな場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

- 相続対策は何から手をつけたらよいのかわからない
- 相続について相談できる相手がいない
- 相続人同士で揉めないようにスムーズに手続きしたい
- 相続の手続きを行う時間がない
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.10.29相続放棄・限定承認空き家を相続する際の話し合いのコツを確認
- 2025.10.29相続全般親が経営していた賃貸マンション・アパートを相続したときの手続きなど解説
- 2025.10.20相続手続き代行【タイプ別】遺産相続における寄与分の計算方法をわかりやすく解説
- 2025.09.22相続全般相続の寄与分と遺留分の関係を解説!トラブル防止のポイントも紹介