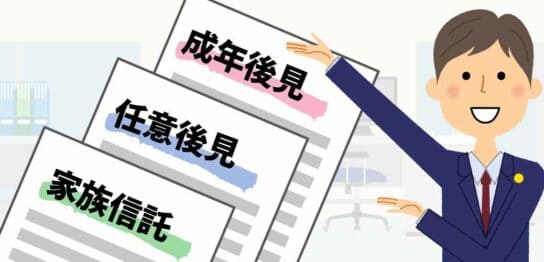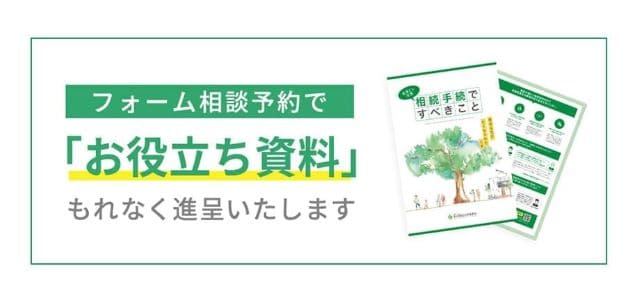- 任意後見人を選任するには、公正証書にて任意後見契約を締結する
- 任意後見監督人の選任が確定すると、任意後見が開始される
- 任意後見人を選任する主な費用は、公正証書を作成する費用や、任意後見人・任意後見監督人の報酬など
【Cross Talk 】任意後見制度を利用するには、どんな費用がかかるの?
将来、判断能力が低下した場合に備えて、任意後見制度を検討しているのですが、色々と費用がかかると聞きました。どのような費用が発生しますか?
任意後見人を選任して任意後見契約を締結するために、公正証書の作成費用がかかります。任意後見の職務を行う任意後見人や、それを監督する任意後見監督人などの報酬も考慮しましょう。
色々な費用があるんですね。任意後見人を選任する流れについても教えてください!
認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、財産管理や介護サービスの契約締結などをしてくれる、任意後見人を選任する制度(任意後見制度)を利用する方法があります。 任意後見制度を利用するためには、任意後見契約を締結する必要がありますが、必ず公正証書を作成するため、作成費用がかかります。その他、任意後見人などに支払う報酬なども考慮する必要があります。 そこで今回は、任意後見人を選任する場合の費用について解説いたします。
任意後見制度とは

- 任意後見制度は成年後見制度の一つ
- 任意後見制度では後見人をあらかじめ自分で決めることができる
任意後見制度というものがあることは知っていますが、具体的にはどんな制度なのですか。
高齢や病気等の影響で判断能力が不十分になった方を保護するために、本人に代わって後見人が財産管理等を行う制度を成年後見といいます。任意後見制度は、成年後見制度の一種で、判断能力がある間に契約によって後見人をあらかじめ決めておく制度です。
任意後見制度の概要
認知症や精神疾患等の影響で判断能力が低下し、自身の財産を管理したり、新たに契約を結んだりすることが難しくなる場合があります。
民法は、このような判断能力が低下した型を保護するために、成年後見制度を規定しています。
成年後見人は、本人の代理人として、本人の財産を管理したり、契約を結んだりすることができます。
成年後見制度には、大きく分けて法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった場合に、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長の申立てにより、家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。
成年後見人の人選は家庭裁判所に委ねられており、本人や申立人が自由に選ぶことはできません。また、後見人の権限の範囲は、法律で定められています。
これに対し、任意後見制度は、本人の判断能力が十分である間に、あらかじめ後見人となる方や、その後見人に委任する事務の内容を契約で定めておき、将来判断能力が不十分になったときに後見人が委任を受けた事務を行うという制度です。
判断能力がある間に、自身で将来後見人になってもらう方を選べること、後見人に委任する事務の内容を決めることができることから、任意後見制度は法定後見制度よりも本人の意思を尊重した柔軟な制度であると言えます。
任意後見人を選任するための手続き

- 任意後見人を選任するには、まず公正証書にて任意後見契約を締結する
- 家庭裁判所が任意後見監督人を選任して確定すると、任意後見が開始される
私の判断能力が低下した場合に備えて、任意後見人を選任しようと思うのですが、どのような手続きが必要ですか?
任意後見人を選任するには、公正証書にして任意後見契約を締結します。その後、判断能力が低下した場合は、家庭裁判所に申立てをして任意後見監督人を選任してもらい、任意後見を開始します。
任意後見契約を結ぶ
自分の判断能力が将来に低下した場合に備えて、財産管理や介護サービスの契約など、必要な事務処理をしてくれる方を選んでおく手続きを、任意後見制度といいます。 任意後見制度を利用するかどうかは、名称の通りに本人の任意であり、自由です。
任意後見制度を利用するか、誰に任意後見人になってもらうか、どのような事務処理を依頼するかなどは、基本的に本人が決めます。 任意後見制度を利用するには、任意後見契約を締結しなければなりません。任意後見契約を依頼する本人を委任者といい、契約に基づいて事務処理を引き受ける方を任意後見人といいます。
任意後見契約を締結するには、公正証書という書類を作成しなければなりません。公正証書を作成するには、公証役場に所属する公証人に依頼して作成してもらいます。
裁判所に申立てを行う
任意後見契約を締結した後に、認知症などによって本人の判断能力が低下した場合は、管轄の裁判所(本人の住所地を管轄する家庭裁判所)に任意後見監督人の選任の申立てをして、任意後見を開始します。 任意後見監督人とは、任意後見人が契約内容に従ってきちんと仕事をしているかを、監督する立場の人です。
任意後見契約の公正証書には、本人が希望する任意後見監督人の候補者を記載できますが、必ずその候補者が選任されるとは限りません。 本人を適切に保護する観点から、家庭裁判所がふさわしいと考える人物が選ばれます。弁護士や司法書士などの法律の専門家が、任意後見監督人として選任されるのが一般的です。
任意後見監督人を選んで監督させることで、任意後見人が本人の利益に反するような行為をすることを防止し、本人の保護を図ります。
後見開始
任意後見監督人を選任する審判が確定すると、任意後見契約の内容に基づいて任意後見人が職務を行います。
任意後見人がどのような職務を行うかは、任意後見契約の内容によります。一般的な職務は以下の通りです。
- 本人の財産管理に関する法律行為
- 本人の療養看護に関する法律行為・事務(介護サービスの契約を締結するなど)
- 上記の法律行為に関する登記申請など
本人または任意後見人が死亡した場合などは、任意後見契約は終了します。また、任意後見人が不正行為をするなど、任務に適しない事由がある場合は、任意後見人の解任請求をすることができます。
任意後見監督人が選任された後に、任意後見契約を解除したい場合は、正当な事由があり家庭裁判所の許可を得た場合に限り、契約の解除が可能です。
任意後見人を選任するための費用

- 任意後見人を選任するには、任意後見契約書を公正証書にするための費用がかかる
- 任意後見人や任意後見監督人に、報酬として支払う費用を考慮する
任意後見人を選任して事務処理をしてもらおうと思うのですが、どのような費用がかかりますか?
まず、任意後見契約を公正証書にするための費用がかかります。次に、任意後見人や任意後見監督人に支払う報酬も考慮しておきましょう。
任意後見契約を結ぶための費用
任意後見契約を結ぶには、公証役場で手続きをして、任意後見契約公正証書を作成してもらう必要があり、そのための費用がかかります。
公証人に任意後見契約書を作成してもらうための主な費用の目安は、以下の通りです。
- 公正証書を作成する手数料:任意後見契約1件につき1万1,000円
- 法務局に納める印紙代:2,600円
- 任意後見契約の登記嘱託料:1,400円
- 書留郵便料:540円程度
証書の枚数:法務省令で定める枚数の計算方法により、証書の枚数が4枚を超える場合は、1枚超えるごとに250円 任意後見契約公正証書を作成するには、少なくとも1万5,000円程度の費用を見ておく必要があるということです。
病気などで公証役場に出向くことができない場合、公証人に自宅や病院に出張してもらい、公正証書を作成する方法があります。 その場合は、公正証書を作成する手数料が5割増となる(任意後見契約1件につき1万6,500円)ほか、日当と現場までの交通費が必要です。
後見人に支払う費用
任意後見人に支払う報酬については、任意後見契約の内容として定めておくのが一般的です。 親族が任意後見人になる場合は、報酬を受け取らないこともありますが、第三者の専門家(弁護士や司法書士など)が任意後見人になる場合は、一般に報酬を支払います。
任意後見人に対する報酬額の基準は、法律で決まっているわけではありません。あくまで参考ですが、任意後見人の報酬額(専門職の場合)の目安は以下の通りです。
- 管理財産額が1,000万円以下の場合、基本報酬(通常の後見事務を行った場合の報酬)は月額2万円程度
- 管理財産額が1,000万円超〜5,000万円以下の場合、基本報酬は月額3万〜4万円程度
- 管理財産額が5,000万円を超える場合、基本報酬は月額5〜6万円程度
任意後見人が後見事務などを行う際に、身上監護などで特別困難な事情があった場合には、上記の基本報酬額とは別に、基本報酬額の50%の範囲内で、追加報酬が付加される場合があります。 なお、任意後見契約で報酬について定めていない場合は、家庭裁判所に申立てをして、審判によって報酬額を決めることができます。
後見監督人に支払う費用
任意後見監督人については、任意後見契約書で報酬について規定する必要はありません。任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が審判によって決定するからです。
任意後見監督人が、通常の後見監督事務を行った場合の基本報酬の目安は、以下の通りです。
- 管理財産額が5,000万円以下の場合、基本報酬は月額1万円~2万円程度
- 管理財産額が5,000万円を超える場合、基本報酬は月額2万5,000円~3万円程度
任意後見契約とセットで結んでおくとよい契約

- 後見開始前のサポートを希望するなら見守り契約、任意代理契約を結ぶ
- 死亡後のサポートが必要な場合は死後事務委任契約を結ぶ
任意後見契約を結んでおけば、将来の不安はありませんか?ほかに必要な契約があれば教えてください。
後見開始前から将来後見人となる方に何らかのサポートをしてほしい場合は、見守り契約や任意代理契約を結ぶことをお勧めします。また、死亡後の事務処理を依頼したい場合には、死後事務委任契約を結ぶ必要があります。
見守り契約
任意後見は、本人の判断能力が不十分になった後、本人、任意後見受任者等の申立てによって家庭裁判所が任意後見監督人選任の審判をし、その審判が確定したときに開始します。いったん開始した任意後見は、本人または後見人の死亡等、委任の終了事由がない限り続きます。
そうすると、任意後見契約を結んでから後見が開始するまでの間と本人が死亡した後については、任意後見契約の効力が及ばないということになります。
これらの任意後見契約の効力が及ばない期間にも、任意後見受任者(任意後見人)から何らかのサポートを受けたい場合、任意後見契約とセットで結んでおくとよい契約があります。
まず、任意後見契約とセットで見守り契約を結ぶ方法があります。
見守り契約とは、任意後見受任者等が、本人と定期的に連絡を取ったり、面談をしたりするなどして、本人の心身の状態や生活状況を確認していくというものです。
本人の判断能力が不十分になった場合に速やかに任意後見監督人の申立てをするには、任意後見受任者等の申立権者が、継続的に本人の判断能力を把握している必要があります。
本人がご家族と同居されていれば、ご家族が本人の判断能力の低下に気付き、任意後見受任者に連絡することもありますが、本人が身寄りのない方の場合、本人の判断能力が低下したことが任意後見受任者に伝わらず、任意後見監督人選任の申立てが遅れることがありえます。
そのような事態を防ぐには、見守り契約を結んで、定期的に任意後見受任者等が本人に接触して、本人の状態を確認することが有効なのです。
任意代理契約
見守り契約は、あくまで本人と連絡を取るなどして本人を見守るというものにすぎないので、本人の財産を管理したり、対外的に本人に代わって契約を結んだりすることはできません。
しかし、任意後見契約を結んだ方の中には、後見が開始する前であっても重要な財産の管理を任せたい、まだ判断能力に不安はないが、体調がすぐれないので日常的な支払いなどの金銭管理を任せたいなどの様々なニーズを持つ方がいます。
そのようなニーズを満たすには、任意後見契約とセットで任意代理契約を結び、任意後見開始前に任せたい事務だけを委任するといいでしょう。
死後事務委任契約
任意後見は本人の死亡によって終了するため、任意後見人は、本人の死亡後に本人の代理人として契約その他の手続をすることはできません。
そうなると、本人に相続人がいない場合や、相続人がいても遠方に居住している・疎遠であるといった事情がある場合、本人の死後の葬儀や埋葬、病院や施設の費用の清算、賃借物件の明け渡し等の事務手続をする方が誰もいないという事態に陥りかねません。
任意後見契約とセットで死後事務委任契約を結び、必要な死後の事務手続を受任者に任せることで、そのような事態を防ぐことができます。
まとめ
任意後見人を選任して任意後見制度を利用する場合、任意後見契約を締結するために、公正証書の作成費用がかかります。 判断能力の低下などによって家庭裁判所に申立てをすると、任意後見監督人が選任されますが、任意後見人や任意後見監督人に支払う報酬についても、費用として考慮しておきましょう。 発生する可能性のある費用を事前に把握しつつ、任意後見制度を効率よく利用するためにも、弁護士にご相談いただくことをおすすめします


- 判断力があるうちに後見人を選んでおきたい
- 物忘れが増えてきて、諸々の手続きに不安がある
- 認知症になってしまった後の財産管理に不安がある
- 病気などにより契約などを一人で決めることが不安である
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.02.26成年後見任意後見人を選任する場合の費用について解説
- 2024.12.02相続手続き代行遺言の捏造をした方にはどのような主張をすることができるか
- 2024.06.28相続全般交通事故で死亡した場合に保険金や慰謝料は相続できる?相続人は誰?
- 2024.05.15遺留分侵害請求遺留分が原因で争いになるのを防ぐためには