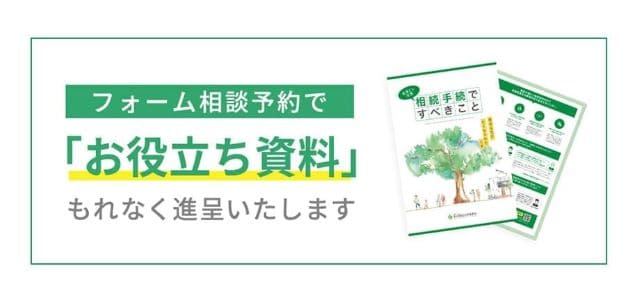- 不動産を所有していると固定資産税がかかる
- 遺言書がある場合は原則として、遺言書の内容に従って固定資産税を負担する
- 遺言書がない場合は原則として、法定相続分の割合で固定資産税を負担する
【Cross Talk 】遺産の中に不動産がある場合、固定資産税はどうなるの?
遺産の中に不動産があるのですが、固定資産税はどうなるのでしょうか?
相続に関する固定資産税は、被相続人の未納の分や、遺産分割が完了するまでに発生した分など、複数の場合があります。いずれにせよ、固定資産税は相続人が負担するのが原則です。
相続に関する固定資産税は、基本的に相続人が負担するんですね。各場合について詳しく教えてください!
遺産の中に不動産がある場合、不動産について固定資産税が課税されます。 相続に関する固定資産税は、被相続人の未納の固定資産税や、遺産分割が完了するまでに発生した固定資産税など、複数の場合があるので複雑です。 そこで今回は、遺産の中に不動産がある場合の固定資産税について解説いたします。
遺産の中に不動産がある場合の固定資産税の取り扱い

- 不動産を所有していると固定資産税がかかる
- 固定資産税の対象は主として土地や建物などである
固定資産税の対象となる不動産はどのようなものがありますか?
固定資産税の対象としては宅地・田畑・山林などの土地や、家屋・店舗・工場などの建物があります。また、一定の機械や船舶などが対象となる場合があります。
不動産を有していると固定資産税がかかる
不動産を所有している場合は、不動産に対して固定資産税がかかります。 固定資産税とは、土地や家屋など、固定資産税の対象となる物件の所有者に対して課される税金です。対 象となる不動産の所在地の市町村(東京23区の場合は東京都)が課税します。固定資産税の税額は、固定資産税の対象となる不動産の価格をもとに算定されます。 固定資産税の税額の基準となる価格を、固定資産税評価額といいます。固定資産税評価額は3年に1度の割合で更新されますが、一般に不動産の実売価格の7割程度が設定されます。
不動産として対象となる財産
不動産とは、土地及びその定着物を指し、不動産以外のものは全て動産とされています。 土地の定着物とは、土地に付着して容易に移動させることができないもので、取引観念上も継続的に土地に付着した状態で使用されると認められており、建物がその典型例です。固定資産税がかかる対象
固定資産税の対象となる物件を、固定資産といいます。一般的な固定資産として、以下のものがあります。・家屋・店舗・工場・発電所・変電所・倉庫・その他建物
・構築物・機械・装置・工具・器具・備品・船舶・航空機などの事業用資産のうち一定のもの
遺産分割前に発生した固定資産税はどうなる
被相続人が亡くなってから遺産分割前に発生した固定資産税は、原則として相続人全員が支払いの義務を負います。 固定資産税は1月1日が基準になりますが、その時点で既に被相続人が亡くなっている場合は、その固定資産税は被相続人ではなく、相続人に対して課税されます。例えば、被相続人が令和3年10月に亡くなっており、令和4年1月1日に固定資産税が発生した場合、その固定資産税は相続人に対して課税されているのです。 仮に固定資産税の対象である不動産の名義が被相続人のままであっても、名義変更が終わっていないだけであり、固定資産税は相続人に対して課されます。
1月1日の時点で遺産分割が成立していない場合、固定資産税の対象である不動産は相続人全員が共有している状態なので、固定資産税も相続人全員が法定相続分の割合で支払いの義務を負っています。
例えば、相続人が長男と次男の2人であり、固定資産税が10万円の場合は、それぞれの法定相続分(1/2ずつ)として5万円ずつ支払い義務があります。 ただし、1月1日の時点では遺産分割が終わっていなくても、固定資産税の納付期限までに遺産分割が終わった場合は、対象の不動産を相続した相続人が固定資産税を支払う例も見られます。
例えば、不動産Aの固定資産税の納付期限が、令和5年2月末日であるとしましょう。 遺産分割の結果、長男が不動産Aを相続することが令和5年1月中に決まった場合、協議により長男が固定資産税を全額納付する場合もあるのです。
いつの時点の価額で評価を行うか
固定資産税の算定の基礎となる評価額は、1月1日時点の評価額になります。土地や建物については、原則として3年ごとに評価を見直すことになっており、これを評価替えといいます。そのため、評価替えがなかった年度の評価額は、前年と同じということになります。
固定資産税の計算方法
固定資産税の税額は、課税標準額に税率をかけて計算します。 固定資産税の評価額=課税標準額となるのが原則ですが、住宅用地の特例などの税負担軽減の措置がとられる場合、評価額よりも課税標準額が低くなることがあります。また、標準税率は1.4%ですが、自治体によって異なる税率を設定している場合があるので、詳細については不動産のある市町村役場に確認する必要があります。
相続税申告をする場合控除の対象となる
相続税は、被相続人のプラスの財産から借入金等のマイナスの財産を差し引いた額を基礎に計算します。これを債務控除といいます。固定資産税は1月1日を基準にその時点の不動産の所有者に課されますが、その年の固定資産税の納付書が送られてくるのは一般的に4月から6月にかけてのことで、4回の分割による納付も可能です。そのため、固定資産税の未払いがあることは珍しくありません。
相続税を申告する際、このような固定資産税の未払いも債務控除の対象とすることができます。
準確定申告をする場合、費用(経費)となる
被相続人が個人事業主であった場合、被相続人が死亡するまでの所得について、被相続人に代わって相続人による準確定申告が必要です。 被相続人が個人事業として不動産賃貸業等を営んでいた場合、所有する賃貸不動産は事業用財産であり、賃貸不動産についての固定資産税は費用(経費)となります。そのため、被相続人が固定資産税の納付通知書を受け取ったがその支払いをする前に死亡した場合、被相続人の準確定申告を行う際、事業用不動産の固定資産税を費用(経費)として計上することができます。
相続放棄をした場合の支払い義務
相続放棄をした相続人は、その相続に関しては初めから相続人ではなかったものと扱われます。 そのため、相続放棄をした場合、原則として固定資産税を支払う必要はありません。ただし、例外的に相続放棄をしても固定資産税を支払わなければならない場合があります。 固定資産税は1月1日時点における所有者(固定資産税課税台帳に登録された方)に対して課されます。このように、固定資産税課税台帳に登録されている方に固定資産税を課税することを台帳課税主義といいます。 相続人が家庭裁判所に相続放棄の申述をしたが、年をまたいで相続放棄の申述が受理された場合、1月1日時点では相続人が固定資産税課税台帳に登録されています。
このような場合、台帳課税主義が優先されることになっているため、相続放棄をした相続人も固定資産税を支払わなければならなくなります。
遺産分割で固定資産税をどう取り扱うか

- 遺言書がある場合は原則として、遺言書の内容に従って固定資産税を負担する
- 遺言書がない場合は原則として、法定相続分の割合で固定資産税を負担する
分割納付の関係で、被相続人の固定資産税に未納があります。誰が固定資産税を負担するのでしょうか?
固定資産税について遺言書がある場合、原則として、遺言書の内容に従って固定資産税を負担します。遺言書がない場合又は遺言書に固定資産税の負担についての記載がない場合は原則として、法定相続分の割合によって各相続人が負担します。
遺言書がある場合
被相続人に対して課税された固定資産税に未納がある場合、相続人が固定資産税を納付する必要があります。 固定資産税は年4回に分けて納付できるのが一般的ですが、分割納付が終わる前に被相続人が亡くなってしまうことで、固定資産税に未納が発生する場合があるのです。例えば、合計16万円の固定資産税を、4月・7月・12月・翌年2月の4回に分けて納付するとしましょう。 4月と7月の分を納付した後、8月に被相続人が亡くなった場合は、12月と翌年2月の分の8万円について、固定資産税が未納になってしまいます。 被相続人の未納分の固定資産税については、相続人が納付義務を負います。 固定資産税の納付について遺言書に記載がある場合は、原則として、遺言書で指定された相続人が固定資産税を負担します。
例えば、「不動産Aは長男に相続させる。不動産Aの固定資産税については、被相続人に課されたものも含めて、全て長男が負担するものとする」という遺言書があったとしましょう。 遺言書によって、不動産Aの固定資産税については全て長男が負担するものと指定されているので、原則として長男が固定資産税を負担することになります。
遺言書がない場合
固定資産税の納付について遺言書がない場合は、原則として、法定相続分の割合で各相続人が固定資産税を負担します。 例えば、固定資産税に12万円の未納があり、相続人として配偶者・長男・次男の3人がいるとしましょう。 各相続人の法定相続分の割合は、配偶者1/2・長男1/4・次男1/4です。 法定相続分に基づいて未納の固定資産税を分けると、配偶者6万円・長男3万円・次男3万円ずつで固定資産税を負担します。なお、遺産分割協議をして誰が固定資産税を負担するかを決めて、特定の相続人が固定資産税を納付することもできます。 例えば、遺産分割協議によって次男が不動産を相続することが決まったので、次男が固定資産税を全額負担するとするなどです。
ただし、特定の相続人が固定資産税を負担すると決めたとしても、相手方(固定資産税を賦課する市町村)に対して主張できるわけではありません。 次男が固定資産税をきちんと納付しない場合は、他の相続人に対して相手方から請求される可能性があります。固定資産税についての手続き

- 不動産を現に所有している者の申告を行う
- 期限内に相続登記を行う
相続した不動産の固定資産税についての手続きはどうすればいいのですか。
相続で不動産を取得した場合、現に所有している方の申告や相続登記をする必要があります。
相続登記を行う
遺産分割が成立するなどして遺産の中に含まれる不動産の新所有者が決まった場合、相続登記を行い、対外的にも不動産の新所有者を明らかにする必要があります。相続登記は令和6年4月1日から義務化され、相続したことを知った日から3年以内に行わなければならなくなりました。正当な理由がなくこの期間内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が課されるおそれがあるので、期間内に相続登記をするようにしましょう。
なお、相続登記をすれば現に所有している方の申告は不要とされています。
現所有者の申告を行う
遺産分割協議が成立するなどして遺産の中に含まれる不動産の新所有者が決まった場合、固定資産税課税台帳の所有者の書き換えが必要になります。そのため、市町村役場に対し、不動産を現に所有している方の申告をする必要があります。この申告を行うことで、翌年1月1日を基準とする固定資産税は新所有者だけに課されることになります。
まとめ
遺産の中に不動産が含まれている場合、固定資産税の対象になります。 被相続人に対して課税された固定資産税について未納分がある場合、各相続人が法定相続分に応じて負担するのが原則です。 相続の発生後、遺産分割が完了する前に固定資産税が発生した場合も、原則として各相続人が法定相続分に応じて負担します。 遺産分割協議によって負担者を決めることもできますが、相手方に対して主張できるのではない点に注意しましょう。


- 相続対策は何から手をつけたらよいのかわからない
- 相続について相談できる相手がいない
- 相続人同士で揉めないようにスムーズに手続きしたい
- 相続の手続きを行う時間がない
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.03.03相続全般相続財産に不動産がある場合の固定資産税は誰が払う?遺産分割ではどう取り扱う?
- 2025.01.20相続全般任意後見制度の基礎知識・手続きの流れとその他概要について解説
- 2024.11.05相続放棄・限定承認遺産分割で相続分を放棄する場合と相続放棄の違いについて解説
- 2024.08.15相続手続き代行遺言書があっても相続人全員の合意があれば遺産分割協議は可能?