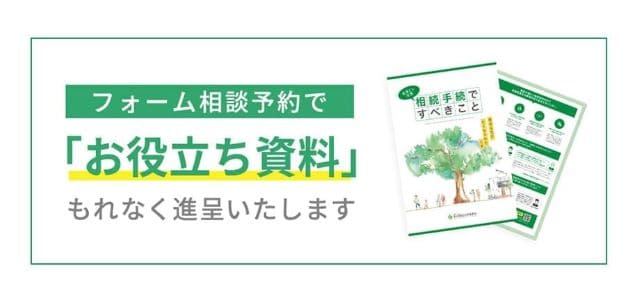- 息子の配偶者は相続人ではないが、特別寄与料を請求できる可能性はある
- 息子の配偶者に財産を譲る方法として、遺贈・死因贈与・生前贈与などがある
- 息子の配偶者と養子縁組をすれば、相続人として遺産を相続させることができる
【Cross Talk 】息子の配偶者に遺産をあげたい場合、どのような方法があるの?
息子の配偶者は私を熱心に介護してくれたので、ぜひ遺産を譲りたいと思っています。どのような方法がありますか?
息子の配偶者は相続人ではないので、遺産を相続することはできません。息子の配偶者に遺産を譲るには、遺贈・生前贈与・養子縁組などを活用しましょう。
息子の配偶者は相続人ではないんですね。遺贈や養子縁組など、息子の配偶者に遺産を譲る方法を詳しく教えてください!
熱心に介護をしてくれたなどの理由で、息子の配偶者に遺産を譲りたいと考える場合があります。 しかし、息子の配偶者は相続人ではないので、そのままでは遺産を相続することはできません。 息子の配偶者に遺産を譲るには、遺贈や養子縁組など、他の対応方法を考える必要があります。 そこで今回は、息子の配偶者に遺産をあげたい場合の対応方法について解説いたします。
息子の配偶者は相続人ではない

- 息子の配偶者は相続人ではない
- 息子の配偶者でも特別寄与料を請求できる可能性はある
お世話になった息子の配偶者に遺産を相続させたいのですが、可能でしょうか?
遺産を相続できるのは相続人ですが、息子の配偶者は相続人ではありません。ただし、息子の配偶者が被相続人に特別な寄与をした場合は、特別寄与料を請求できる可能性があります。
子どもがいる場合の相続人
被相続人に子どもがいる場合、子どもは第一順位の相続人です。 誰が相続人になるかは民法で順位が決まっており、1位:被相続人の子ども・2位:父母・3位:兄弟姉妹の順位で相続人となります(被相続人の配偶者は順位に関係なく相続人です)。順位が上の方がいる場合、下の方は相続人になりません。被相続人の子どもが相続人となる場合、被相続人の父母や兄弟姉妹は相続人にならないのです。
なお、被相続人の息子は第一順位の相続人ですが、息子の配偶者は被相続人にとっては子どもではないので、息子の配偶者は相続人にはなりません。特別寄与料の請求ができる可能性はある
息子の配偶者は相続人ではありませんが、場合によっては特別寄与料を請求できる可能性があります。 同居して熱心に介護を続けたなど、被相続人に特別な貢献をした相続人がいる場合に、通常よりも多くの遺産を相続できる制度として、寄与分があります。しかし、寄与分が認められるのは相続人だけなので、相続人ではない長男の配偶者が貢献をしたとしても、寄与分は認められません。
そこで、相続人以外の親族が特別な寄与をした場合に金銭を請求できる制度として、特別寄与料が創設されました。 特別寄与料を請求できるのは、被相続人の6親等内の血族・3親等内の姻族・配偶者です。長男の配偶者は被相続人の1親等の婚族なので、特別の寄与が認められた場合は、特別寄与料を請求することができます。
お気軽にご相談ください
初回相談無料
息子の配偶者に遺産をあげたい場合の対応方法

- 息子の配偶者に財産を譲る方法として、遺贈・死因贈与・生前贈与などがある
- 息子の配偶者と養子縁組をすれば、相続人として遺産を相続させることができる
息子の配偶者に遺産を譲る方法はありますか?
息子の配偶者に財産を譲る方法として、遺贈・死因贈与・生前贈与があります。息子の配偶者と養子縁組をすれば、相続人として遺産を相続させることもできますよ。
遺贈・死因贈与
息子の配偶者に遺産をあげたい場合の対処法として、遺贈や死因贈与があります。 遺贈とは、遺言書によって他人に遺産を譲る方法です。具体的には、遺言者(遺言をする人)が遺言書によって、相手を指定して自分の財産を贈与する旨の意思表示をします。
法が定める方式を満たした遺言書によって、有効な遺贈がおこなわれた場合、遺言者が亡くなった時点で効力が発生します。 遺贈をする相手は相続人に限られないので、相続人ではない息子の配偶者に対しても、遺贈によって遺産を譲ることが可能です。死因贈与とは、贈与者(財産を譲る人)が死亡した時点で、事前に指定した財産を受贈者(財産を受け取る人)に贈与する契約です。
死因贈与をする相手は相続人に限られないので、息子の配偶者に対しても遺産を譲ることができます。遺贈と死因贈与の違いは、一方の意思のみで行為ができるのか、当事者の間で合意が必要なのかです。
遺贈は遺言者の単独行為なので、遺言者が遺言書によって誰に遺贈をするかを指定すればよく、法的には相手の同意は不要です。死因贈与は贈与者と受遺者の間の契約なので、法的には当事者がお互いに合意する必要があり、合意しなければ契約は成立しません。
遺贈と死因贈与のもう一つの違いとして、行為をするために書類が必要かどうかです。 遺贈は遺言書に従う必要がありますが、遺言をするには遺言書を作成する必要があります。つまり、遺贈をするには遺言書を作成しなければなりません。 死因贈与は当事者の合意によって成立しますが、贈与契約を締結するために契約書を作成することは必須ではないので、法的には書類がなくても契約をすることができます。 ただし、死因贈与をする場合はあとでトラブルになった場合に備えて、契約書を交わすのが一般的です。生前贈与
息子の配偶者に遺産を譲る方法として、生前贈与があります。 生前贈与とは贈与者が生きている間に、自分の財産を受贈者に譲ることです。死因贈与との違いは、死因贈与は贈与者が亡くなった時点で財産を譲るのに対し、生前贈与は贈与者が生きている間に譲ることです。
生前贈与をする相手は相続人に限られないので、息子の配偶者に財産を譲ることができます。また、生前贈与は贈与者が生きている間に効力が生じるので、相続の発生を待たずに財産を譲ることが可能です。
死因贈与と同じく、生前贈与も贈与者と受贈者の契約なので、成立させるには当事者が合意しなければなりません。 生前贈与を締結するために契約書を交わすのは必須ではありませんが、トラブル防止や税金対策の観点からは、契約書を作成するのが一般的です。養子縁組
息子の配偶者に遺産を譲る方法として、息子の配偶者と養子縁組(普通養子縁組)をする方法があります。 息子の配偶者は相続人ではないので、そのままでは遺産を相続させることはできません。 しかし、養子縁組をして息子の配偶者を養子にすれば、相続が発生した場合に相続人として遺産を相続させることができます。 養子縁組をすると、養親(親になる人)と養子(子どもになる人)の間に法的な親子関係が生じるからです。法的な親子関係が生じることで、養親が亡くなって相続が発生した場合、養子は実子と同様に第一順位の相続人になります。 相続人として養子と実子がいる場合、養子と実子の相続割合は平等です。 例えば、被相続人が亡くなって総額1200万円の遺産があり、相続人として長男(実子)・長女(実子)・長男の配偶者(養子)がいるとしましょう。
養子と実子の相続割合は平等なので、法定相続分の場合、3人の相続人はそれぞれ400万円を相続します。生命保険の受取人
生命保険の受取人は、契約者が指定することができます。 生命保険金は、被相続人の遺産ではなく、受取人固有の権利とされています。 そのため。息子の配偶者を受取人とする生命保険に加入することで、息子の配偶者に保険金を取得させることができます。なお、生命保険金は受取人固有の権利ですが、相続税を計算する際には課税対象として扱われています(みなし相続財産といいます)。 生命保険金の受取人が相続人である場合、「500万円×法定相続人の数」までは非課税とされており、これを超える部分だけが課税の対象になるとされています。
しかし、生命保険の受取人が法定相続人ではない場合、上記計算式による非課税枠は認められません。 そのため、息子の配偶者を受取人とする場合、受取人を相続人にする場合と比較して、相続税が高くなるおそれがあることに注意が必要です。
特別寄与分
ここまでに紹介した方法は、息子の配偶者に財産を取得させたいと考える舅、姑が生前に行うことができる対策です。 これらの対策を講じる前に舅、姑が亡くなってしまった場合、相続人ではない息子の配偶者は遺産を取得できないのが原則です。ただし、平成30年の民法改正(令和元年7月1日施行)によって、相続人ではない親族の特別寄与料請求権が創設されたことから、息子の配偶者はこの権利を行使することで、寄与に応じた金銭を取得できる可能性があります。
特別寄与料の請求が認められる要件は、以下の通りです・被相続人に対し、無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと
・上記労務の提供によって被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたこと
そのため、残り二つの要件を満たせば、相続人に対して寄与に応じた金銭の支払いを請求することができます。
まとめ
息子の配偶者は相続人ではないので、遺産を相続させることはできませんが、親族にあたるので、特別寄与料の請求が認められる可能性はあります。 息子の配偶者に財産を譲るための対応方法として、生前贈与・遺贈・死因贈与などの方法があります。 息子の配偶者と養子縁組をすれば、遺産を相続させることも可能です。 息子の配偶者に特別寄与料が認められるかどうかや、遺産を譲るためにどの方法が最適かなどは場合によるので、まずは相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。


- 相続対策は何から手をつけたらよいのかわからない
- 相続について相談できる相手がいない
- 相続人同士で揉めないようにスムーズに手続きしたい
- 相続の手続きを行う時間がない
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.03.03相続全般息子の配偶者にも遺産をあげたい場合の対応方法を弁護士が解説
- 2025.02.25遺産分割協議遺産分割調停の必要書類について解説
- 2024.11.05遺言書作成・執行遺言書の必要性が分かる4つのケースについて解説
- 2024.07.16相続手続き代行未支給年金は相続放棄をしても受け取れる!相続放棄のルールの確認とともに解説