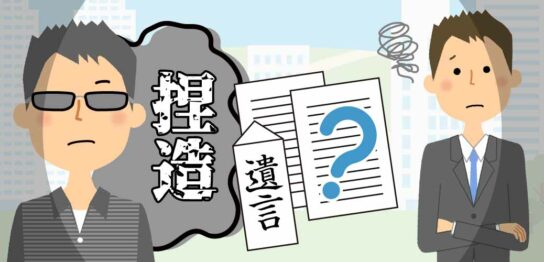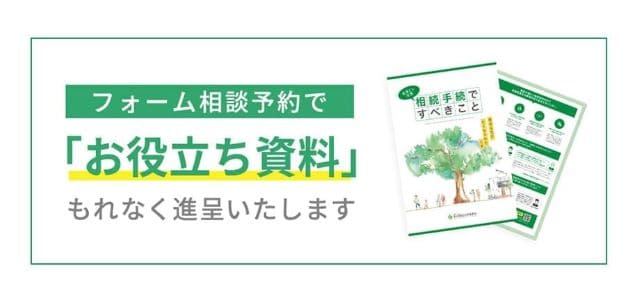- 遺言は法定相続に優先する
- 遺言がないときは相続人全員で遺産分割協議をする
- 遺言は方式によって要件が異なる
【Cross Talk 】遺言をするかしないかで何が変わるの?
私も高齢になってきて、周囲から遺言を書くことを勧められています。それほどたくさんの遺産があるわけではないので、わざわざ遺言を書くまでもないと思うのですが、遺言があるのとないのとで何が変わるのですか?
遺言がある場合はご本人の意思が尊重されるので、基本的に遺言通りに遺産を分けることになります。遺言がない場合、相続人の間で話し合って遺産の分け方を決める必要があります。法律には相続人が相続する割合など基本的なことが定められているだけなので、相続人の間でトラブルになるおそれがあります。
トラブルを防ぐには遺言をした方がいいんですね。
「大した遺産もないのに遺言なんて大げさじゃないか」「遺言をしたら何が変わるのか」といった疑問をお持ちの方は少なくないでしょう。 相続は、俗に「争族」と言われるほど親族間に深刻な争いを生じさせることがありますが、実は相続におけるトラブルの多くは、遺言をすることで防ぐことができます。 そこで今回は、遺言をしない場合とする場合の違いや、遺言をする場合の遺言の方式による違い等について解説いたします。 遺言をするかお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
遺言をしない・する場合でどのような違いがあるか

- 遺言をしない場合には法定相続
- 遺言をすれば原則として遺言どおりに遺産を分けることができる
遺言をしない場合と遺言をする場合でどんな違いがあるのですか?
遺言がある場合、亡くなった方の遺産は基本的に遺言どおりに分けられることになります。遺言がない場合、相続人全員で遺産の分け方について話し合いをする必要があり、話し合いがまとまらないときは家庭裁判所の手続で遺産の分け方を決めることになります。
遺言をしない場合の相続
遺言をしない場合、亡くなった方(被相続人)の遺産は法律で定められた相続人(法定相続人)が相続することになります。 相続人が複数いる場合は、相続人全員で遺産の分け方について話し合いをする必要があります(遺産分割協議)。遺言をする場合の相続
遺言がある場合、本人の意思が尊重され、基本的に遺言どおりに遺産を分けることになります。 相続人の間で遺産の分け方について話し合いをする必要はないのです。 ただし、兄弟姉妹以外の相続人には、相続によって得られる最小限度の利益(遺留分)があります。たとえば特定の相続人に全ての遺産を相続させる遺言をすると、遺留分を侵害された相続人は遺産を相続する相続人に対し、遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます(遺留分侵害額請求)。 ですから遺言をする場合は、相続人の間で遺留分をめぐる争いを生じさせないような配慮が必要になります。
どのような違いがあるか
遺言をしない場合とする場合の最大の違いは、本人が遺産の分け方について関与するか否かということです。 したがって、遺産の分け方について何か希望がある場合は、遺言をすべきということになります。それ以外の違いをいくつか紹介すると、遺言をすれば相続人以外にも遺産を取得させることができるということがあげられます。相続人ではないがお世話になった人に遺産を贈ることもできますし、法人(地自治体、施設、病院、研究機関など)に贈る(寄付する)こともできます。
また、遺言をする方が遺産を早く取得させることができ、相続人の間でトラブルが起こりにくいということも重要です。 「遺言をする場合の相続」で解説したとおり、遺言がある場合は基本的に遺言どおりに遺産が分けられます。 これに対し、遺言がない場合は相続人全員で話し合いをする必要があります。 話し合いにはそれなりの時間がかかることが多いですし、場合によっては一部の相続人と連絡が取れない等の事情で話し合いを始めることもできないという事態さえあり得るでしょう。また、話し合いができたとしても、うまくまとまるとは限りません。 民法は、相続人が複数いる場合について各相続人が相続する割合(法定相続分)を定めるのみで、遺産の具体的な分け方については何も定めていません。合意ができれば法定相続分と異なる遺産分割も可能ですが、そのためには相続人全員が合意する必要があります。
そのため、相続人の間で話し合いをしても、合意には至らないということは珍しくないのです。 もし相続人の間で合意ができないと、家庭裁判所の遺産分割調停・審判という手続きで遺産の分け方などを決めなければなりません。このように、遺言がないと、遺産を受け取るまでに時間がかかり、相続人の間でトラブルも起きやすいといえます。
遺言をする場合の方式による違い

- 自筆証書遺言は費用がかからないが効力をめぐる争いになりやすい
- 公正証書遺言は費用がかかるが争いになりにくい
今のお話を聞いて遺言をしようと思うようになったのですが、これからどうすればいいですか?
まず、遺言にはいくつかの方式があり、費用や要件が異なることをおさえてください。代表的な方式としては自筆証書遺言と公正証書遺言があげられます。
どういう違いがあるのですか?
自筆証書遺言は自分で書く遺言で、費用がかかりませんが、遺言の効力について争いが生じるおそれがあります。公正証書遺言は公証人に作成してもらう遺言で、費用がかかりますが、効力をめぐる争いが起こりにくいというメリットがあります。双方のメリット、デメリットを比較してどちらにするかを決めればいいでしょう。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で書いた遺言のことを言います。 自筆証書遺言は、全文、日付、署名を自分で書き、押印しなければなりません(ただし、遺産の目録については、自書でなくても良いことになりました)。公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が作成する公正証書によってする遺言です。公証人は、裁判官、検察官、弁護士、法務局長などの長年法律関係の業務を行い、法務大臣から任命された方です。 全国各地の公証役場に赴くか、公証人に自宅や病院などに出張してもらって作成することができます。どのような違いがあるか
自筆証書遺言と公正証書遺言には、次のようにいろいろな違いがあります。自筆証書遺言は自分で書くため、費用がかからない(紙や封筒が必要になる程度です)のに対し、公正証書遺言は公証人の手数料がかかります(公証人の手数料の額は政令で定められています)。
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認(裁判官が相続人等の前で封を開け遺言の内容を確認する)という手続が必要になりますが、公正証書遺言の場合、検認は不要です。
自筆証書遺言は原則として自分で管理するので紛失や滅失のおそれがありますが、公正証書遺言は公証役場で保管されるため、紛失等のおそれがありません。 なお、2020年7月から法務局で自筆証書遺言を保管する制度の運用が始まったので、この点に関する違いは小さくなったと言えます。
自筆証書遺言は専門家の関与なしで作成することができるので、全文を自書するなど法律に定める要件をみたさず、無効とされる場合があります。 これに対し、公正証書遺言は、公証人という専門家が作成するので、形式的な不備によって遺言が無効となるおそれはありません。
自筆証書遺言は遺言の存在そのものや内容を秘密にすることができますが、公正証書遺言を作成するには二人以上の証人の立会いが必要となるので、遺言の存在や内容を完全に秘密にすることはできません。
自筆証書遺言の場合、遺言によって不利益を受ける相続人から、遺言は被相続人が書いたものではないとか、被相続人は認知症で遺言をする能力がなかったなどとして、遺言の効力が争われるおそれがあります。
これに対し、公正証書遺言の場合、公証人が遺言者の本人確認をいたしますので、他人が偽造することはできません。 また、公証人が本人と会い、証人2人も立ち会いますので、明らかに本人の判断能力に問題があるようなケースでは、公正証書遺言を作成することはできません。そのため、本人に遺言をする能力がなかったと争われることも、相当程度防ぐことができます。
まとめ
遺言がある場合とない場合の違いなどについて解説しましたが、いがかでしたでしょうか? 遺言をしようと思われた方は、法律の定める要件をみたした遺言をするため、事前に相続に詳しい弁護士にご相談するといいでしょう。


- 遺言書が無効にならないか不安がある
- 遺産相続のトラブルを未然に防ぎたい
- 独身なので、遺言の執行までお願いしたい
- 遺言書を正しく作成できるかに不安がある
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2024.07.16遺言書作成・執行遺言書を作成するために必要な費用は?弁護士に依頼するメリットや注意点についても解説!
- 2024.05.15相続税申告・対策遺留分侵害額請求をした場合の相続税について解説
- 2024.01.22相続全般不動産の相続で必要な登録免許税とは?計算方法や納付方法について解説
- 2023.09.17遺留分侵害請求相続人の具体的相続分と法定相続分・指定相続分の違いは?